広島県内では、新型コロナウイルス感染症の拡大が続いており、県独自の警報が発令されました。また、インフルエンザによる学級閉鎖も報告されており、両感染症への警戒と対策が求められています。本記事では、現在の感染状況と、私たち一人ひとりができる予防策について詳しく解説します。
広島県が新型コロナ医療ひっ迫警報を発令
県内全体の感染状況と警報発令の背景
2023年(令和5年)5月8日以降、新型コロナウイルス感染症は感染症法上の「5類感染症」に位置づけられています。
しかし、広島県は2025年9月18日、新型コロナウイルス感染症の患者数増加を受けて、県独自の「新型コロナ医療ひっ迫警報」を県内全域に発令しました。これは2024年7月25日以来、今年初めての警報発令となります。
最新の報告(2025年9月8日から9月14日の第37週)によると、県内の定点医療機関94施設からの報告患者数は合計875人となり、1医療機関あたりの平均患者数は9.31人に上りました。この数字は前週から69人増加しており、4週間前のおよそ1.8倍に相当し、5週連続の増加傾向を示しています。
県は、将来的な医療提供体制への負担増大を防ぎ、県民への注意喚起を促すために、この警報を発令しています。現時点では、重症化しやすい高齢患者の割合が低いため、医療機関が差し迫ってひっ迫している状況ではないとされていますが、今後の感染拡大への警戒が必要です。
地域別の感染状況と特に警戒が必要な地域
県内では特に東部地域で感染が拡大しています。尾道市や三原市を含む東部保健所管内では、1医療機関あたりの平均患者数が13.56人に達し、県が定める警報基準の13人を上回りました。
福山市においても、医療ひっ迫注意報の開始基準値である定点当たり8人を超過しており、感染が拡大しています。2025年(令和7年)第34週(8月18日から8月24日)には、福山市の定点医療機関12機関から127人の報告患者がありました。福山市には、2025年8月21日に「新型コロナ医療ひっ迫注意報」が発令されています。
広島市でも、9月10日の時点で1医療機関あたりの患者数が8人を超え、県の注意報基準を上回ったと報告されています。呉市保健所管内では、同週の定点あたり患者数は7.33人でした。
夏休み明けの子どもたちの感染増加
夏休みが終わって以降、新型コロナウイルス感染症の患者数は10代以下で顕著に増加しており、全体の約半数を占める状況です。具体的には、10代の患者が228人(26.1%)と最も多く、次いで0歳から9歳が207人(23.7%)と報告されています。この増加は、夏休み明けに保育施設や学校などで集団生活が再開されたことに関連していると見られています。
三次市では、吉舎中学校の1年生で学年閉鎖が実施された事例もあります。1学年の生徒5名が新型コロナウイルス感染症で欠席し、その後2名の生徒が発熱や体調不良を訴えたため、学校医との相談を経て、校長が学年閉鎖を決定しました。これは三次市における今年度初の新型コロナウイルスによる学年閉鎖でした。
流行する変異株「ニンバス」の特徴
現在、広島県内で流行の中心となっているのは、オミクロン株から派生した「ニンバス」と呼ばれる変異株(正式名称NB.1.8.1)です。このウイルスの感染力は「過去最高レベル」と評されており、喉に非常に強い痛みを感じることが大きな特徴です。一部の患者は「カミソリを飲んだような痛み」と表現するほどの強い痛みを訴える一方で、発熱など比較的通常の症状で経過する患者もいるとのことです。
専門家は、若い世代にとってはインフルエンザと同程度の症状である可能性があると指摘していますが、高齢者や基礎疾患を持つ人々は重症化のリスクが一定程度あると考えられています。
新型コロナウイルス感染症の主な症状は、発熱、咳、全身倦怠感といった風邪のような症状ですが、頭痛、下痢、結膜炎、嗅覚や味覚の障害を伴う場合もあります。ウイルスの排出期間には個人差がありますが、一般的に発症の2日前から発症後7~10日間は感染性のウイルスを排出していると言われています。特に発症後3日間は排出量が非常に多く、5日間経過後も大きく減少するものの、症状が軽快した後も一定期間ウイルスを排出する可能性があるため、注意が必要です。
インフルエンザの流行状況とシーズン初の学級閉鎖
県内での学級閉鎖発生
2025年9月18日、三原市の中学校で、今シーズン初となるインフルエンザによる学級閉鎖が確認されました。対象となったのは中学3年生の2クラスで、9月10日の時点で71人の生徒のうち28人が発熱や喉の痛みなどを訴え、そのうち21人が病院でインフルエンザと診断されました。これらの2クラスは9月12日まで学級閉鎖となりました。
今回の学級閉鎖の報告は、9月9日時点で過去10年間で2023年9月4日に次ぐ2番目の早さとなっています。患者からは発熱、咽頭痛、関節痛、嘔吐、頭痛などの症状が報告されています。
広島県全体のインフルエンザ流行状況
広島県では、インフルエンザシーズンを毎年第36週(9月頃)から翌年の第35週までと定め、情報提供を行っています。2025/2026年シーズンは、令和7年9月1日から令和8年9月30日までです。
現在、広島県内ではインフルエンザの「流行入り」「注意報」「警報」は発令されていません。しかし、2025年第37週(9月8日から9月14日)の広島県全体の定点当たり報告数は0.37人(報告患者数35人)となり、前週(第36週)の0.30人(報告患者数28人)と比べてわずかな増加傾向が見られます。保健所別では、東部、福山市、広島市保健所管内で、定点当たり報告数が前週より増加しています。
インフルエンザの基本的な知識
インフルエンザは、インフルエンザウイルスによって引き起こされる急性呼吸器感染症です。毎年多くの患者が発生し、症状が重くなることが多いため、一般的な風邪とは区別して考えるべき疾病です。
ウイルスに感染すると、1~3日間の潜伏期間を経て、通常38℃以上の高熱、頭痛、全身の倦怠感、筋肉痛、関節痛などが突然現れます。その後、咳や鼻汁などの上気道炎症状が続き、約1週間で治癒しますが、風邪に比べて熱が高く、全身症状が重いのが特徴です。
特に高齢者や慢性疾患を持つ患者は、肺炎などの合併症を併発し、症状が重篤化したり死亡する事例もあるため、注意が必要です。また、小児では、まれにインフルエンザ脳炎・脳症を発症することがあるため、症状の経過をよく観察する必要があります。
感染経路としては、患者の咳やくしゃみに含まれるウイルスを吸い込むことによる「飛沫感染」と、ウイルスが付着したタオルなどの物品を介する「接触感染」があります。感染者がウイルスを多く排出するのは発症から約3日目までと言われており、この期間は特に注意が必要です。
感染症対策
市民に求められる基本的な感染対策
広島県は、新型コロナウイルスとインフルエンザ双方の感染拡大を抑制するため、以下の基本的な感染対策を徹底するよう県民に呼びかけています。
- 体調不良時の外出自粛
- 発熱などの体調不良がある場合は、不要不急の外出を控えましょう。
- 軽症の場合は自宅で療養し、検査や診断書発行のためだけの救急受診は避けましょう。
- 換気の徹底
- 室内の換気をこまめに行いましょう。
- 手洗い・手指消毒
- 外出から帰宅した際など、こまめに流水と石けんで手洗いをしましょう。手指消毒も効果的です。
- 特に指先、親指の付け根、手首などは洗い残しが多いため、念入りに洗うことが大切です。
- マスク着用と咳エチケット
- 医療機関や高齢者施設などを訪問する際は、マスク着用を徹底しましょう。人混みを避け、外出時にはマスクを着用することも推奨されます。
- 咳やくしゃみが出る場合は、不織布マスクを着用し、持っていない場合はハンカチなどで口と鼻を覆い、他の人から1メートル以上離れるなど「咳エチケット」を守りましょう。
- 鼻水や痰を含んだティッシュはすぐにゴミ箱に捨ててください。
- 適切な湿度保持
- 室内は加湿器などを利用し、湿度を50%から60%に保つよう心がけましょう。
- 健康維持
- 十分な睡眠をとり、バランスの取れた食事を心がけて体力を維持しましょう。
- 予防接種の検討
- インフルエンザについては、本格的な流行シーズンが到来する前に予防接種を検討しましょう。
- 予防接種は感染しにくくしたり、感染しても症状を軽くする効果が期待できます。高齢者は新型コロナワクチンの接種も検討してください。
- 早期の医療機関受診
- 症状が疑われる場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
- 特に腎臓疾患、心臓疾患、呼吸器疾患などの基礎疾患を持つ方、妊婦、高齢者、乳幼児は、合併症を起こしたり重症化する恐れがあるため、特に注意が必要です。
私の見解
県の早めの警報発出は妥当。現時点は「注意を要する上昇トレンド」であり、“行動の先手”が有効です(病院・学校・個人が同時に小さな対策を積み重ねれば、重症化と医療負荷の悪化をかなり抑えられます)。逆に受け身だと、数週間で急に負荷が増す可能性があります。
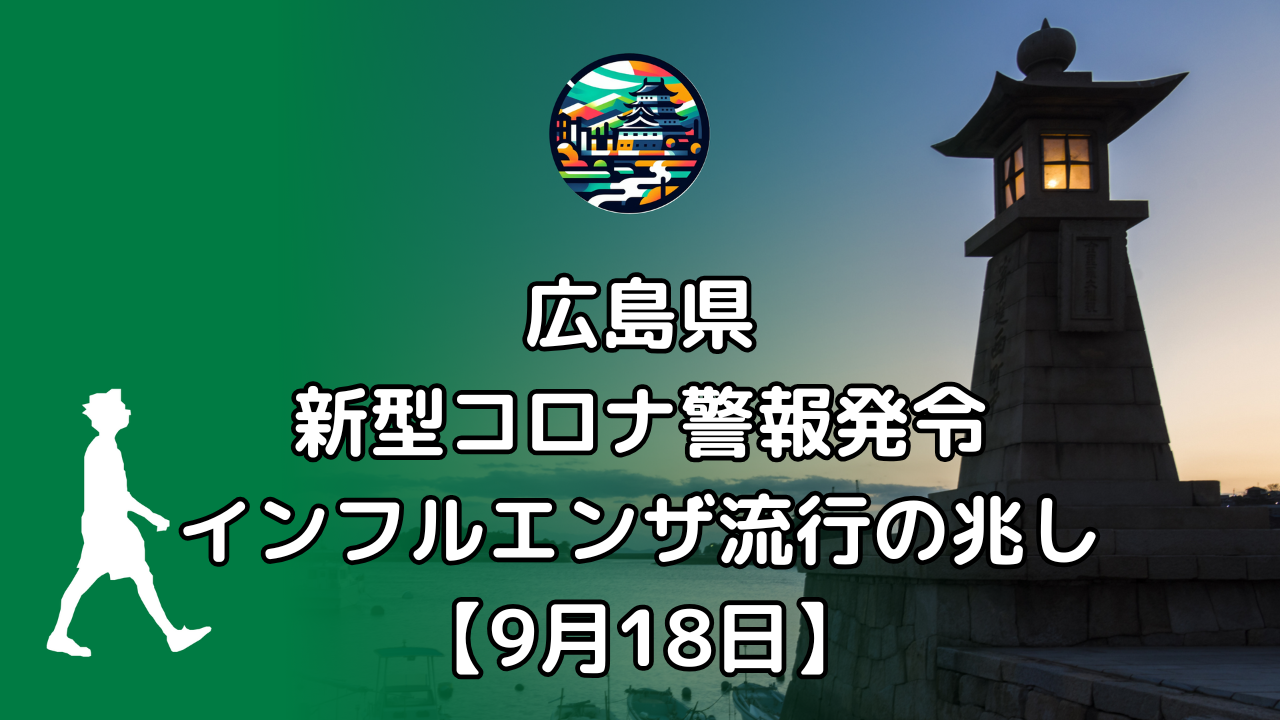
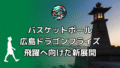
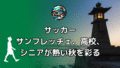
コメント