三次市で発生した大規模新米盗難事件
新米の収穫が本格化し、コメの価格が高騰する中、広島県三次市で大規模な窃盗事件が発生しました。
9月上旬、三次市に住む70代の農家男性の自宅倉庫から、収穫したばかりの新米約400kgが盗まれました。盗まれたコメはコシヒカリの「もみ」の状態で、倉庫内の乾燥機に保管されていました。地元JAによると、この量のコシヒカリは時価で15万円ほどに相当します。
被害は9月7日に稲刈りされた直後の新米で、男性が9月9日に盗難に気づき、警察に通報しました。警察の捜査によると、倉庫のシャッターは閉められていましたが、鍵はかけられていない状態だったということです。警察は窃盗事件とみて、倉庫に侵入した何者かを捜査しています。
繰り返される盗難被害と防犯対策の呼びかけ
広島県内では、今年の6月にも熊野町の農家の納屋から鍵がかかっていない状態で、袋詰めの玄米およそ250kgが盗まれる事件が発生しています。
警察は、収穫したコメを保管する場所には必ず鍵をかけること、また、鍵がかけられない場合は入り口の前に車を止めて侵入を阻むといった対策を取るよう呼びかけています。さらに、防犯カメラやセンサーライトを活用し、怪しい人物や車を見かけた場合は速やかに110番通報するよう警戒を強めています。
私の見解
三次市での大規模新米盗難事件は、単なる窃盗事件以上の意味を持っています。
背景には以下の点が考えられます。
- コメ価格の高騰と経済的動機
コシヒカリなどのブランド米は市場価格が高騰しており、転売目的の組織的犯行の可能性も否定できません。特に「もみ」の状態で盗まれたことは、精米前で保存性が高く、流通に乗せやすい点を狙ったとも考えられます。 - 農村部の防犯意識の弱さ
今回も鍵がかけられていない倉庫から盗まれており、農家の「地域だから大丈夫」という慣習的な防犯感覚が狙われています。過去の熊野町での事件と同様、侵入難易度が低いことが犯行を助長しているといえます。 - 今後への警鐘
今後も収穫期に同様の事件が続発する恐れがあります。農産物盗難は農家にとって経済的損失だけでなく、生産意欲の低下にもつながります。地域単位での監視体制(防犯カメラの共有利用、見回り、LINEなどによる不審者情報共有)が不可欠です。
つまり、この事件は「農産物の価値の上昇」と「農村の防犯脆弱性」が交錯して起きた典型例であり、個別の農家の問題ではなく地域全体の課題と捉えるべきだと考えます。
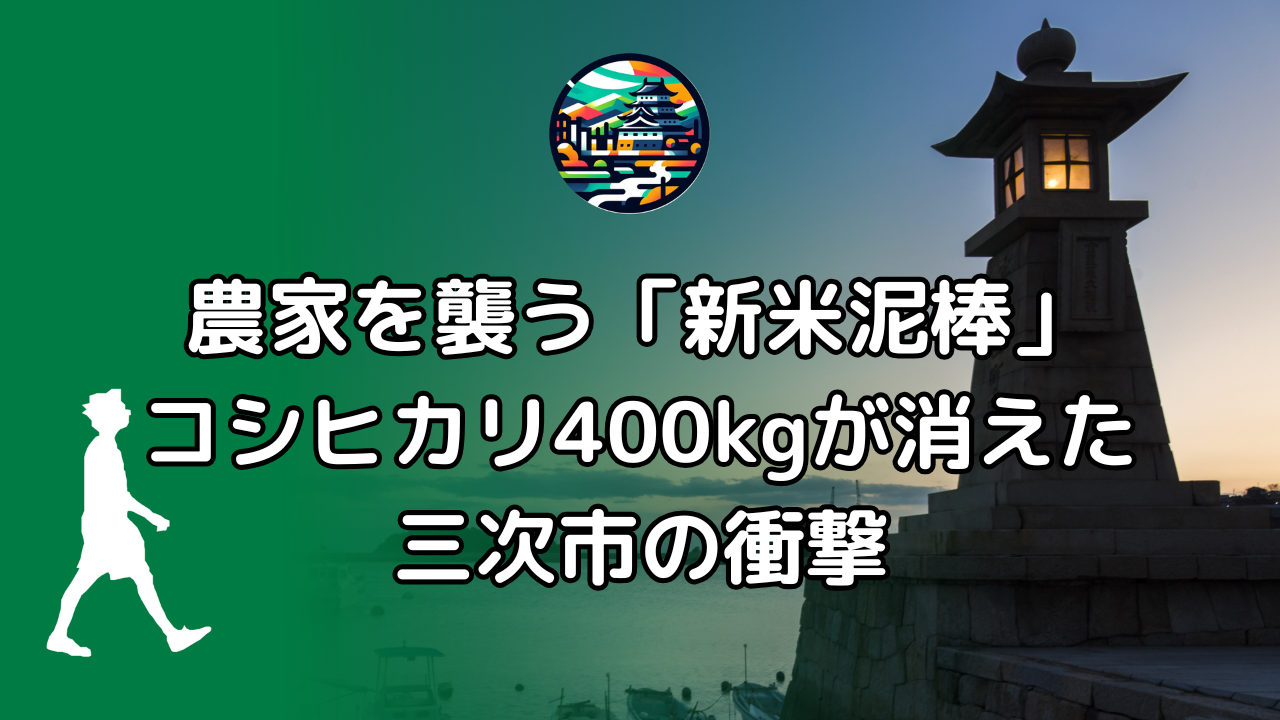
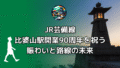
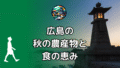
コメント