観光客増加に伴う遭難・救助要請の急増
世界遺産・宮島の弥山(標高約530メートル)は絶景が人気ですが、観光客、特に外国人観光客の増加に伴い、遭難やけがによる救助要請が相次いでいます。2025年の遭難者数は9月19日時点で22人と、前年の同じ時期と比べ約4倍近くに増加しており、119番通報件数も過去最多を上回るペースで推移しています。遭難者の半数以上は県外や外国からの観光客です。
遭難の要因と軽装登山への警鐘
遭難の原因としては、ロープウエーの営業終了後に日が暮れて道に迷うケースや、下山中のけがで動けなくなるケースが挙げられています。また、軽装(サンダル、半袖のスウェットなど)や遅い時間帯の登山が、けがや道迷いの原因となりやすいと指摘されています。観光客からは、想像していたよりも山道が険しく大変だったという声も聞かれています。
全国的に見ても、7月から8月の山岳遭難者数は統計史上最多(917人)を記録しており、「転倒」「道迷い」が主な要因です。警察は、遭難者の多くが天候確認の怠りや極端な軽装など、基本的な知識・経験が不足していたと指摘しています。
登山道点検と多言語での安全呼びかけ
秋の行楽シーズンを前に、県警と消防は9月19日に弥山の登山道を合同で点検しました。滑落の恐れがある場所や道に迷いやすい分岐点、過去に死亡事故が起きた急斜面などで、案内表示や立ち入り禁止標識の目立ちやすさが確認されました。警察の担当者は、特に危険なルートには「観光客はこれ以上入ったら危ない」といった具体的な表示が必要だと感じたと述べました。
警察と消防は、登山者に対し、サンダルなどの軽装で入ることの危険性を理解し、水分や食料を十分に用意し、日没前に下山するよう呼びかけました。外国人観光客の増加を受けて、英語や中国語などに翻訳されたチラシも配布されています。
私の見解
宮島・弥山の遭難急増は、観光客の増加と「登山のリスク認識不足」が重なった典型的事例です。標高530m程度の山でも、軽装や日没後の登山は命に関わる危険を伴います。特に外国人観光客や県外からの訪問者は、地形や気候への理解が十分でない場合が多く、統計的にも「転倒」「道迷い」が主な原因となっている点から、基本的な登山準備の重要性が浮き彫りになっています。
警察・消防による登山道点検や多言語での啓発は、観光地としての安全確保と、訪問者への注意喚起という両面で有効です。今後は、単なる注意呼びかけだけでなく、「入山規制」「危険ルートの明確化」「事前情報提供(公式サイトや宿泊施設経由)」など、訪問者が安全に登山計画を立てられる仕組みづくりも重要と考えられます。
総合的には、観光資源の保護と安全対策はセットで考える必要があり、事故が起きる前の予防が最大のポイントです。
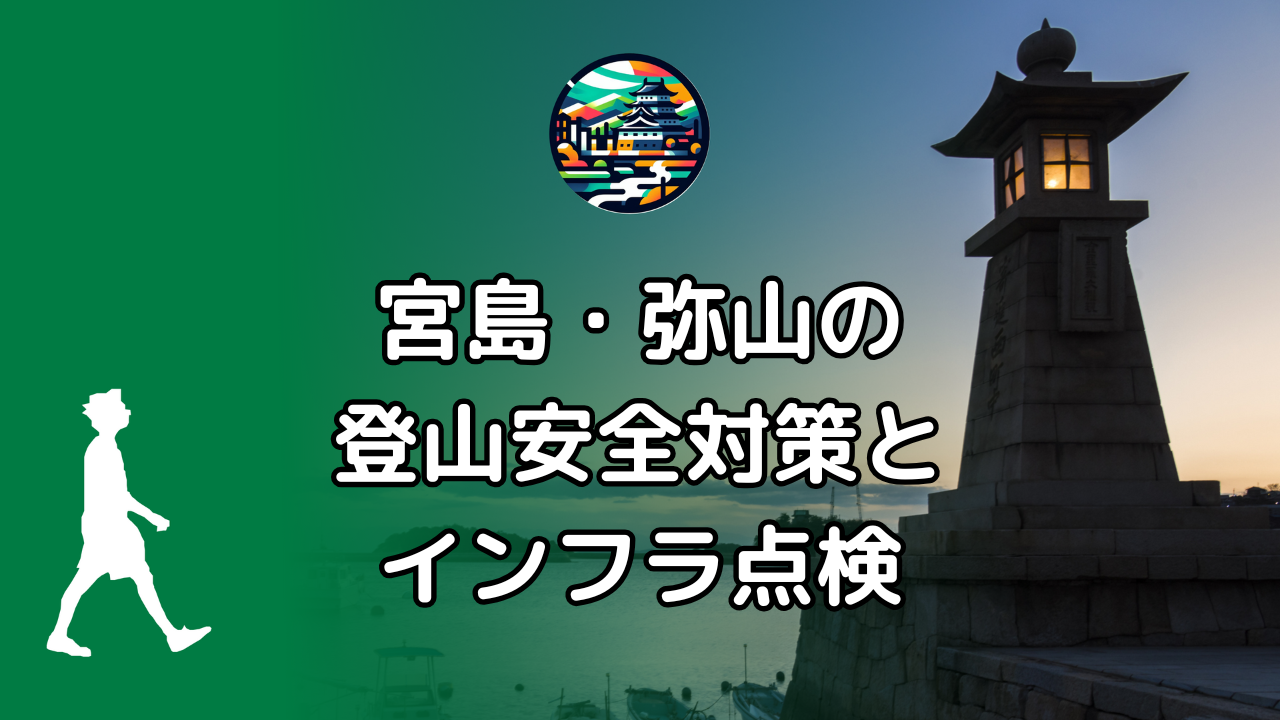
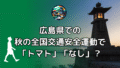
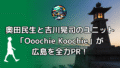
コメント