保育士・幼稚園教諭の養成校減少と対策
広島県内では保育士の「なり手不足」が問題視されており、県内の保育士の有効求人倍率は全国平均よりも高い水準が続いています(今年1月時点で6.44倍)。
一方で、保育士などを養成する短期大学が減少傾向にあり、安田女子短大や比治山大学が募集を停止しているため、来年度には広島市内の短大は広島文化学園短大の1校のみとなる見込みです。
この危機感から、広島文化学園大学が主催し、行政や幼稚園・保育園の園長などが初めて一堂に会する協議会が開催されました。協議会では、保育士を志望する学生を増やすことや、免許を持ちながら働いていない「潜在保育士」の掘り起こしが重要な課題として認識されました。
協議会に参加した大学理事長は、短期大学の卒業生が幼稚園・保育所に多く就職している現状を指摘し、幼稚園長からは、元保育士が復帰しやすいよう研修制度や職場体験の機会を設けるべきだという意見が出ました。
広島文化学園大学の関係者は、今後は園、行政、養成校がそれぞれの持ち味を活かし、相乗効果につながるようにPDCAサイクルを回していくことが大切であり、これがスタート地点であると述べています。
看護師確保の強化と専門学校の閉校方針
高齢化の進展に伴い看護師の確保は「喫緊の課題」とされていますが、広島市にある医師会は、学生数の激減により年間約7000万円の赤字が出ているとして、運営する看護専門学校を将来的に閉校する方針を固めました。
医師会は、災害医療体制の構築や救急医療体制の支援などとともに、看護師確保の強化と看護学校への支援を広島市と市議会議長に要望しています。特に、県内で唯一准看護師の養成ができる「安佐准看護学院」への財政支援も要望されました。
高卒採用の売り手市場とミスマッチ対策
高校生の新卒採用は、広島労働局の調べで求人倍率が過去最高の5.05倍(今年3月時点)となるなど、空前の売り手市場が続いています。現在の県内の高校生の求人倍率は4.33倍です。
企業側は若手人材の「確保」と「定着」のため、積極的に待遇改善に乗り出しており、主催企業の調査では、来年の初任給を上げる予定の企業は約7割に達しています。賃上げの理由は、社員の生活支援、社員の定着、高卒採用の応募増を目的としています。
また、就職後のミスマッチによる離職を防ぐため、高校生向けの合同企業説明会では、パイプを切る作業やさすまた体験など、実際の仕事内容を深く知ってもらうための体験スペースが設けられました。建設業の担当者は、若い人が集まることで会社に躍動感が出ると期待を述べ、業界のイメージが湧きにくい建設業をもっと身近に感じてもらいたいとしています。
私の見解
- 保育士・幼稚園教諭の養成校減少
- 養成校の減少は「なり手不足」と直結しており、潜在保育士の掘り起こしや復職支援が急務。
- 協議会で示されたように、大学・園・行政が連携し、研修制度や職場体験を組み合わせたPDCAサイクルで改善する方針は有効。
- ただし、短期大学の閉鎖により供給が減少するため、根本的な人材確保策としてオンライン研修や資格取得支援なども検討すべき。
- 看護師確保の課題
- 高齢化進展に伴う需要増に対し、学校運営の赤字問題が重なり、閉校リスクがある。
- 財政支援や准看護師養成校への支援を行政が実施することは、地域医療の安全確保に直結する重要課題。
- 高校生採用の売り手市場
- 求人倍率の高さは企業にとっても人材確保の競争が激しい状況。
- 体験型の合同説明会や待遇改善は、若者の定着やミスマッチ防止に有効。
- 長期的には、職業理解の深化やキャリア教育の充実も必要。
全体として、広島県内では「人材不足×養成機関減少×需要増」という構造的課題が顕在化しており、単発の施策ではなく、教育・行政・企業の連携と制度設計が不可欠です。
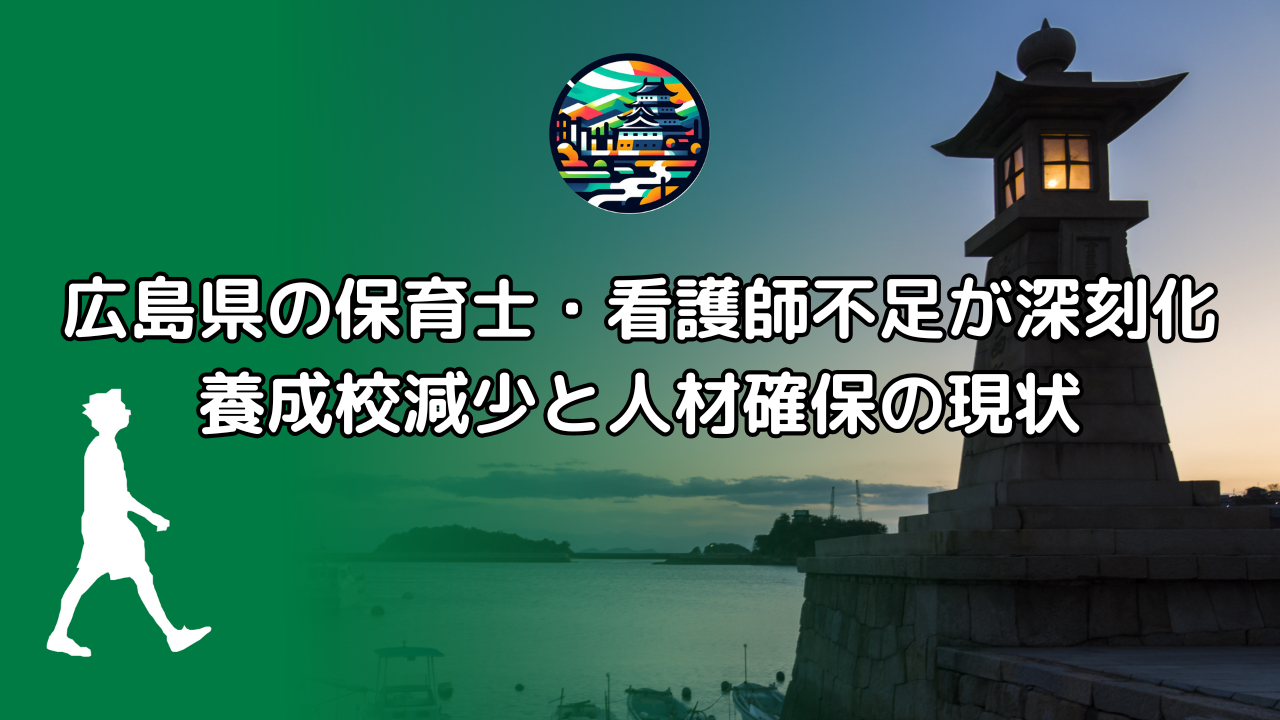
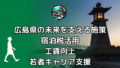
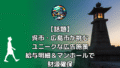
コメント