2025年9月、多聞櫓の遺構が福山城で初めて出土
幻の長大防御施設、礎石の発見が構造解明の鍵に
2025年9月、広島県福山市の福山城跡において、長屋状の防御施設である多聞櫓(たもんやぐら)の遺構が、発掘調査により初めて確認され、9月26日に報道陣に公開されました。
多聞櫓は本丸の西側、および二之丸の北側から西側にかけて建物を接続し、「渡櫓(わたりやぐら)」とも呼ばれていた構造物です。その総延長は約722メートルとされ、大坂城や名古屋城に次ぐ、国内屈指の規模を誇っていたと伝えられています。多聞櫓は明治期の廃城により失われており、これまでは絵図や古写真のみを基に研究が進められていました。
今回の発見は、重要文化財の伏見櫓から北側へ約5メートル離れた地点で、深さ20センチの地中から石が3個見つかったものです。これらの石は、多聞櫓の入り口付近の木材を支えていた礎石とみられています。
この痕跡の確認は大きな成果であり、将来的に多聞櫓を復元する際に重要な資料となると、福山市文化振興課の担当課長は述べています。市は現場を近く埋め戻す予定ですが、今後も別の地点での発掘調査を予定しています。
伏見櫓の再検討:転用材が示す築造の緊急性
伏見城からの移築を裏付ける刻銘と最古級の可能性
福山城は、初代藩主である水野勝成によって築かれた近世城郭であり、1622年(元和8年)に竣工しました。築城にあたり、伏見櫓や筋鉄御門など複数の建物が伏見城から移築されたことで著名です。
現存する伏見櫓(三重櫓)は国の重要文化財に指定されており、1951年(昭和26年)から1954年(昭和29年)にかけて行われた修理工事で、二階の梁から「松ノ丸ノ東やくら」という刻銘が発見され、伏見城からの移築が改めて立証されました。
伏見櫓は遅くとも1602年(慶長7年)頃の建築と考えられており、現存する三重櫓の中で熊本城宇土櫓と並んで最古級です。もし、豊臣秀吉が築いた木幡山伏見城からの移築であった場合は、現存最古の三重櫓となる可能性を秘めています。
多数の転用材と古式な架構・平面構成
2017年(平成29年)に実施された伏見櫓の現地調査(実測図作成、部材の新旧判定など)では、その建築年代を再検討する上で重要な特色が明らかになりました。特に、伏見櫓には転用材が多数使用されており、例えば太さが一辺9寸5分を超える柱(天守に使用される規模)が使われています。
これらの転用材は、移築元である伏見城松ノ丸東櫓の築造時から使用されていたと考えられます。転用材の使用によって、梁と根太の間に隙間が生じるなど、本来であれば設計上生じない誤差が発生し、それを繕うための現場合わせが行われていた痕跡が見られます。
これは、松ノ丸東櫓の築造時において、きちんとした設計のもとで部材を用意するのではなく、急いで造る必要があり、近辺に転用可能な部材が多数存在した状況をよく表していると考えられています。
また、伏見櫓の架構や平面形式にも古式な特徴が見られます。例えば、一階の牛梁(うしばり)が中心通りから北にずれた位置に架かっている点や、一・二階ともに室内に入側柱(内側の柱)が立つものの、身舎(もや)と入側(武者走)の区別が整然とせず明確ではない点は、比較的大きな櫓としては特異な事例です。
これらの古式な点は、伏見櫓が身舎と入側の区画形式が整う以前の状態を残している可能性を示唆しており、豊臣秀吉が築いた木幡山伏見城の松ノ丸東櫓からの移築であるという可能性を補強しています。
天守と他の現存建造物の特色
天守に復元された全国唯一の「鉄板張り」
福山城は1945年(昭和20年)の福山大空襲によって天守や御湯殿など多くを焼失しましたが、1966年(昭和41年)に天守などが復興されました。
天守は複合式層塔型5重5階地下1階という大規模なものでした。その最大の特徴は、防備上の弱点であった北面全体(最上層を除く)に、防御のために施されていたとされる鉄板張りです。これは全国の天守において類例がない非常に特殊な構造でした。
1966年の復興天守では再現されていませんでしたが、築城400年を記念した大規模改修(令和の大普請)を経て、2022年8月28日のリニューアルオープンに合わせて、この鉄板張りの外観復元が実現しました。
伏見櫓と対をなす筋鉄御門とL字型の鐘櫓
伏見櫓と並び、空襲を免れて現存する筋鉄御門(すじがねごもん)も国の重要文化財です。
これは本丸の正門にあたる脇戸附櫓門で、元和年間(1615-1624年)の建築とされています。名称の通り、一階の扉や門柱には筋状の鉄板が打ち付けられています。また、伏見櫓の近くにあり、二階の外壁意匠(白漆喰総塗籠の柱形・長押形)が伏見櫓と意匠を合わせた可能性があると指摘されています。
一方、福山市指定重要文化財である鐘櫓は、近世城郭で唯一本丸内に位置するとされますが、元々は多聞櫓(枡形門)の一部に組み込まれていた「鐘突堂」でした。周囲の多聞櫓が撤去された結果、L字型の構造の一部が単独で残り、現在の「鐘櫓」と呼ばれる姿となりました。
現在の建物は1979年(昭和54年)に修理・復興されたものです。鐘は毎日、午前6時、正午、午後6時、夜10時の定時に自動で鳴らされています。
私の見解
福山城の多聞櫓遺構の出土は、歴史的な空白を埋める重要な成果です。絵図や古写真だけに頼っていた研究に、現物の裏付けが加わることで、城郭史の解明が新たな段階へ進んだといえます。
伏見櫓に見られる転用材や古式な構造と合わせて考えると、福山城は単なる近世城郭にとどまらず、戦乱期から江戸初期へ至る時代の技術や価値観の変遷を映す「生きた資料館」のような存在に思えます。
今後の調査によって、幻とされた多聞櫓の姿が少しずつ明らかになることを期待します。同時に、現存建築や復元部分を訪ね歩き、歴史の断片に自分自身の視点を重ねる楽しみも広がっていきます。
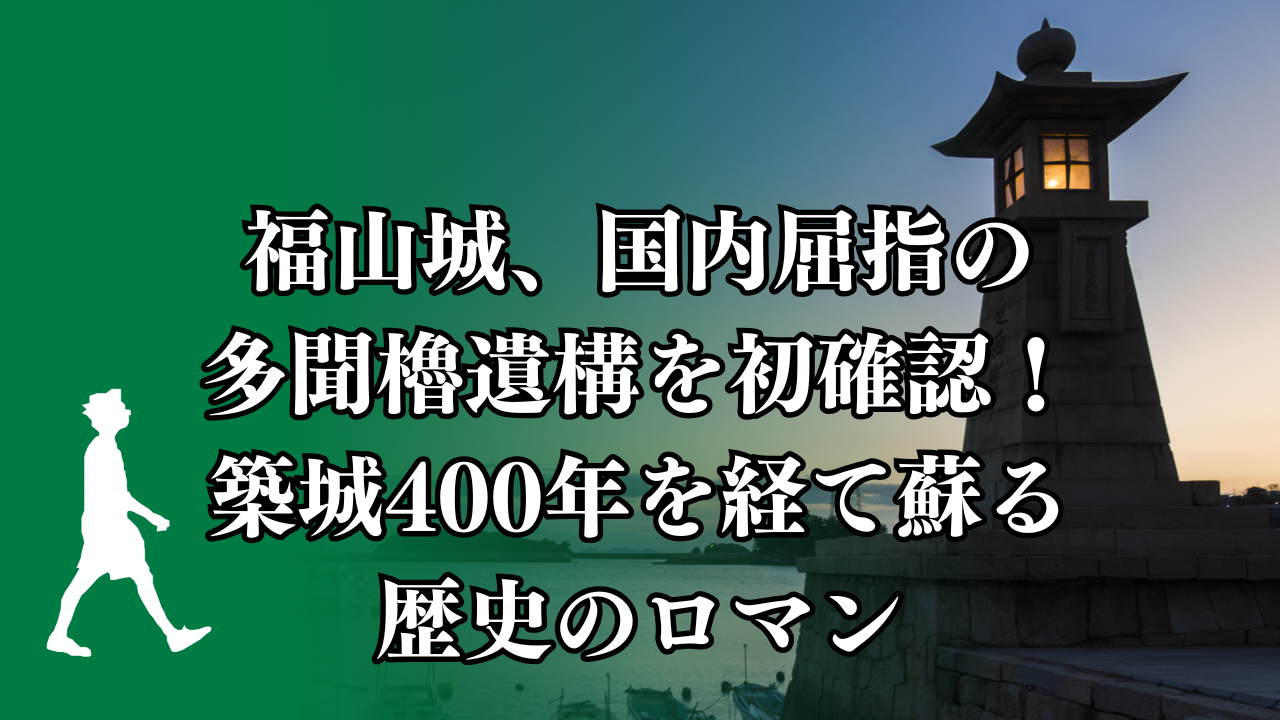
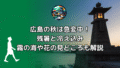
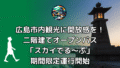
コメント