広島家裁、17歳元女子生徒の医療少年院送致を決定
裁判所が指摘した犯行の動機と更生の可能性
広島家庭裁判所福山支部は、同級生3人を刺したとして殺人未遂の疑いで逮捕・送致されていた17歳の元女子生徒について、医療少年院に送致する保護処分を決定しました。この決定は、9月29日(または30日)に開かれた審判で下されました。
松本英男裁判長は、少女が「極めて身勝手」であると指摘し、妬みや逆恨みといった感情から非行に及んだとし、その行為が社会に与えた影響も大きいとしました。一方で、裁判所は、少女が統合失調症を患っており、医療的治療が必要であることを認定しました。
さらに、少女が自身の抱える問題に向き合う姿勢を見せていることから、「保護処分による矯正が可能」であると判断。適切な医療措置と十分な矯正教育を行う必要があるとして、医療少年院への送致を決定したものです。この事件は9月5日付で家庭裁判所に送致されていました。
刑事責任能力の判断を経た司法手続き
本件では、犯行時の精神状態を調べるため、広島地検福山支部により鑑定留置が実施されました。
鑑定留置は2025年6月6日から9月1日までの約3カ月間にわたって行われ、その結果、検察は少女に対し刑事責任能力を問えると判断し、殺人未遂と銃刀法違反の容疑で家庭裁判所福山支部に送致しました。この司法判断は、更生教育と社会的制裁のバランスという観点から注目されていました。
事件の概要と動機、被害状況
通信制高校の教室内で発生した刺傷事件
事件は2025年5月21日午前10時15分ごろ、福山市三之丸町にある通信制高校「おおぞら高等学院」福山キャンパスの教室内で発生しました。当時17歳の女子生徒が、果物ナイフを用いて同級生3人を刺したとして、殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されました。
犯行は授業と授業の間の休憩時間中に発生し、教室内には当時約20人の生徒がいたとされています。少女は、ナイフを自宅から持ち込み、着席していた被害生徒らを後ろから突然、短時間に次々と刺したとみられています。
「殺意」と「人間関係のもつれ」
逮捕後の警察の調べに対し、女子生徒は「殺してやろうと思って刺した」と供述し、容疑を認めていました。
動機については、「校内の人間関係にもつれがあった」といった趣旨の話をしており、無差別ではなく特定の人を狙ったとみられています。特に、女子生徒と被害者側との間で、人間関係の「距離感の認識のずれ」があったことが、事件の動機につながったと警察はみています。
被害生徒3人は肩や背中、腕などを刺されましたが、いずれも命に別状はありませんでした。ただし、3人のうち1人は背中などを刺されて大けがを負い、他の2人は軽傷(全治1〜2週間程度)でした。
学校現場の対応と再発防止への取り組み
生徒の心の安全を最優先とした学校の対応
事件が発生したおおぞら高等学院は、社会に多大な心配と迷惑をかけたことに対し深くお詫びを表明しました。
学校は、被害生徒と在校生の保護者宅への訪問や電話連絡を通じて状況説明と謝罪を行い、何よりも生徒の安全確保と心のケアを最優先とする姿勢を強調しました。専門家(臨床心理士)も交えたカウンセリング体制の継続実施や、生徒相談窓口の強化、個別面談機会の充実が図られました。
安全対策の強化と授業の再開
事件を受けて、学校は一時的に登校による授業を見合わせましたが、生徒の状況把握が進んだことから、事件から1週間後の5月28日(水)に対面授業を再開しました。
再発防止策として、学校は以下の取り組みを徹底しています。教室への職員常駐(授業時間外も含む)とキャンパス内の巡回体制の強化、さらに監視カメラや非常ブザーといった安全設備の整備・拡充を進めています。
また、学校側は、これらの安全体制の整備を経て、入学を検討している方向けのイベントを、福山キャンパスを除く全国47カ所では6月23日(月)より、福山キャンパスでは7月23日(水)より再開しました。
主なタイムライン
- 2025年5月21日
- 午前10時15分ごろ、福山市三之丸町の通信制高校「おおぞら高等学院」福山キャンパスの教室で、17歳の女子生徒が果物ナイフで同級生3人を刺す。
- 被害生徒は肩や背中、腕を負傷。うち1人が大けが、2人は軽傷。
- 女子生徒を現行犯逮捕。警察の調べで「殺してやろうと思った」と供述。
- 5月28日
- 学校は生徒の安全確認後、対面授業を再開。
- カウンセリングや相談窓口の強化など、再発防止策を実施開始。
- 6月6日〜9月1日
- 広島地検福山支部で精神鑑定留置が実施される。
- 9月5日
- 少女が家庭裁判所に送致される。
- 9月29日
- 広島家庭裁判所福山支部が、統合失調症の治療と更生のため医療少年院送致を決定。
私の見解
裁判所が精神疾患を認定し医療少年院送致を決めたことは、治療と更生を重視する判断だと受け取れます。ただし、被害者の救済と社会的説明責任をどう担保するかは引き続き問われます。
再発防止には監視設備だけでなく、教職員の相談体制強化や早期発見のための医療・地域連携が不可欠です。被害者支援の長期的フォローも制度として整備すべきだと考えます。
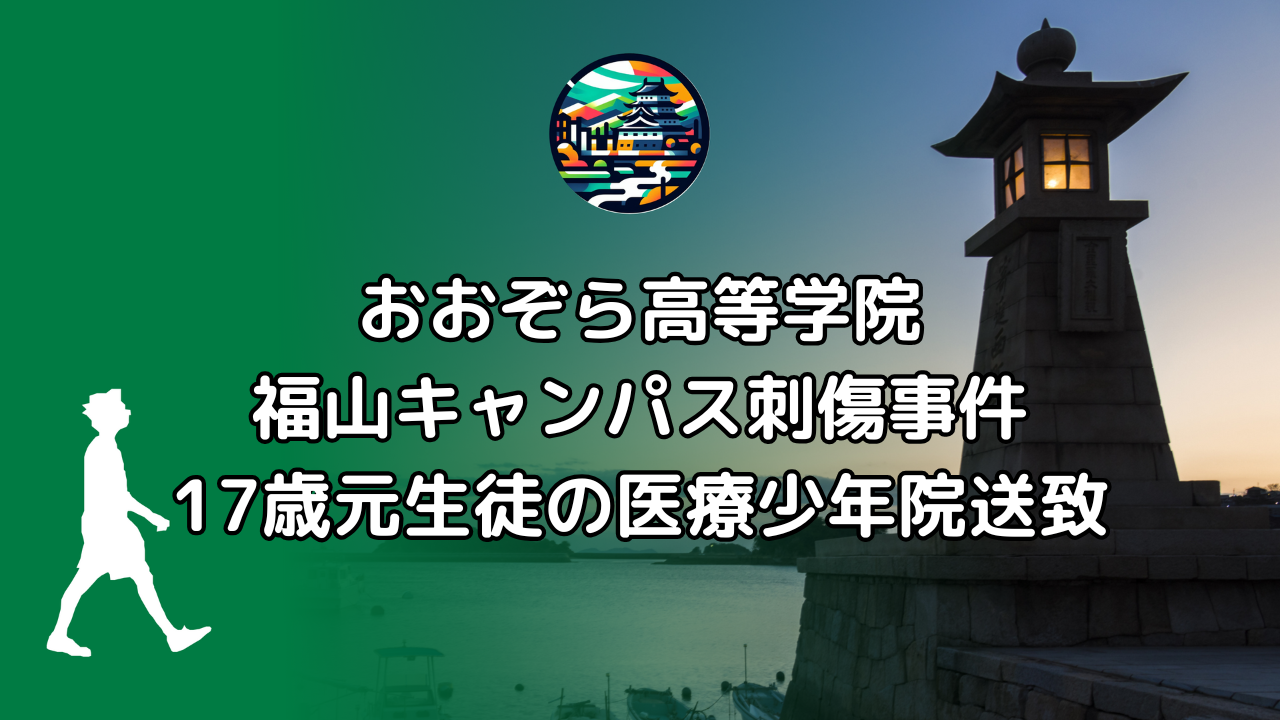
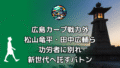
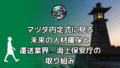
コメント