死亡事故現場を含む可部線2カ所をフェンスで封鎖
正式な踏切ではないものの、住民が日常的に線路を横断する「勝手踏切」について、JR西日本と広島市は対策を講じました。
特に、2024年10月に高齢男性が列車と接触し死亡する事故 が発生した広島市安佐南区祇園の勝手踏切を含む2カ所(下祇園駅と古市橋駅の間)が、地元住民や地権者などとの協議を経て、2025年9月に立ち入り防止の柵(フェンス)で封鎖されました。この封鎖工事は、9月30日未明に終電通過後におよそ2時間かけて実施されました。
JR西日本の担当者は、封鎖によって周辺住民の安全を確保できる点で効果は大きいと考えていると述べました。また、封鎖された地区の自治会長は、死亡事故が二度と起きないよう住民の命と安全を優先した判断であり、近隣住民も安心しただろうと話しました。広島市長も、関係者の主体的な判断と配慮によって処理が進んだことは良いことだと評価しました。
生活道としての利便性と封鎖の難しさ
この「勝手踏切」は長年、地域住民の生活道として利用されてきました。住民からは、踏切がなくなると遠回りしなければならず、バス停に行くのに便利だったため困るという声や、危険性は認識しているものの、人命には代えられないのでJRが通行を止めるのは仕方がないといった複雑な思いも聞かれました。
勝手踏切は、元々あった生活道(里道)に後から線路が敷かれた場所が多く、封鎖には地権者の同意や自治体による道路機能の廃止手続きが必要となるため、対策が一直線に進むことが難しい要因の一つとされています。専門家も、住民が生活上の必要性から封鎖に難色を示すケースが多いことを指摘しています。
JR西日本は、広島県内に460カ所以上、または540カ所以上 の勝手踏切を確認しており、中国地方では最多です。JR西日本は今後、これらを「里道」か「勝手道」(鉄道事業者単独で封鎖可能な場所)かに分けて調査し、自治体や住民と協力して順次封鎖を進める方針です。しかし、2024年4月に死亡事故が起きた別の勝手踏切(安佐南区緑井)では、依然として住民の同意が得られておらず、封鎖の目途は立っていません。
私の見解
今回の封鎖は、住民の利便性を犠牲にしてでも人命を最優先するという判断が下された点に大きな意味があります。安全の確保は鉄道事業者と地域社会の最重要課題であり、再発防止のための一歩だといえます。
一方で、勝手踏切が生活道として機能していた背景には、地域の長い歴史や日常の習慣があります。単純に「危険だから封鎖」で終わらせず、住民が安心して移動できる代替手段の整備が今後の課題だと思います。
JR西日本や自治体は、封鎖の推進と同時に、住民に納得してもらえる説明と代替ルートの提示を重視すべきです。安全と利便性のバランスをとる努力が、真に地域に寄り添った事故防止策につながると考えます。
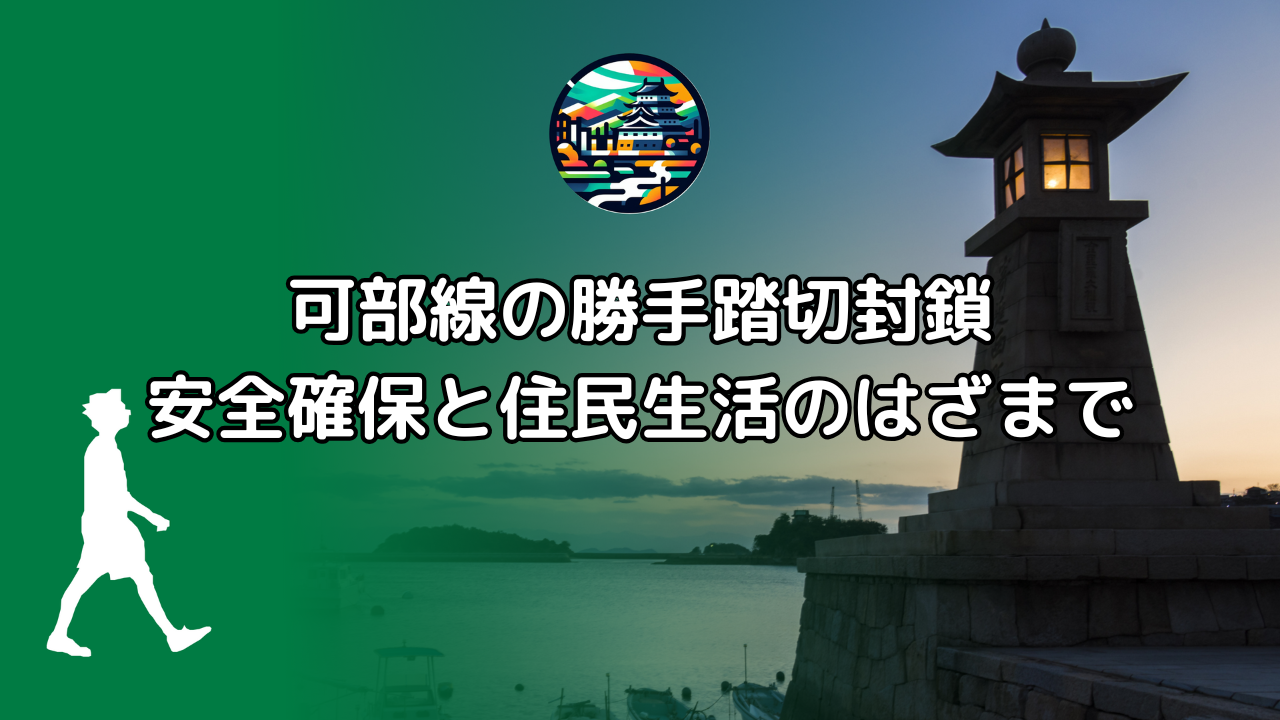
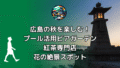
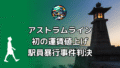
コメント