高齢者を狙った特殊詐欺の巧妙な手口
銀行協会職員を装いキャッシュカードを窃盗
広島県警は、銀行協会の職員を装ってキャッシュカードを盗み、現金512万円を引き出したとして、住所不定・無職の男(58歳)を窃盗の疑いで逮捕しました。この男は去年12月23日、共犯者と共謀し、広島市中区の84歳の女性に電話をかけ、女性宅を訪れてキャッシュカード6枚を盗んだ疑いが持たれています。
犯行グループは、まずNTTを名乗って「料金未納」を、次に警察官を名乗って「口座悪用の可能性」を告げ、最後に銀行協会職員を名乗る男が「新しいパスワード設定のため」と偽って訪問するという、段階を踏んだ手口を用いました。男は、女性にカードを封筒に入れさせ、その隙に別の封筒とすり替えて盗み出したとみられています。
男は容疑を認めており、警察は男が現金を引き出す役割を担っていたとして、組織的な犯行の全容解明を進めています。
過去最悪ペースで増加する特殊詐欺被害
広島県内では、今年の特殊詐欺の被害額が8月末時点で約14億3400万円に達し、過去最悪のペースで推移しています。特に警察官を騙る詐欺が増加傾向にあります。この状況に対し、県警と中国財務局は、県内20の金融機関の担当者と意見交換会を初めて開催し、最近の詐欺の手口や、疑わしい利用者への対応策を共有しました。
金融機関の担当者からは、「競争する分野ではなく皆で協力して詐欺防止に取り組みたい」という意向や、「窓口担当者にも手口を共有し、連携して防止に役立てたい」という考えが示されました。
信頼を裏切る専門職による金銭の不正着服
成年後見人による業務上横領事件
元司法書士の男(55歳)が、成年後見人として管理していた男性(53歳)の口座から現金を着服したとして、業務上横領の疑いで逮捕されました。男は2022年6月15日から約7カ月間にわたり、被後見人の口座から17回にわたり合計368万円(またはおよそ360万円)を引き出し、着服した疑いが持たれています。
男は2019年に家庭裁判所から男性の成年後見人に選任されていました。男は2023年2月に警察へ「財産を着服して横領した」という趣旨で自首し、容疑を認めています。警察は、男が他にも複数の成年後見人を担当していたことから、余罪の有無についても捜査を進めています。
虚偽の説明で屋根修繕工事の契約を勧誘
住宅を訪れ、必要のない屋根の修繕工事の契約をさせようとしたとして、神奈川県綾瀬市の自営業の男(38歳)と府中町の会社員の男(30歳)の2人が、工事契約勧誘の罪に問われました。2人は他の2人と共謀し、昨年9月と今年2月に広島市などの住宅を訪問し、「板金が剥がれているため、台風などの強風で落ちる可能性がある」「住民の不安を煽り、契約させた」「嘘を言って契約を取ろうとはしていない」、被告は「実際に板金が浮いていたから言った」と、いずれも起訴内容を否認しました。
私の見解
高齢者を狙う特殊詐欺は、電話や訪問を巧妙に組み合わせて不安を与える点が特徴です。今回の事件のように段階的に信頼を装う手口は、誰でも騙される可能性があります。疑わしい電話や来訪は一人で判断せず、家族や警察に相談することが重要です。
成年後見制度は弱者の財産を守るための仕組みですが、その信頼を裏切る行為は社会全体に深刻な影響を与えます。専門職による不正は制度そのものへの不信につながりかねません。監視やチェック体制を強化し、再発を防ぐ必要があります。
悪質な住宅工事の勧誘も後を絶ちません。「不安を煽って契約を迫る」行為は典型的な消費者被害のパターンです。住民側は複数業者に見積もりを依頼するなど冷静に対応し、行政や消費生活センターと連携することが被害防止に有効だと考えます。
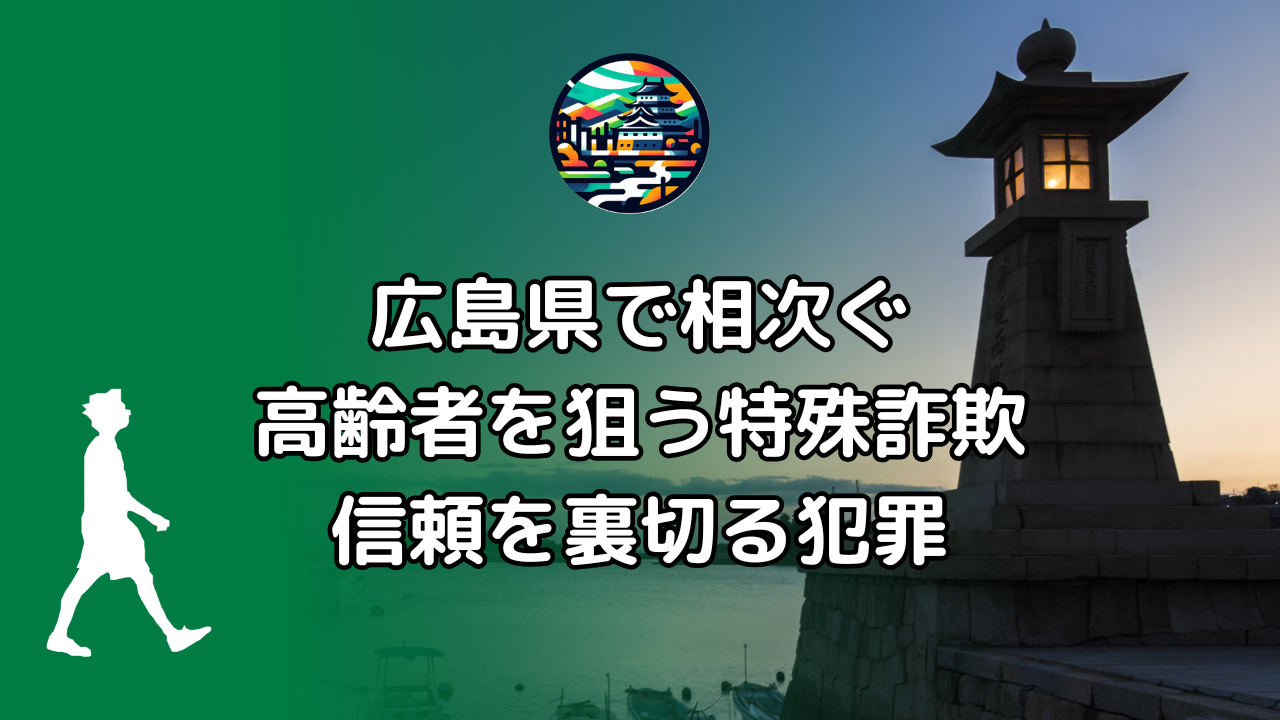
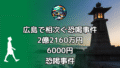
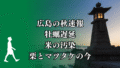
コメント