無印良品 広島アルパークで「捨てない精神」を体験
2025年9月6日(土)から9月7日(日)にかけて、無印良品 広島アルパーク 2F OpenMUJIにて、アップサイクルイベント「LIFE CYCLE MARKET ~余白のちから:アップサイクルで守る命と地球~」が開催されました。
このイベントは、「捨てない精神」で平和と環境を考えることを目的としており、廃棄されるものに新たな価値を加える「アップサイクル」の取り組みに焦点を当てています。
主催はものづくり企業である児玉ゴム商会で、製造工程で生じる「端材」の大量廃棄という課題に対し、新たな価値を与えて再利用するアップサイクルプロジェクトを2024年から立ち上げました。
被爆後の広島復興に息づく「アップサイクル」の精神
このイベントでは、特に「被爆とアップサイクルの関係」に焦点を当て、過去から学び、持続可能な未来を思考する機会を提供しています。アップサイクルの視点を通じて被爆の歴史を風化させずに深く知ってもらいたいということです。
被爆後の広島では、多くの人々が家を失い、瓦礫で作られたバラックで生活していました。当時の雨漏りに苦しむ人々を救うため、歴清社が紙にコールタールを塗った防水紙をバラックの屋根に設置した話や、瓦礫でバラックを作ったこと自体もアップサイクルの一例として紹介されています。
多彩な出展と体験型ワークショップ
イベントでは、様々な企業がアップサイクル製品の展示・販売を行いました。
- 児玉ゴム商会は、創業64年のゴム加工会社で、アップサイクルブランド「HAZAI WORKS」を始動し、端材で作る雑貨を販売しました。また、一流ブランドに選ばれる縫製会社である八橋装院とコラボし、プロバレーボールチーム「広島サンダーズ」の使用済みボールを活用した限定ポーチも販売しています。
- 創業120周年を迎える箔押し紙メーカーの歴清社は、「もったいない精神」から金銀紙の端材を活用した箔雑貨を提供しました。
- 株式会社シモヱは、カイハラデニムの糸と突板を融合した世界初のサステナブル素材「INDIGO」を提案。
- 有限会社 Sakuroは、千羽鶴再生紙や被爆樹木の剪定枝を再利用したキーホルダーを制作。
- 株式会社 FORESTWORKERは、切り株まで辿れるHIBARINGs材を使ったインテリア雑貨を販売。
- 千差株式会社 Sukima.は、広島仏壇の製造時に出る端材を利用した積木「ヤマヅミ」を販売しました。
体験型のコンテンツも充実しており、無印良品主催のワークショップでは、店舗で使用した広告用バナーをコインケースにアップサイクルする体験が提供されました(予約不要、参加費100円)。
また、ICHI DESIGN OFFICEのプロダクトデザイナーを講師に招き、小中学生向けに端材を使った雑貨制作ワークショップも開催され、デザイン思考やものづくりの面白さが伝えられました(予約制、参加費1,000円)。
広島出身の絵描きひィ仔さんによる「平和」と「アップサイクル」をテーマにした参加型ライブペイントも実施され、来場者も共に絵を描く機会がありました。
私の見解
今回の「LIFE CYCLE MARKET」は、単なるエコイベントではなく、広島の被爆の歴史とアップサイクルを結びつけた点に大きな意義があると思います。
- 被爆後の生活再建を「アップサイクル」と再定義した視点
瓦礫の活用や防水紙の提供といった復興の知恵を、現代のサステナビリティの文脈に接続したことは、過去と未来を橋渡しする重要な試みです。単なる「ものの再利用」ではなく、「命を守る工夫」としてのアップサイクルを伝えている点が強い説得力を持っています。 - 地域企業と文化の結びつき
ゴム加工、デニム、仏壇、箔押し、千羽鶴再生紙など、広島ならではの産業や文化資源が「もったいない精神」と結びつき、新しい商品や体験に昇華しているのが印象的です。これにより「地元の技術 × アップサイクル」が地域のブランド力向上にもつながっています。 - 体験型・参加型のアプローチ
ワークショップやライブペイントは、消費者を「観客」から「共創者」へと引き込み、捨てない精神を自分ごととして感じてもらう仕掛けになっていました。特に子ども向けワークショップは、次世代に「つくる楽しさ」と「資源を大切にする感覚」を伝える教育的な効果が期待できます。
総合すると、このイベントは「広島の平和文化」と「持続可能な社会づくり」を接続する実践例であり、無印良品という日常ブランドの空間を活かした発信力も相まって、多世代に訴える力を持っていたと考えます。

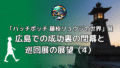
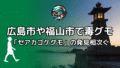
コメント