職員による硬貨の不正持ち出しとその結末
不足した硬貨と容疑の特定
造幣局広島支局(広島市佐伯区)において、新しい硬貨の材料となる回収貨幣が不正に持ち出される事態が発生しました。調査の結果、不足していたのは旧500円硬貨174枚、総額8万7000円分であり、当時、古くなった硬貨をコンテナに移し替える作業を担当していた60代の再任用男性職員が不正に関与した可能性が高いとされました。
監視カメラの映像と職員の供述
6月下旬から7月上旬にかけて、支局内の防犯カメラには、この職員が貨幣を掴んで持ち出すような不審な姿が複数回記録されていました。職員は内部調査に対し、不正を認め、「魔が差した」、「買い物に使った」 などと供述していました。造幣局は警察に被害届を提出しましたが、この不正に関与した職員はすでに死亡していることが明らかになりました。
過去にも発生していた不正
造幣局広島支局では、2000年にも職員が保管されていた500円硬貨500枚を持ち出す事案が発生しており、今回で同様の不正が2度目となります。造幣局は、この事態を極めて重く受け止めているとコメントしています。
管理体制の不備と関係者の処分
金属探知機の不適切な運用
今回の不正持ち出しを許した大きな原因として、造幣局は、金属探知機の運用が規定通りに行われていなかった点を挙げました。当時、職員は金属の付いたヘルメットを着用したまま探知機を通過しており、警報音が鳴ってもヘルメットによるものだと見過ごされていたということです。
責任者への懲戒処分と再発防止策
造幣局は、管理体制の不備を認め、監督責任として広島支局長など6人に対し、戒告などの懲戒処分を行いました。今後、造幣局は金属探知機検査の適切な運用を徹底するなど、管理体制の強化を図り、再発防止に努めるとしています。
私の見解
このような不正は、個人の一時的な過ちにとどまらず、組織の信頼を大きく損なう出来事です。造幣局という国家機関で発生したことは、社会全体に「制度の形骸化」への不安を与えます。日常的な業務の中でも、「慣れ」と「油断」が積み重なると、倫理意識の低下を招くことを改めて示した事例といえます。
特に注目すべきは、金属探知機の警報を「形式的に無視」していた点です。安全管理や内部統制は、運用の徹底があって初めて機能します。ルールが存在しても、それを「守る文化」が根づかなければ意味をなしません。これは官民を問わず、多くの組織に共通する課題です。
再発防止の取り組みが実効性を持つためには、単なる規定の強化ではなく、現場の意識改革が欠かせません。監督者が「見過ごさない姿勢」を示すことが、最も効果的な抑止力となります。倫理教育と現場点検の両輪で、組織全体が自浄作用を持つ体制づくりを進めることが求められます。
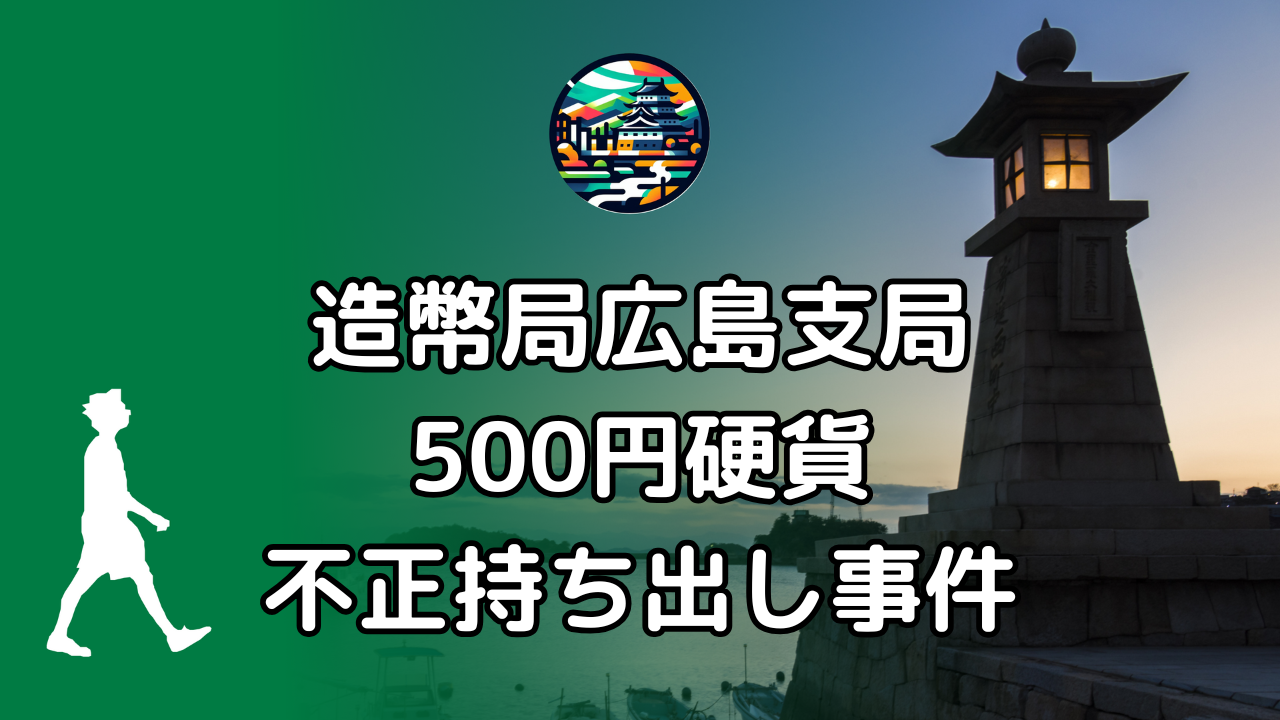
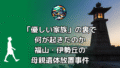
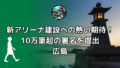
コメント