NHK大河ドラマ第63作『光る君へ』は、平安時代中期を舞台に、『源氏物語』の作者・紫式部の生涯を描く作品です。藤原道長が京都市上京区に建立した法成寺に関わる地名として伝わる福山市駅家町法成寺についても触れています。
紫式部の生涯を描く作品『光る君へ』
NHK大河ドラマ第63作『光る君へ』は、平安時代中期を舞台に、『源氏物語』の作者・紫式部の生涯を描く作品です。脚本を大石静、主演を吉高由里子が担当します。作品タイトルの「光る君」とは光源氏と、そのモデルのひとりといわれる藤原道長を指しています。
紫微垣の天蓬の星がいつになく強い光を放っている
このドラマは2024年1月7日から一年間放送予定です。物語は貞元2年(977年)、安倍晴明の「紫微垣の天蓬の星がいつになく強い光を放っている」というセリフから始まり、まひろが、深い絆を育むことになる三郎との出会いが描かれました。少女・まひろは後の紫式部、少年・三郎は後の藤原道長です。
藤原道長が建立した法成寺とは?歴史と現在の状況
藤原道長は晩年にあたる寛仁4年(1020年)、現在の京都府京都市上京区の京都府立鴨沂高等学校付近に無量寿院を建立しました。治安2年(1022年)には法成寺と改名しました。建立された地名から京極御堂とも呼ばれ、藤原道長の「御堂殿」「御堂関白」の異名の由来でもあります。天喜6年(1058年)2月23日に焼失しましたが、すぐに再建されました。鎌倉時代には大火や兵火などの災難に度々遭遇し荒廃し、現在はかつて法成寺があったことを示す石標が残っています。
福山市駅家町法成寺との関係
ところで法成寺は福山市駅家町にも現存する大字ですが、この地名は藤原道長が建立した法成寺に関わる地名として伝わっています。「岡の堂」や「岡の御堂」と呼ばれている、江戸時代に大庄屋をつとめた門田家の屋敷跡から平安時代の古瓦が出土し、そこに寺院が存在したことも関係しているのではないかと考えられています。
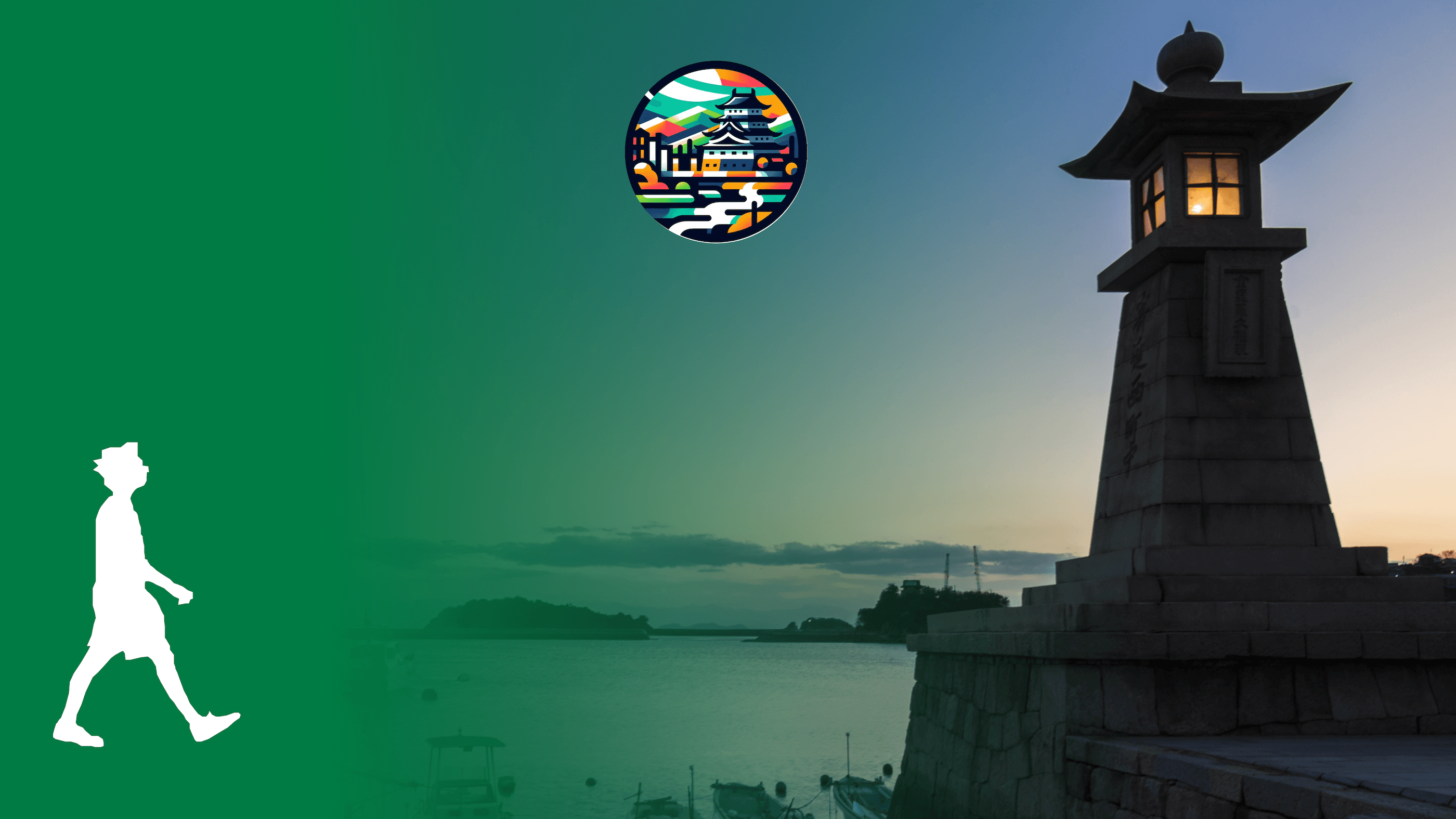

コメント