西日本豪雨を教訓に始まった取り組み
広島県福山市は、大規模災害などによる断水が発生した場合に備え、隣接する岡山県の井原市および笠岡市と、水道水を相互に融通するための連携を強化しています。この県境を越えた自治体間の協力は、全国的にも珍しい取り組みです。
この連携の背景にあるのは、7年前の西日本豪雨の教訓です。当時、広島県三原市で水道水の取水場が浸水し、三原市や尾道市で長期間の断水が発生しました。福山市では、他の水源からの水を広域連合企業団の水道管を経由して供給することで、一部地域での断水を回避できました。
この経験に基づき、福山市が笠岡市と井原市に提案し、災害時に水道水を融通しあう協定が2025年4月にそれぞれ締結されました。
具体的な連絡管の整備状況と能力
福山市は、笠岡市および井原市との県境付近の合計3か所で水道管をつなぐ作業を進めてきました。
福山市神辺町と井原市高屋町の県境では、7月中旬から工事が行われ、8月28日に長さ75メートルのポリエチレン製連絡管が地下70センチの場所に設置され、通水が確認されました。これにより、福山市と井原市間では、1日あたり300トン(約600世帯分)の水を送り合う能力が確保されました。
また、福山市と笠岡市の県境2カ所でも接続工事が進められ、9月18日にすべての水道管の接続作業が完了しました。福山市坪生町では、約340メートルの新たな水道管が取り付けられ、緊急時にバルブを操作して水が融通し合えることが確認されました。
住民の安心安全への貢献と今後の運用
一連の工事が完了したことにより、福山市は笠岡市と井原市に対して、1日あたり合計1300世帯分の水を融通できるようになる見込みです。敷設される連絡管は直径最大10センチ、長さは40メートルから340メートルです。
接続箇所には緊急時に開くバルブが設けられ、断水時に相互供給を可能にしますが、接続部分付近の取水栓からは給水車への送水も行えるようになります。福山市の担当者は、水源が異なる自治体間で水を相互融通することは減災につながり、市民の安心安全を提供できると強調しています。また、少しでも早く応急給水できることが、市民の安心安全につながるという見解も示されています。
井原市と笠岡市の担当者も、この整備により災害時の応急給水が可能になり、市民の安心安全の確保に役立つと述べています。
この県境を越えた水道水融通の取り組みは、岡山県内では初めての事例です。3市は今後合同訓練を実施し、ことし11月から本格的な運用を開始する予定です。
私の見解
福山市が笠岡市・井原市と連携して水道水を相互融通する取り組みは、西日本豪雨での断水被害の教訓を活かした、極めて実践的な減災策です。特に、県境を越えた自治体間の協力は全国的にも珍しく、災害時の住民生活の継続性を確保するモデルケースと言えます。
水道管接続の具体的能力(1日あたり最大1300世帯分の水を融通可能)や、緊急時に給水車へも送水可能な設計は、単なる理論上の連携ではなく「即戦力」としての価値があります。さらに合同訓練や本格運用の予定があることから、災害対応力の強化だけでなく、住民の安心感の向上にも寄与すると考えます。
この取り組みは、自治体間の境界にとらわれない柔軟な防災戦略の先駆例であり、他地域への横展開の可能性も高いと考えます。
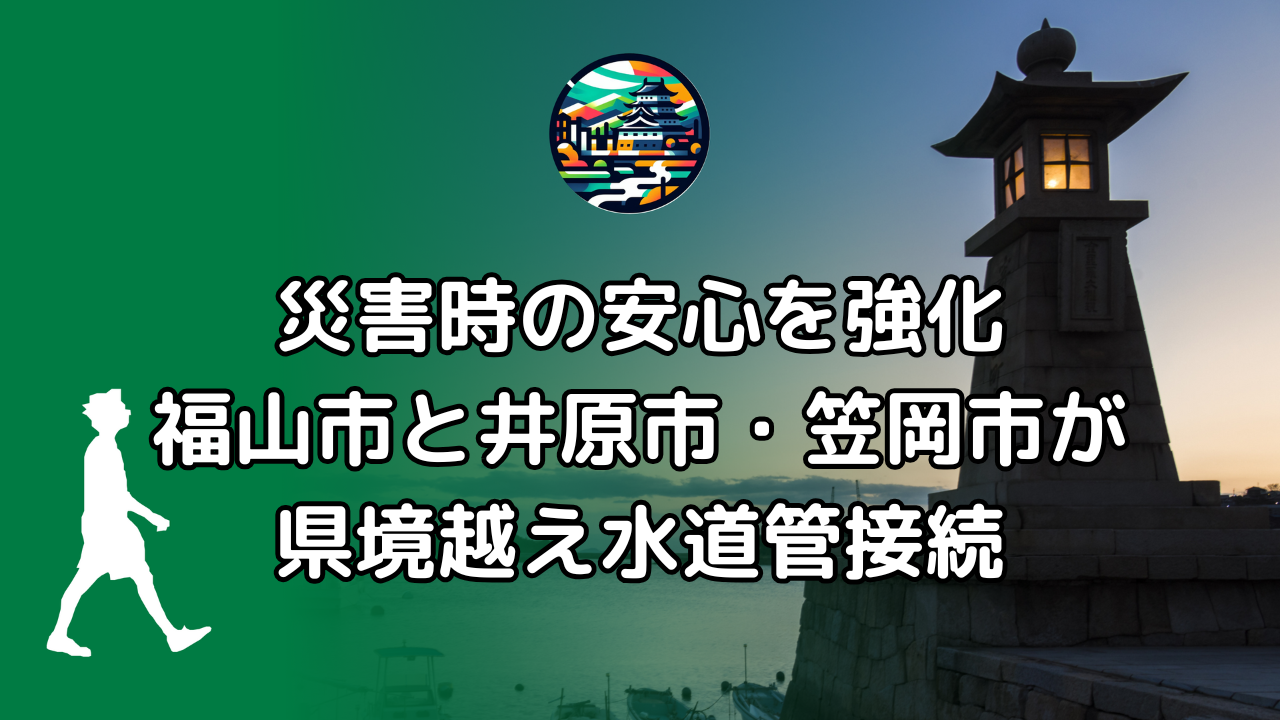
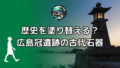
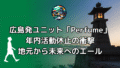
コメント