地域に愛される比婆山駅の歴史と祭りの詳細
広島県庄原市西城町にあるJR芸備線・比婆山駅は、1935年の開業から90周年を迎え、2025年9月20日に地元団体などによる記念イベント「比婆山駅まつり」が開催されました。比婆山駅は元々、伊邪那美命の陵墓とされる比婆山御陵への玄関口として、1935年12月20日に「備後熊野駅」として開設された歴史を持ち、駅舎は朱色の社殿型屋根が特徴的です。
イベント当日は、臨時列車で多くの乗客が比婆山駅に到着し、地元住民が旗を振って出迎えました。会場では、庄原市制施行20周年も記念し、地元産のそば粉を使った「西城ヒバゴンそば」や新米、どぶろくなどが販売された産直市(マルシェ)、キッチンカーが出店しました。
また、ミニコンサート、大黒さまの福餅まき、ヒバゴンクイズ、90周年記念スタンプの押印、鉄道模型の展示など、鉄道と地域にちなんだ企画が午前9時26分から午後2時55分まで繰り広げられました。
地域を支える活動と記念イベントの継続
比婆山駅は1972年から無人駅となっていますが、地域住民が毎月ボランティアで清掃活動を続けています。9月14日には、イベントに先立ち、比婆山自治会など地域の人々およそ20人が、駅舎や周辺の念入りな清掃を実施しました。
自治会の代表者からは、駅がきれいになり安心して来客を迎えられることへの喜びと、今後の100年に向けて努力したいという決意が示されました。比婆山駅の90周年イベントに続き、10月5日には備後落合駅でも開業90周年記念イベントが開催される予定です。
芸備線の利用促進と存続を巡る議論
芸備線は地域住民の生活交通基盤であると同時に、観光を通じた地方創生にも重要な役割を果たしています。路線の存続に向け、広島県は沿線自治体や交通事業者と連携し、臨時便の運行や沿線周遊の企画を推進しています。
現在、芸備線では観光需要を調査する実証事業として、7月19日から11月24日までの土日祝日に臨時列車(増便)が運行されています。JR西日本広島支社の飯田支社長は、実証事業開始から2か月間の利用状況について、増便により乗車機会が増え、利用者が若干増加傾向にあると報告しました(備後庄原〜備後落合間で1日平均約30人、備後落合〜新見間で約25人)。
しかし、JR西日本側は、増便期間の延長は運転士確保の難しさから今の形では難しいとの認識を示しました。その上で、土日祝日の始発・最終列車(利用者は少数)をバスに置き換え、その運転士を日中の増便に充てることで延長が可能になるという案を再構築協議会の幹事会で議論したいと提案しました。
これに対し、地元自治体は強く反発しています。庄原市地域交通課の担当者は、実証事業は路線の可能性を探るものであり、通常の列車を減便することは目的と合わないのではないかと疑問を呈しました。新見市交通対策課の担当者も、増便が前提の実証事業において通常列車を減便することは想定外であり、運転士不足はJR側の問題で住民に影響が出るのはおかしい、という見解を述べました。
私の見解
比婆山駅90周年記念まつりは、単なる駅の節目を祝うイベントではなく、地域の誇りと結束を再確認する場だったと考えます。
1935年に比婆山御陵への玄関口として誕生した駅は、鉄道の利用減少や無人化の波を受けながらも、住民の手で清掃や維持活動が続けられてきました。この「支える文化」があるからこそ、90周年を多くの人と共に祝えたのでしょう。
一方で、芸備線の存続問題は依然として重くのしかかっています。JR側が提示する「減便とバス代替」は、効率面では理解できるものの、沿線の人々にとって鉄道は「単なる移動手段」ではなく「地域の象徴」です。今回のまつりは、その象徴を守りたいという強い意思表示でもあると感じます。
しかしJR西日本は、1987年の民営化以降、利益を出すことを最も大切な役割とする企業となりました。企業が生み出す利益は、税金や投資を通じて、社会全体の福祉や年金の財源など、多くの人々の生活の役に立っています。
そのため、利益が見込めない路線を運営し続けることは、企業全体の力を弱め、結果として国全体の利益を減らすことにつながってしまいます。もし芸備線が、地域にとって本当に必要不可欠なインフラであると判断されるならば、それは「市場の失敗」に対応すべき行政の役割です。
現代は、戦前や昭和30年代のように道路が未整備で車がなかった時代とは異なり、鉄道が移動手段として必ずしも必要とされない状況があります。JRに対し、資金負担を伴わずに運営継続を要求したり批判したりするのではなく、行政が率先して赤字分を負担し、路線維持に責任を持つ姿勢が大切と考えます。
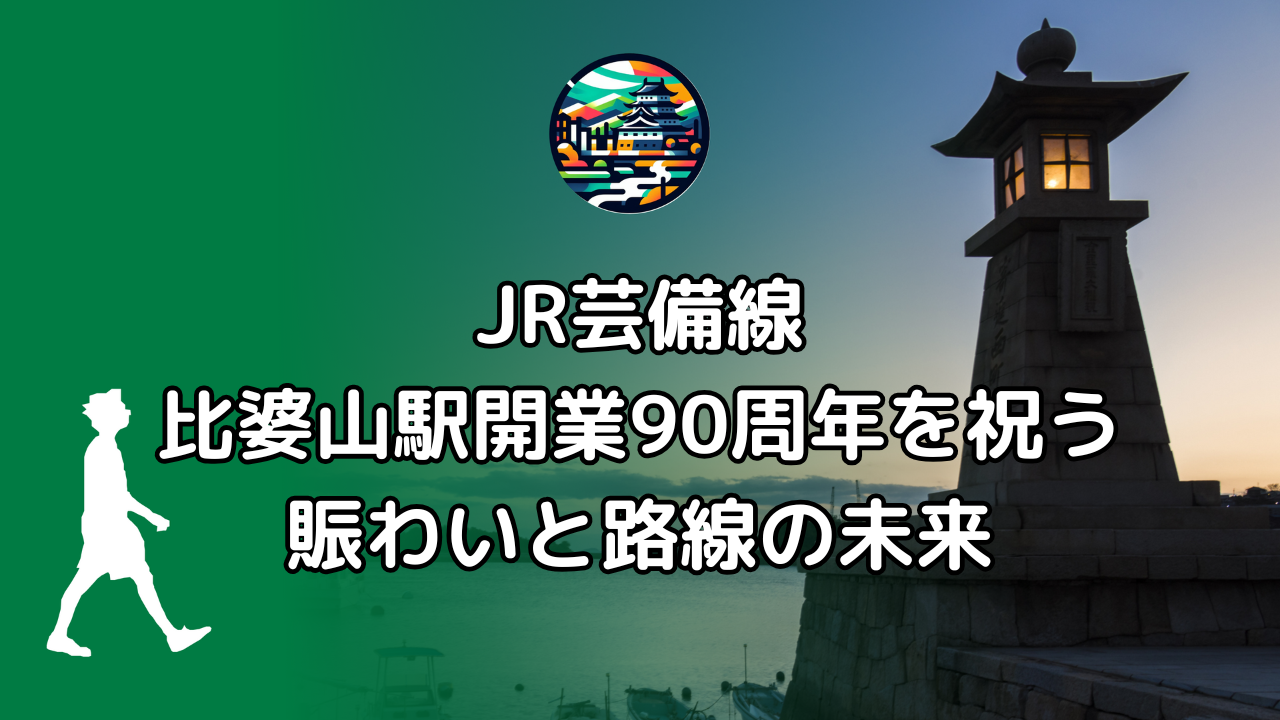
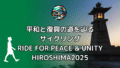
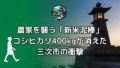
コメント