江戸時代、困窮を救うために誕生した義倉
庄屋たちの熱意が生んだ画期的な民間救済システム
一般財団法人「義倉」は、文化元年(1804年)に創立され、2025年に創立220周年を迎えました。この組織のルーツは、江戸時代の福山藩で困窮者の支援を目的として設立された民間組織にあります。
その始まりは、深津村の庄屋であった石井武右衛門盈比が、死に際して銀60貫目を千田村の庄屋・河相周兵衛に託したことに遡ります。河相周兵衛は、度重なる飢饉や農民一揆という社会情勢の中で、この窮状を救う方法を8年間熟考しました。彼は、戸手村の庄屋である信岡平六、福山の豪商・神野利右衛門、府中の義人・大戸久三郎などの同志を糾合し、銀300貫を拠出しました。
彼らは、財政難にあった福山藩が石州銀山から借りていた銀約300貫の借財を肩代わりする代わりに、利息相当分として銀45貫目を15年間に限り藩から下賜される約束を取り付けました。この資金を元手に農村の疲弊を救済するという骨子(救法目論見)を作成し、藩の認可を得て、一大救済組織として活動を開始しました。
地域リーダーの功績と安定的な資産運用
義倉の初期の資産運用では、貸付銀の利子収入が経営の中心でした。貸付先の債権回収や小作地の管理といった実務は村役人(庄屋)の仕事であり、藩がその履行を厳しく強制していました。庄屋役は義倉の小作地管理と同義であり、庄屋役を辞退したいという申し出があった際、藩は庄屋退役を命じることも辞さない姿勢で応じた記録があります。庄屋は連帯保証人としての役割も担い、義倉の債権回収は福山藩の存在によって担保されていました。
義倉の創設者の一人、信岡平六は戸手村の庄屋役を代々務めた家柄であり、義倉の設置だけでなく戸手用水の開削にも功績がありました。戸手村では、平六の命日を「平六休み」と称して顕彰碑に詣でる風習があったといいます。彼の頌徳碑(「石塔さん」)は1839年(天保10年)の七回忌に建立され、今も地元の人々に尊崇されています。信岡家の住宅は江戸後期から昭和にかけて建てられた8棟の建造物が良好に保存されており、2008年(平成20年)3月には国の登録文化財の指定を受けました。
義倉の経営は、同時期に多くの豪農が経営難に陥る中で、安定的に展開しました。これは、貸付銀と土地のバランスを取るという運営方針や、藩による村請機能の活用と債務履行の強制といった支援の結果であると考えられます。
儒学思想に基づく文化・教育活動
義倉は、飢饉時の米や金銭の放出による困窮者救済に加え、文化教育活動も展開した点で、他の義倉・社倉にはない大きな特徴を持っていました。これには、著名図書の購入、医師育成のための助成、上方からの著名人を招いての儒学・神道・仏学の講釈の実施などが含まれます。
この義倉の理念は、朱子学者の菅茶山が神辺宿に開いた廉塾の影響を受けている可能性が指摘されており、当時の文化的背景と義倉の利他の精神との関係性が講演で説かれています。義倉の発起人であった河相周兵衛は、中井竹山の経世論にある「社倉私議」を参考にしています。この創設は、菅茶山の門下生らを含む、地域を超え、身分を越えた文化的ネットワークの絆に支えられていたといえます。
近代化と大戦を経て、財団法人への移行
近代化の波を乗り越え、多角化する事業
明治政府樹立後、全国の義倉や社倉の多くは解散・廃止されましたが、「福府義倉」は飢饉救済以外の文化教育活動を軸に事業を継続した、全国的にも極めて珍しい存在です(秋田感恩講とともに挙げられます)。
明治以降の活動内容は多岐にわたりました。黎明期の福山において、全国規模の地震や津波の災害見舞金贈呈、流行病防疫費の寄付、道路・橋梁の建設資金負担など、社会資本整備を展開しました。また、各村の尋常小学校の設立資金贈呈を皮切りに、中学校、女学校、実業学校への寄付、用地提供、経費補助など、教育施設の充実に大きく貢献しました。
さらに、農業技術発展のための農業講習会や品評会施設の補助、農業会技術員の養成、地方養蚕業の奨励に対する経費補助など、農業振興にも力を注ぎました。日清・日露戦争以降は、陸軍病院建設費の献金、出征軍人の留守家族や遺族への援助なども行いました。
近代経営者としての担い手たちと財団設立
義倉は、民法が施行された1899年(明治32年)に、備後福山認可第一号として、いち早く財団法人に改組しました。この時期の義倉運営には、地域の有力な実業家たちが理事として関わりました。
例えば、石井英太郎は、1900年から1910年まで専務理事を務め、義倉の最大出資者として利益分配の30%を取得していました。彼は郡農会長として農事改良を主導し、義倉に補助金の支出を促すなど、地域貢献が認められていました。
また、神野利右衛門は1900年から理事や常務理事を務めました。彼は福山銀行、松永銀行などの役員も兼任し、地域貢献が評価された人物ですが、義倉からの利益分配への依存率が非常に高い時期もありました。
河相三郎も1907年から理事や専務理事を務め、福山銀行の専務取締役、福山町会議員、衆議院議員などを歴任した、地域の名望家でした。彼もまた地域貢献の有無に基づいて評価された一人です。
財団の事業活動は多岐にわたり、1910年(明治43年)には「義倉図書館」を設立し、地方図書館としては当時威容を誇りました。大正期から昭和初期にかけても、生活困窮者への資金援助、片山病撲滅のための資金協力、山本瀧之助の青年教育支援、庶民金融のための公益質店開設(1921年・大正10年)、青年練成道場開設(1943年・昭和18年)など、地道な活動を続けました。
戦後の困難を乗り越え、現代の助成活動へ
農地改革と教育事業への転換
1945年(昭和20年)の福山空襲により、図書館を含む義倉の諸施設はすべて焼失しました。さらに1947年(昭和22年)の農地改革により、義倉の中心的な財産であった百数十町歩の農地を失い、今後の方向性の転換を迫られました。
1952年(昭和27年)、義倉は戦後の荒廃の中で婦女子教育を最重要課題と位置づけ、「義倉女学園」を設立しました。その後「義倉女子専門学校」と改称されましたが、1991年(平成3年)3月にその使命を終えるまで、約5,000名の卒業生を世に送り出しました。
福祉、教育、殖産を柱とする助成団体へ
1991年(平成3年)の学校終焉を機に、義倉は明治32年制定以来の寄附行為を改正し、時代に適応した活動に転換しました。小規模ながらも、財団法人本来の寄付・助成活動に専念することを決意し、「福祉」「教育」「殖産」の三分野を活動の基本とし、福山市を中心に周辺町村のボランティア活動、教育文化の向上、地場産業の推進・振興のための資金拠出を続けています。
2012年(平成24年)4月1日には公益法人制度の改正に伴い、一般財団法人「義倉」として再スタートしました。代表理事の藤原平氏の挨拶の要点は、創設者の趣意を基に、福祉、教育、殖産をはじめとする社会活動の多くの分野で活動する方々(団体・個人)への助成を今後も続けていくというものでした。
創立220周年記念式典:歴史の継承と未来への貢献
記念式典の開催と文化功労賞の贈呈
義倉は、創立220周年を記念し、2025年10月2日に福山市内のホテルで式典を開催しました。この式典には、設立メンバーの子孫ら「義倉七家」をはじめ、多くの関係者が集まり賑わいました。
式典では、地域文化発展への貢献を称えるため、歴史小説家の藤井登美子氏と喜多流大島能楽堂の能楽師・大島衣恵氏に文化功労賞が贈られました。祝賀会では大島衣恵氏による仕舞が披露されています。
助成金交付と歴史的意義の再確認
2025年度は、地元の93団体に対し、総額1,370万円の助成金が贈呈されました。これは義倉が現在、福祉や教育団体への助成活動を続けていることを示しています。
福山大学の青木美保名誉教授による講演では、義倉の江戸時代の成り立ちが解説され、菅茶山の廉塾からの影響や、当時の文化的背景と義倉の「利他の精神」との関連性が説かれました。
藤原代表理事は、挨拶の中で、義倉が江戸、明治、大正、昭和、平成、令和の様々な社会情勢や障壁を力強く乗り越えてこられたのは、福山地域の皆様のおかげであると感謝の意を述べました。
義倉関係者は、200余年の昔、世直しに情熱を注いだ創設者の趣意をふまえ、今後も福山市民の役に立つにはどうすればよいかを考え続けていきたいと述べています。
私の見解
義倉の成立は、庄屋たちの実務力と利他の精神が結実した好例です。民間の柔軟な資金運用と藩の協力が、救済と持続性を支えたと考えます。
明治以降の財団化や教育・福祉への転換は、時代に応じた柔軟な再編の成功事例です。地域ニーズに応え続ける姿勢が今も評価に値します。
220周年は継承と刷新の好機です。若い世代の参画、記録のデジタル化、地域団体との協働を進めれば、義倉の「利他」は次代へ確実に受け継がれます。
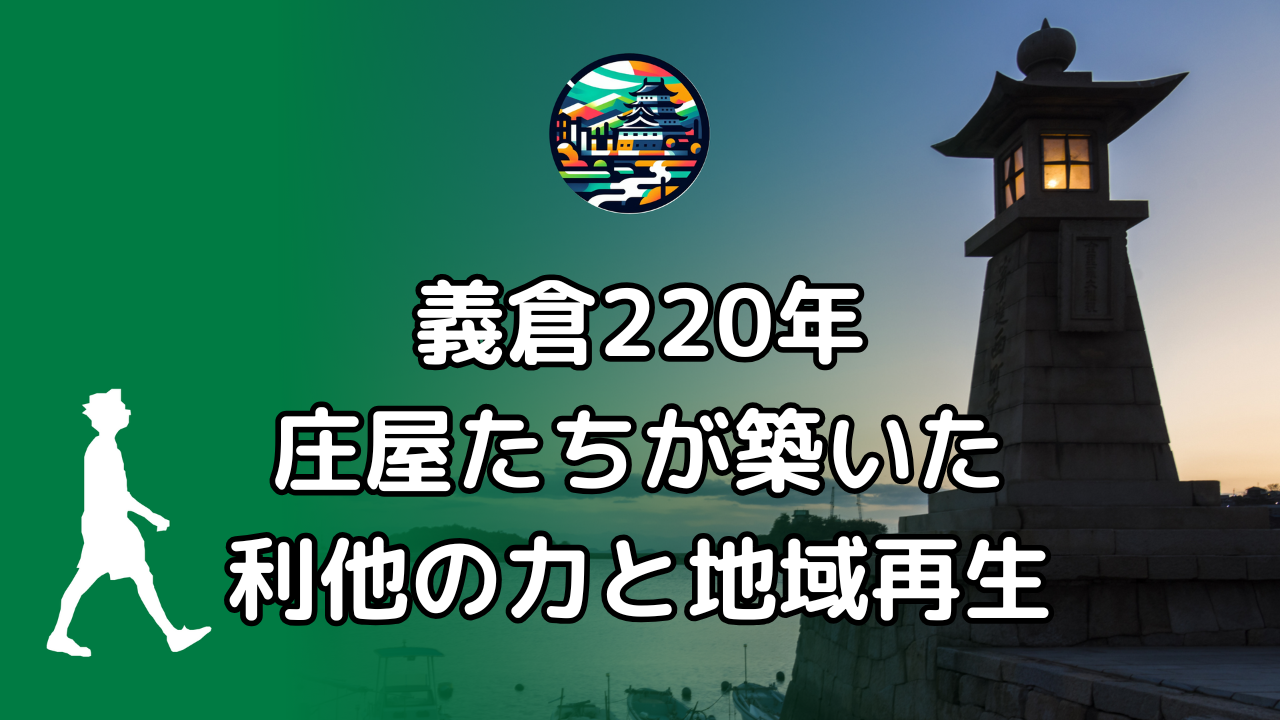
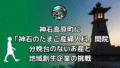
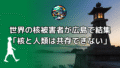
コメント