商業地・住宅地ともに上昇、京橋町が特に注目
2025年9月16日に公表された広島県内の地価調査によると、土地の取引価格は全体的に上昇傾向にあります。特にJR広島駅周辺の再開発が地価を大きく押し上げている状況です。県全体では住宅地の平均価格が0.4%上昇し2年連続、商業地の平均価格は1.8%上昇し4年連続で値上がりしています。
最も上昇率が高かったのは広島市南区京橋町1の3の地点で、JR広島駅の再開発や広島電鉄の駅前大橋ルート開通に伴い、18.9%もの上昇を記録し、1平方メートルあたり195万円となりました。これはバブル景気直後の1991年以来34年ぶりの高い伸び率です。この上昇の背景には、駅ビル開業など中心部の再開発が進み、オフィスやホテルの需要が高まっていること、そして今後の利便性向上への期待感が影響しているとされています。
最高価格地点と広がるオフィス需要
商業地の最高価格地点は広島市中区本通の金正堂ビルで、1平方メートルあたり346万円を記録し、40年連続の1位を維持しています。住宅地の最高価格は広島市中区白島中町8の8で18年連続1位、その上昇率は8.1%と住宅地で最も高い伸びを示しました。
広島市中心部ではオフィス需要も高まっており、不動産サービス大手のCBREの調査では、広島駅周辺のオフィスビル空室率は今年6月時点で0.7%と、ほぼ空きがない状態が続いています。賃料も上昇傾向にあり、広島駅周辺が市外からの通勤にも便利で人材確保の面でも優位性があると企業から評価されている点が背景にあると見られています。
地域間の二極化と未来への展望
一方、県内を地域別に見ると、広島市や福山市、府中町、廿日市市などでは地価が上昇しているのに対し、人口減少が進む島しょ部や中山間地を含む呉市、尾道市、三原市などでは下落傾向が続いており、地価の二極化が進んでいる現状が明らかになりました。
不動産鑑定士は、商業地においては、広島駅前の再開発によるハード面の整備が進んだ今、人々がどれだけ集まるかが今後の課題であり、若者が訪れたくなるような施設開発がさらなる地価上昇の要因となると指摘しています。住宅地についても、広島市中心部の需要は引き続き高く上昇傾向が続く一方で、郊外の古い住宅団地や島しょ部では下落傾向が続くと予測されています。
私の見解
- 駅前再開発の波及効果
- 広島駅周辺の地価上昇は、単なる不動産価格の上振れに留まらず、オフィス需要・ホテル需要・交通利便性の三拍子がそろった好循環を生み出しています。特に京橋町の18.9%という異常値的な上昇率は、再開発の直接的なインパクトを象徴しています。
- 商業地と住宅地の温度差
- 本通や白島といった「伝統的な一等地」が安定して最高価格を維持する一方、周辺エリアは再開発や新交通網の恩恵を受けて急伸。住宅地では中心部が堅調ながら、郊外や島しょ部はマイナスが続いており、「利便性と人口動態」の影響が直結していることが浮き彫りになりました。
- 二極化の加速と課題
- 広島・福山・府中町・廿日市といった都市圏はプラス成長、呉・尾道・三原といった中小都市は下落継続。この二極化は今後さらに拡大すると予想され、行政の都市計画・交通網整備・移住政策などの戦略性が問われます。
- 今後の展望
- 再開発の「ハード」は整ってきたので、今後は「ソフト」、すなわち若者や観光客を惹きつける文化的・商業的コンテンツが重要。駅前に人の流れを生み出し続ける仕掛けがなければ、地価上昇も一過性で終わるリスクがあります。
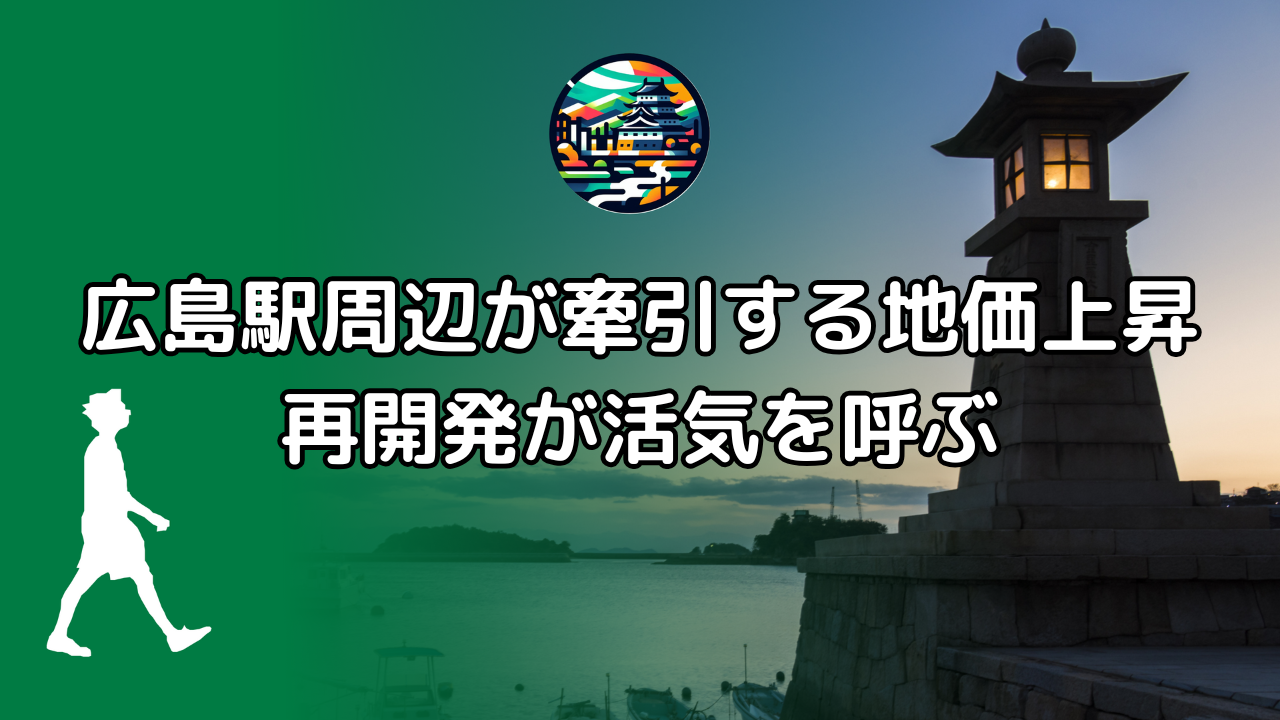
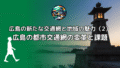
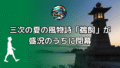
コメント