脱炭素ロードマップの更新と燃料転換
マツダは、世界の製造施設におけるカーボンニュートラル(CN)を2035年までに達成するという目標に向けて、ロードマップと2030年度の中間目標を更新しました。
この更新されたロードマップは、CO2排出量の約75%を占める国内の工場およびオフィスに適用されます。新たな計画では、将来の代替燃料調達や技術進展を柔軟に見据えつつ、事業に必要なエネルギーを安定的に確保し、CO2削減を促進します。
当初、マツダは広島工場宇品地区の発電燃料を石炭から単一燃料アンモニアに切り替えることを計画していましたが、これを変更しました。代替案として、確立された発電技術であるガスコジェネレーションシステムを導入し、LNG(液化天然ガス)を原料とする都市ガスを燃料に用いて脱炭素化を進めます。
新システムのメリットと中間目標の変更
この新しいガスコジェネレーションシステムは、将来的にカーボンニュートラル燃料と期待される水素へも、軽微な設備変更で段階的に移行できる設計となっています。
マツダは、川崎重工業と共同で、このシステムの仕様を検討し、極めて高いエネルギー利用効率と工場運営に合わせた最適なエネルギー管理を目指します。このシステムは、発電時に発生する熱を工場で有効活用することで、エネルギー効率を現在の2倍にあたる80%まで向上させられる見込みです。
また、ロードマップの更新に伴い、2030年度のCO2排出量削減中間目標は、2013年度比で「46%以上」の削減(日本の目標と同等)へと修正されました(以前は69%削減)。
マツダは、省エネ、再生可能エネルギーの採用、CN燃料の利用という三つの柱で、2050年までにサプライチェーン全体でのCN達成を目指します。脱炭素化計画の推進にあたっては、広島ガスや中国電力といった地元のエネルギー事業者からの協力を得て、地域一体で取り組む方針です。
この計画の一環として、広島工場と防府工場にある石炭火力発電所は2030年頃を目処に廃止される予定です。
8月の生産実績とトランプ関税の影響
マツダの2025年8月の国内生産台数は4万8903台で、前年同月比4.3%増となり、7カ月ぶりに増加に転じました。工場別に見ると、宇品工場ではCX-5の生産が大きく伸びたことで、全体生産台数も増加しました。
一方、山口県の防府工場では、アメリカ向けの大型SUV(CX-70やCX-90)の生産が減少し、生産台数は20.4%減となりました。マツダは、アメリカ向けの輸出減少(32%減)の理由として、トランプ政権の関税措置による不透明な経済状況と、現地での在庫が十分であることを挙げています。
世界販売台数も8.3%減少しましたが、アメリカ国内ではCX-50などのSUVの販売は好調でした。
私の見解
マツダの脱炭素ロードマップ更新は、現実的な燃料転換を重視した方針転換といえます。石炭から直接アンモニアではなく、段階的に水素利用へ移行可能なガスコジェネを導入する判断は、柔軟性と安定性を兼ね備えています。
また、中間目標を「46%以上削減」に修正した点は、挑戦的な数値から現実的な数値へ再調整した印象を受けます。地元企業と連携して持続可能な道を模索する姿勢は、地域経済と環境政策の両立に寄与するでしょう。
一方で、アメリカ市場の不透明さや関税リスクは依然として課題です。国内での脱炭素化を進めながらも、世界的な販売戦略に柔軟性を持たせることが、今後の競争力維持の鍵になると考えます。

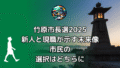
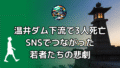
コメント