オーストラリア原産の特定外来生物、その特徴と危険性
セアカゴケグモは、オーストラリア原産の特定外来生物であり、メスは毒を持っています。オスはメスの半分以下の大きさで毒はなく、人体に被害を与えることはありません。メスの体長は約1cm(足を含まない)で、全体が黒色、腹部は球状に丸く、腹部背面に赤色の帯状の模様、腹部腹面には赤色の砂時計のような模様が特徴です。繁殖時期は真夏で、乳白色の卵のう(直径1~1.5cm)を産みます。
セアカゴケグモに咬まれると、初めは針で刺したような痛みを感じ、患部が腫れて赤くなる局所症状(疼痛、熱感、痒感、紅斑、硬結)が現れます。通常は数時間から数日で症状は軽減しますが、稀に脱力、頭痛、筋肉痛、不眠といった全身症状が数週間続くことがあります。重症例では、多量の発汗、寒気、吐き気、呼吸困難といった症状や、進行性の筋肉麻痺を生じる場合もあります。
日常生活における注意点と駆除方法
セアカゴケグモは攻撃性がなく、素手で触らない限り咬まれることはありません。しかし、日当たりが良く暖かい場所の地面近くの隙間や窪みに巣を張るため、日常の様々な場所に生息する可能性があります。具体的には、プランターや植木鉢の底、側溝の下やグレーチングの裏、エアコンの室外機や自動販売機の裏、排水溝の側面や蓋の裏、墓石の隙間、屋外に放置された傘や靴の中などが挙げられます。これらの場所を清掃する際や、不用意に隙間に手を入れないように注意が必要です。
駆除は、市販の家庭用殺虫剤(ピレスロイド系)を直接噴霧するか、熱湯をかける、靴で踏みつぶすといった方法が有効です。殺虫剤を噴霧する際は火バサミなどで押さえつけると良いでしょう。周囲に卵がある可能性もあるため、卵のうもビニール袋に入れて踏みつぶし、口を縛ってゴミとして捨てるようにします。万一咬まれた場合は、毒を温水や石けん水で洗い流し、保冷剤で患部を冷やして速やかに医療機関を受診してください。その際、駆除したクモを持参すると、種類が特定され適切な治療につながります。
広島県内各地で確認が相次ぐセアカゴケグモ
国内では平成7年に大阪府で初めて確認されて以来、青森県と秋田県を除く全国45都道府県で確認されており、大阪府、三重県、兵庫県、和歌山県、奈良県では定着が確認されています。
広島県では平成24年9月に大竹市で初めて確認されました。県内における報告数が増加している要因の一つとして、県民の危険意識や発見した際にセアカゴケグモかもしれないと疑うことができるようになっている点が挙げられています。
広島市内では、2025年9月5日時点で40事例が確認されています。2025年9月4日午後1時30分頃、広島市西区の観音小学校で、児童が校舎間の渡り廊下の柱にセアカゴケグモとみられるクモ1匹を発見しました。教員が捕獲し、児童に被害はなかったものの、保健所の職員が駆除し周辺に殺虫剤を散布しました。
福山市内では、2014年(平成26年)9月10日に山陽自動車道福山サービスエリア内で初めて確認されて以来、複数の場所でセアカゴケグモの目撃情報が寄せられています。2025年9月3日、福山市西新涯町2丁目で確認されました。
私の見解
セアカゴケグモは「攻撃性は低いが潜在的リスクが非常に高い外来種」と評価すべき存在だと思います。
特に注意すべき点は次の3つです。
- 毒性と医療リスク
- 本来は人を襲わないにも関わらず、不用意に触れた際には強力な神経毒によって全身症状を引き起こす可能性があります。
- 日本では抗毒素血清が限られており、迅速に対応できる医療体制の整備が課題です。
- 生活環境への侵入性
- 自動販売機の裏、プランターや排水溝など、人の日常生活に密着した場所に潜むため、一般市民が遭遇するリスクが高い。
- 特に学校や公園など、子どもが集まる場所での確認例は、行政の警戒を強める必要性を示しています。
- 定着の広がり
- 広島県でも確認件数が増加しており、既に「希少な外来種」ではなく「地域社会で現実的に注意すべき危険生物」になりつつある。
- 一度定着すると駆除が困難なため、発見時の通報と個体・卵の徹底処理が重要です。
総合すると、「過度に恐れる必要はないが、リスクを正しく理解し、日常生活の中で“予防的習慣”を持つこと」が最も重要だと考えます。
つまり、清掃や屋外活動時の注意喚起を徹底することで被害は大幅に減らせる一方、油断は禁物という立ち位置です。
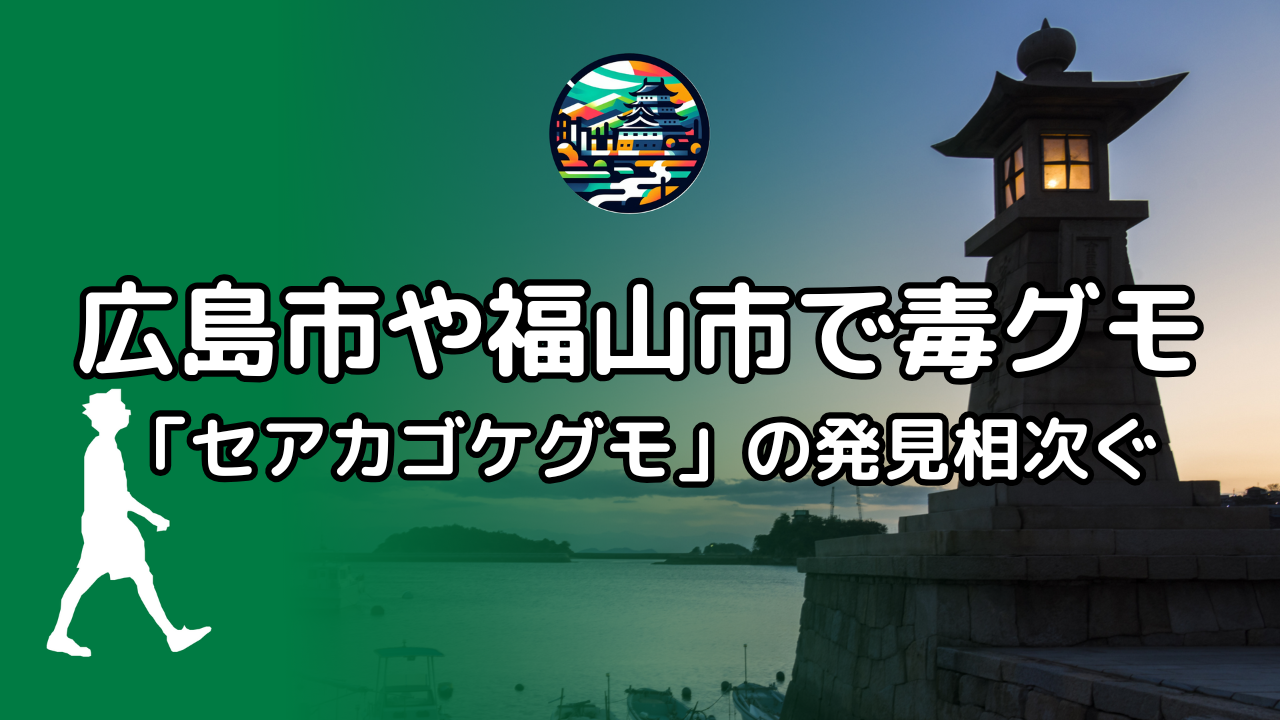

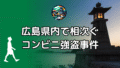
コメント