相次ぐ給食異物混入の実態
東広島市にある県立広島中学校で、給食への異物混入が頻繁に発生しており、その深刻さが浮き彫りになっています。2022年度以降、確認された異物混入は合計で57件に上り、特に2025年度に入ってからも4月から9月10日までの間に29件という多数の事例が報告されています。
給食に混入した異物は多岐にわたり、髪の毛やハエ、クモなどの虫のほか、ペーパータオル、ビニール袋の切れ端、さらには段ボール片のようなものまで見つかっています。中には、生徒がビニール片を誤って口に入れて吐き出すという事態も発生しましたが、幸いなことにこれまでのところ健康被害は確認されていません。
この給食は広島市内の委託業者が提供しており、同業者は少なくとも2013年度から継続して給食を提供し、今年度も入札で落札していました。しかし、県教育委員会がこれまで衛生管理の確認や指導を行ってきたにもかかわらず、問題の根本的な改善には至っていません。
なお、県立三次中、県立三原特別支援学校、県立呉南特別支援学校でも、給食にビニール片が混入するなどの事案が各1件報告されています。
県教育委員会の対応と今後の課題
広島県教育委員会の篠田智志教育長は、学校給食の安全・安心が最優先の原則であるとし、この異物混入の状況を重く受け止めていると表明しました。
これまでは健康被害が確認されなかったという理由で事案を公表していなかったものの、その対応が十分ではなかったことを認め、今後は異物混入事案の公表基準を新たに検討する方針を示しました。
県教育委員会は、再発防止のために調理機器の点検強化や従業員の身だしなみ徹底といった対策を進めるほか、異物混入発生時の安全確認や公表に関するマニュアルを作成し、県立学校全体でこれを徹底するよう呼びかける予定です。
県立広島中学校の澄川利之校長も、異物混入は許されないことであると述べ、生徒や保護者に心配をかけていることを謝罪。委託業者への注意喚起と、学校としてできる限りの対策強化を約束しました。
私の見解
今回の給食異物混入問題は、単発的な「事故」ではなく、組織的な衛生管理体制の不備が浮き彫りになっている事例だと考えられます。
- 件数の多さが示す構造的問題
2022年度以降で57件、今年度だけで29件という数字は、偶発的ではなく「管理工程のどこかに恒常的な問題がある」ことを示しています。 - リスクマネジメントの甘さ
健康被害が確認されなかったから公表しない、という姿勢はリスクコミュニケーションの観点から不適切です。透明性の欠如は、結果的に学校や行政への信頼を損なう可能性が高いです。 - 委託業者と行政の責任分担
業者だけに責任を押し付けるのではなく、発注者である県教育委員会にも「監督責任」「改善要求の仕組みづくり」の両面で課題があります。 - 再発防止の鍵
- 調理機器や調理場の構造的な点検(老朽化設備の影響を含む)
- 作業工程の可視化(記録・監査・外部チェック)
- 従業員教育の徹底(身だしなみ・器具管理)
- 公表とフィードバックの仕組み(隠さず、改善につなげる)
学校給食は子どもの日常に直結するものですから、たとえ直接的な健康被害がなくとも「安心の欠如」自体が大きな社会的損失になります。信頼を取り戻すためには、数字やマニュアル以上に、組織全体の「安全文化」の醸成が必要だと思います。
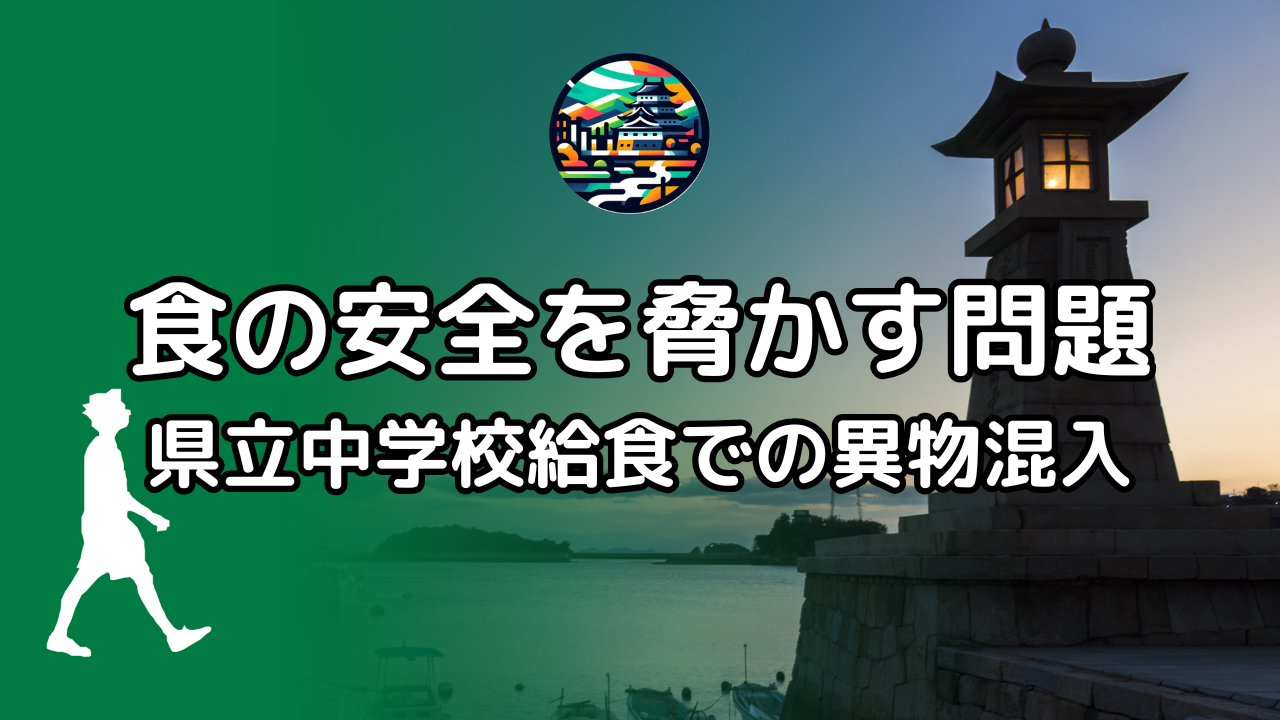
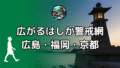
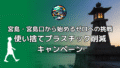
コメント