海上バス「ゆき姫」の試験運航と利用者の反応
大崎上島町では、本州との移動手段が限られる住民の生活支援や船員不足の解消のため、AI技術を搭載した「スマート海上バスゆき姫」の自律航行試験運航が進められています。このプロジェクトは2021年から開発が進められており、将来的な無人航行を目指しています。
2025年7月25日から、2回目の試験運航が竹原港と大崎上島町の港(福浦、白水など)を結ぶ航路で開始され、10月20日まで運航される予定です。運航は、フェリー便がない夜間や早朝に、予約がある場合のみ行われる柔軟な運用が試されています。
最初の試験運航(2025年1月まで)では、利用者の満足度が高く、8割以上が本格導入時に利用したいと回答しました。また、利用者は運賃として平均で約700円高く支払ってもよいと答えたことから、2回目の試験では中学生以上の運賃が1,500円に引き上げられました。
9月には、この船を利用したサンセットクルーズも実施され、参加者は瀬戸内海の景色を楽しみつつ、自動航行システムの説明に熱心に耳を傾けていました。
離島が求める「道路代わり」の航行と技術的な課題
大崎上島町の町長は、離島にとって船は道路の代わりであり、24時間備わっていることが当たり前になってほしいという強い願いを述べています。
しかし、自律航行システムの実用化には技術的・法的な課題があります。開発企業であるエイトノット社は、船の運航は潮の流れや風の影響を受けるため、陸上の自動運転とは異なる高度な技術が必要だと説明しています。同社は、船長や船員の確保が困難な瀬戸内海の課題を解決するため、様々な船に取り付け可能なシステム開発を目指しています。
将来的な「無人化」の実現については、国際法や国内法の整備がまだ途上にあり、ハードルは大きいものの、この法整備を待っていては立ち行かなくなる地域が数年のうちに出てくるだろうという見解が示されています。
私の見解
「ゆき姫」の試験運航は、離島の生活インフラを守るための挑戦であり、単なる技術実験ではなく「暮らしの足を未来へつなぐ取り組み」と捉えるべきだと思います。
利用者が「高くても使いたい」と答えている点は重要で、これは利便性や安心感が、単なる運賃の問題を超えて価値を持つことを示しています。言い換えれば、離島住民にとって船は「代替不可能な公共財」であり、その持続可能性に対して一定の負担を受け入れる意識があるということです。
一方で、技術面・法制度面の課題は依然大きく、自律航行が直ちに「無人化」を意味するものではありません。しばらくは有人監視を前提としたハイブリッド型運用が現実的でしょう。ただし、少子高齢化と船員不足が加速する中で、「法整備を待ってから導入」では遅すぎるという町長や企業側の危機感には強く同意します。
結局のところ、このプロジェクトは「地域の持続性を守る社会実験」であり、ゆき姫が成功すれば、全国の離島交通モデルにも波及する可能性があると考えます。
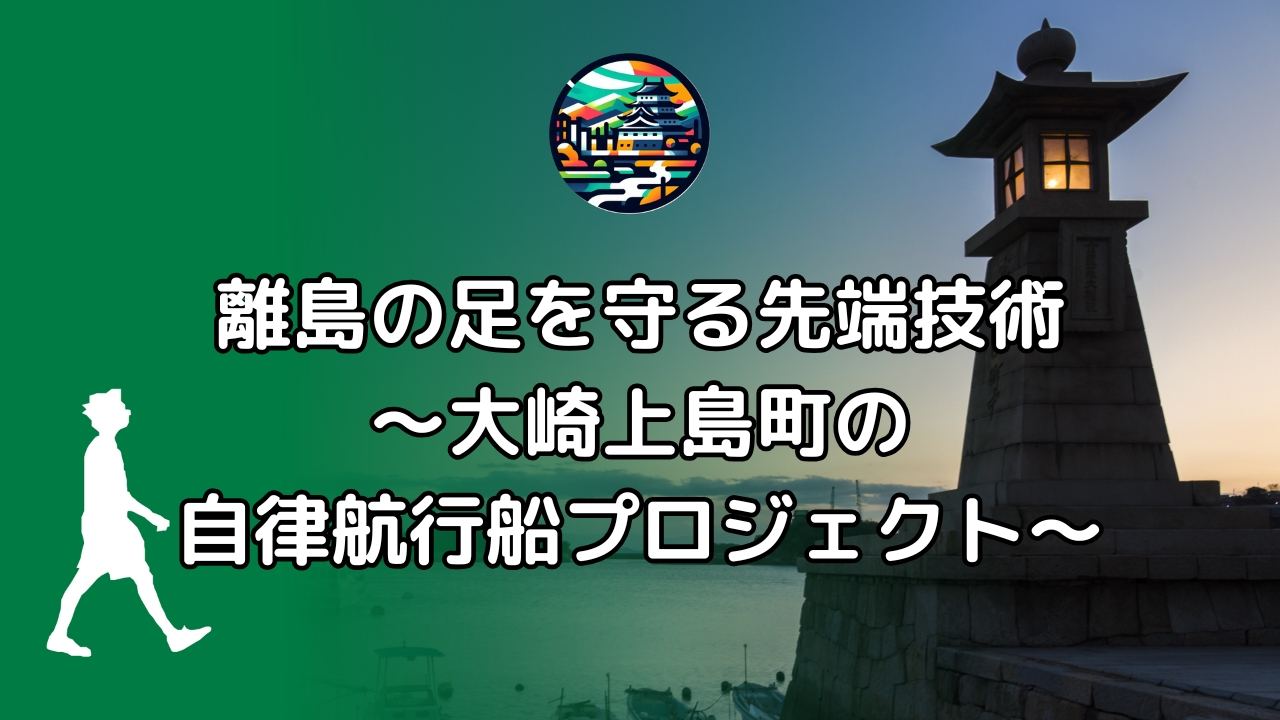
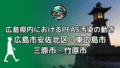
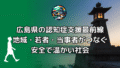
コメント