岩国基地で25年ぶりのFCLP訓練開始、地元に広がる懸念
硫黄島噴火による異例の措置と訓練の実態
アメリカ軍は、2025年9月17日から26日までの平日、山口県にある岩国基地で空母艦載機による陸上模擬着艦訓練(FCLP)を開始しました。
この訓練は、パイロットが空母への着艦資格を得るために不可欠なもので、滑走路を空母の甲板に見立て、着陸後すぐに離陸する「タッチアンドゴー」を繰り返すのが特徴です。通常は太平洋上の硫黄島で実施されますが、硫黄島の火山噴火活動が続いているため、訓練が困難となり、25年ぶりに岩国基地が代替地として選ばれました。
住民を悩ませる「轟音」と夜間訓練の実施
このFCLP訓練は激しい騒音を伴うことで知られており、岩国基地周辺では100デシベルを超える騒音がたびたび記録されました。特に基地に近い観測点では、最大で88.7デシベルの騒音が観測され、70デシベル以上の音が5秒以上続いた回数は1日で202回に及んだ日もありました。
訓練は昼間の午後1時半から午後4時半、そして夜間の午後6時45分から午後9時45分まで実施されており、夜間も戦闘機が「タッチアンドゴー」を繰り返す様子が確認されています。17日には、午後の訓練で108回のタッチアンドゴーが確認され、80件の騒音に関する苦情が寄せられました。
地元自治体と住民からの強い反発、過去の約束との食い違い
相次ぐ中止要請と「断じて容認できない」声
広島県は、地元住民の安全が脅かされることや騒音被害、事故の危険性増大を懸念し、訓練の中止をアメリカ大使館などに文書で要請しました。岩国市の福田市長も、訓練の実施は「到底容認できない」と中谷防衛大臣に申し入れ、中止を強く求めています。
大臣からは「訓練はやむを得ない」との回答がありましたが、市は今後の動向を注視する構えです。基地に隣接する広島県大竹市や廿日市市からも、「地元住民に多大な影響を与えるため、断じて容認できない」として、訓練実施の中止を求める声が上がっています。
住民生活への影響と将来への不安
大竹市の住民からは、騒音への不満や不安の声が聞かれました。また、基地に近い阿多田島の住民は、訓練があるとテレビや電話の音が聞こえなくなり、漁師など朝早くから活動する人々の生活に支障が出ると訴え、訓練はやめてほしいと強く要望しています。
市民団体は、2017年に岩国市が艦載機移転計画を受け入れた際の条件として「FCLPは実施しないこと」があったにもかかわらず、今回の実施は条件を破る行為であると指摘し、将来的にFCLPが定期的に岩国で行われることを危惧しています。
継続的な騒音は市民生活に大きなダメージを与えると強調し、二度とこのような事態は避けたいと考えています。専門家は、東アジア全体の安全保障状況が訓練の背景にあるとしつつも、地域住民の安全と安心とのバランスが重要であり、訓練の弊害を最小限に抑えるべきだと述べています。
新型ミサイルシステム「タイフォン」岩国基地に初展開、その戦略的意味
日本初上陸「タイフォン」の能力と岩国基地の重要性
日米共同訓練「レゾリュート・ドラゴン」の一環として、アメリカ陸軍の新型ミサイルシステム「タイフォン」が9月11日から岩国基地に展開し、日本国内で初めて公開されました。
このシステムは車両に搭載され移動可能で、巡航ミサイル「トマホーク」や迎撃ミサイル「SM6」などを搭載し、陸上や海上の目標を攻撃できます。
アメリカ陸軍は、岩国基地が航空基地と港湾施設の両方を備えているため、航空機や艦船への搭載訓練を一度に行える点が、タイフォンの訓練場所として優れていると説明しています。
東アジアの安全保障を意識した展開と中国の反発
軍事問題の専門家は、タイフォンの岩国展開には、海洋進出を強める中国やミサイル開発を進める北朝鮮をけん制する戦略的な狙いがあると分析しています。特にトマホークミサイルの射程は約1600kmに及び、東シナ海のほぼ全域や北朝鮮も射程圏内に収まる能力があります。
アメリカ陸軍の関係者は、タイフォンが海上・陸上の領域で効果を発揮し、複数の弾種を使用することで敵に多くのジレンマを与えると説明し、地域一帯の安全保障に貢献すると強調しています。
今回の訓練では実弾射撃は行われず、訓練終了後には撤収される予定ですが、中国外務省の報道官は、アメリカがタイフォンを日本に配備することに「断固反対」し、他国の正当な安全保障上の利益を損なうものだと表明しています。
アメリカ軍は将来的に日本で再び展開する可能性を否定しておらず、専門家は岩国に今後も「意外な装備」が展開する可能性を指摘しています。廿日市市と大竹市の市長は、新型ミサイルシステムの展開に関して、住民の安全確保のための情報提供などを求める考えを示しています。
私の見解
岩国基地は、航空・港湾機能を併せ持つ「多用途拠点」として日米の戦略上重要性を増しています。だがその一方で、「FCLPの定期化」や「新型兵器展開の常態化」への懸念は払拭されていません。
地域の声をどう政策に反映させるかが、今後の最大の課題になると考えます。
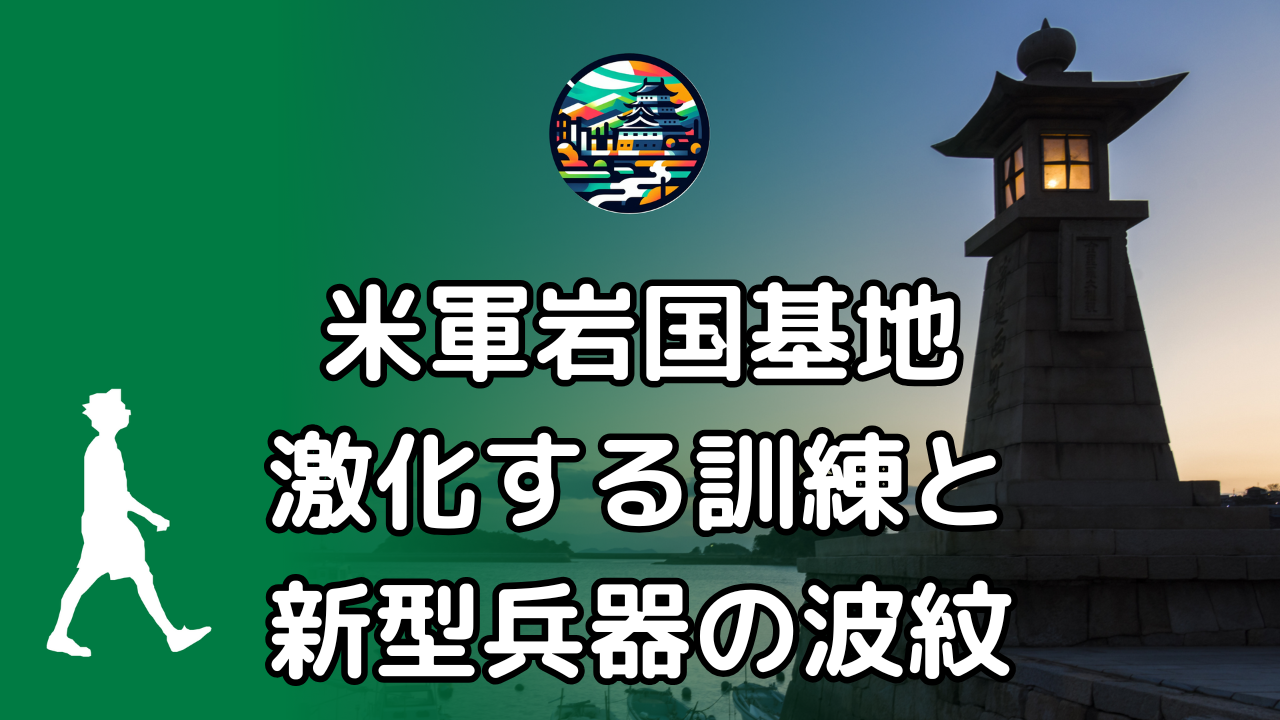
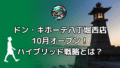
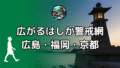
コメント