文化の殿堂の始まり
広島市中央公園の緑豊かな一角に佇む広島市映像文化ライブラリーは、40年以上にわたり、単なる映画上映施設以上の役割を果たしてきた。それは、市民が映画と出会い、文化を享受し、そして広島の歴史と記憶を次世代に伝える「映像と音の殿堂」であった。国際平和文化都市の理念を体現するこの施設は、広島の文化的アイデンティティの形成に不可欠な存在であり、その歩みは、日本の地方都市における公立フィルムアーカイブの先駆的な歴史そのものである。
平和文化都市の構想から誕生
広島市映像文化ライブラリーは、1982年5月1日、国内の地方自治体が設立した初のフィルム・アーカイブとして開館した。その誕生は、広島を「国際平和文化都市」として創造しようとする市民と行政の強い意志の結晶であった。
この構想は、1970年代後半、広島大学の中川剛教授が市の文化懇話会で建設を提案したことに端を発する。「広島には、原爆に関するあらゆるフィルム資料を収集・保存する義務がある」という彼の信念は、当時の沢田秀男助役や市民の映画愛好団体らの共感を呼び、大きなうねりとなった。
さらに、東広島市出身で当時東映社長であった岡田茂氏が全面的に支援を表明したことで、計画は大きく前進。これにより、市は商業映画フィルムの購入が可能となり、アーカイブとしての基盤が築かれた。
ライブラリーの設立目的は明確であった。広島ゆかりの映画作品や、原爆に関する貴重な映像資料を体系的に収集・保存し、広く市民に上映の機会を提供すること。それは、映像という力強いメディアを通じて、市の掲げる「平和文化」を未来へ継承していくという、重い使命を担うものであった。
映画文化の拠点としての活動実績
開館以来、ライブラリーは多彩な文化事業を展開し、市民の文化的な憩いの場として確固たる地位を築いてきた。
多彩な文化事業と市民の支持 定期的に開催される名作映画鑑賞会や文化映画鑑賞会は、民間の映画館とは一線を画すプログラムで多くのファンを魅了した。その活況は数字にも表れており、例えば平成29(2017)年度の事業報告書によれば、年間で以下の入場者数を記録している。
- 名作映画鑑賞会: 17,806人
- 文化映画鑑賞会: 1,386人
- 外国映画鑑賞会: 6,903人
このほかにも、無声映画に弁士が語りをつける活弁シアターや、貴重な音源を最高の音響で楽しむレコードコンサートなど、映像と音に関する幅広い事業が市民に親しまれてきた。
アーカイブとしての金字塔
ライブラリーの功績は、上映活動だけにとどまらない。1991年には、所在不明となっていた伊藤大輔監督の傑作「忠次旅日記」(1927年)のフィルムを発見し、専門家による修復に貢献。この「幻の名作」の再発見は、日本の映画史における大きな出来事であり、アーカイブとしての重要な役割を国内外に示した象徴的なエピソードとなった。
施設の老朽化
中央公園の緑に包まれた環境で40年以上にわたり、市民の文化的欲求に応え、広島の映像遺産を守り育ててきた映像文化ライブラリー。しかし、施設の老朽化という避けられない課題に直面し、今、その歴史は大きな転換点を迎えようとしている。
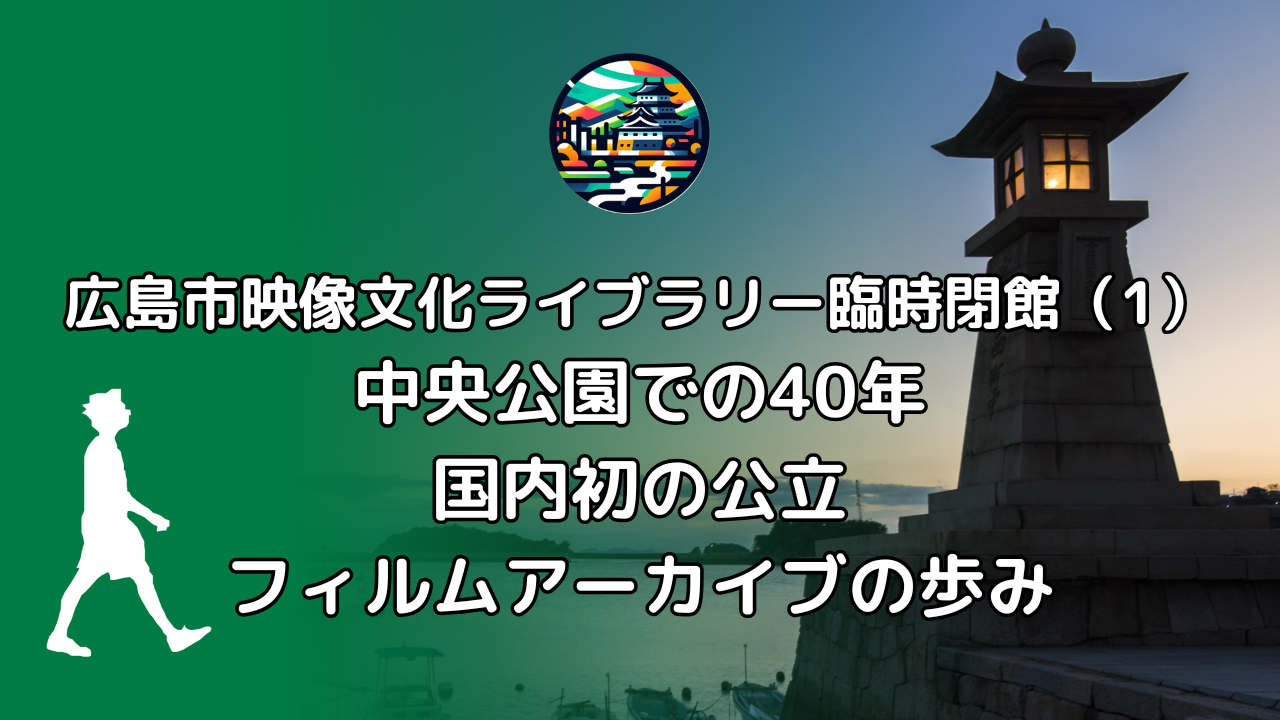
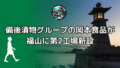
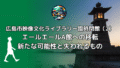
コメント