未来の農業を担う世代の交流と収穫
庄原市では実りの秋を迎え、2025年9月19日に庄原小学校の児童と庄原実業高校の生徒、合わせて55人が参加し、高校の田んぼで稲刈り体験を行いました。これは作物の栽培学習と生産者への感謝を育むための交流活動で、児童たちは高校生に鎌の使い方などを教わりながら、黄金色に実った「あきさかり」という品種の稲を刈り取りました。
その後、伝統的な方法である「ハデ干し」作業も協力して行いました。参加した小学生からは、稲刈りの楽しさと、美味しい米を食べるためには大人の努力が必要だと実感したという声が聞かれました。高校生からは、小学生が手際よく稲刈りをしていたこと、そして農業に興味を持つ子どもが増えてほしいという期待が述べられました。
特産品の加工と冬に向けた準備
三次市三良坂町では、「ピオーネいきいきグループ」が、規格外のピオーネを活用したジャム作りを最盛期としています。果肉の形を残すように工夫し、自然な色を出すために皮を袋に詰めて煮込む手法で、食べ応えのある特長的なジャムが作られています。生産数は今年は約500個に留まる見込みで、広島三次ワイナリーなどで販売されています。
また、三次市君田町の平田観光農園では、冬のイチゴ狩りに向けた準備が進められており、8月10日から「紅ほっぺ」などの3品種、合計1万8,000株の苗の植え付け作業が行われています。担当者は、温度管理に注意し、美味しいイチゴを提供できるよう努力したいと述べており、イチゴ狩りは12月上旬から始まる予定です。
尾道市では、温暖な気候と水はけの良い土壌を活かした県内一のいちじく栽培が盛んです。旬を迎えた「蓬莱柿(ほうらいし)」の収穫が行われており、今年の実は猛暑の影響で小ぶりながらも、甘みが増しているとのことです。収穫は11月ごろまで続く見通しです。
私の見解
庄原・三次・尾道の農業の現場からは、未来へつながる三つの流れが見えてきます。
- 次世代の育成(庄原市)
小学生と高校生が一緒に稲刈りをするという活動は、単なる農業体験ではなく「食と農への理解」を深める教育の一環です。大人の努力を実感した子どもたちが、食の大切さを自分ごととして考えるようになる点に大きな意義があります。 - 地域資源の有効活用(三次市)
規格外ピオーネのジャム作りは、フードロス削減と特産品のブランド化を両立させる好例です。量は少なくても、手仕事のこだわりが消費者に伝わることで、地域の魅力を発信する力になります。 - 持続可能な農業と観光(尾道市・三次市君田町)
イチゴ狩りやいちじく栽培のように、観光と結びついた農業は「体験型の価値」を提供します。単なる収益事業にとどまらず、地域の人々と都市部からの来訪者をつなげる役割を果たしています。
こうした取り組みは「子どもたちの学び」「資源の循環利用」「地域観光との連携」という3本柱で、これからの農業の持続性を支えていく動きだと思います。
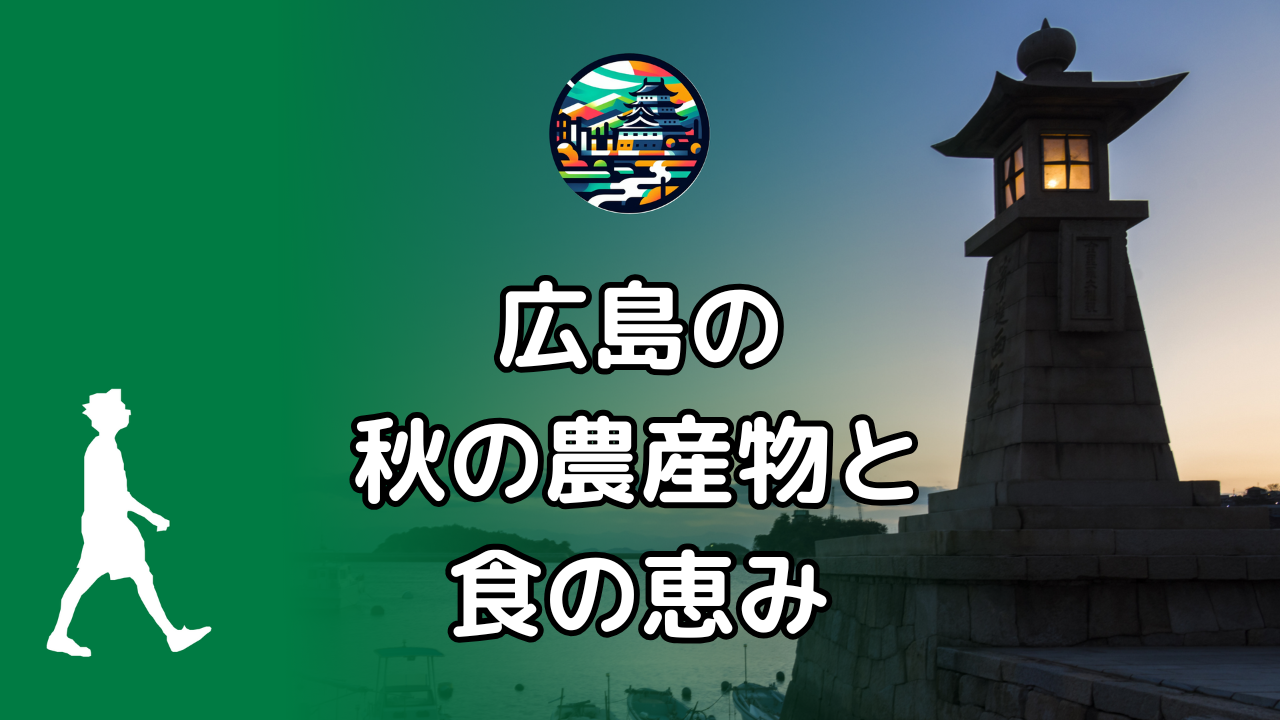
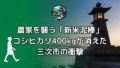
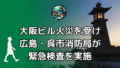
コメント