若者の転出超過が地域存続の危機に
広島県は、若者の流出が続き、転出超過が4年連続で全国最多という深刻な状況にあります。2025年6月1日時点で、県の推計人口は1977年以来48年ぶりに270万人を割り込みました。特に20代の女性の流出が多く、この状況が続くと結婚や出生数の減少につながり、少子化対策で他県に後れをとる可能性があります。
若者の転出は東京への一極集中だけでなく、愛知、大阪、福岡といった全国の都市部へも広がっており、広島県は「20代人口供給地からの脱却」を求められています。
企業連合「HATAful」と産学官連携の模索
こうした課題に対応するため、ひろぎんホールディングス、中国電力、マツダの3社は、転出超過解決を目指す共同企画「HATAful(はたフル)」を立ち上げました。9月16日には、HATAfulの活動の一環として、地元企業7社の社員と県内の大学生など約40人が参加し、課題解決に向けたワークショップが実施されました。
参加した若者からは、企業連携による魅力発信や、広島の自然や歴史の中でワークライフバランスを充実させる必要性が訴えられました。また、広島県警も、良質な雇用機会の不足という原因の解決に向け、職場環境の改善で先行する中国電力と意見交換を実施しています。
女性活躍推進と子ども議員の提言
広島市では9月8日、人口減少対策として、女性が働きやすく暮らしやすい街づくりについて、松井市長や経済界、大学の代表などが集まり、産学官で意見交換が行われました。会議では、女性が働きやすい企業への行政支援の必要性が強調されました。
また、8月には小中学生が参加する「子ども議会」が開催され、若者の転出超過対策として、広島の特色や良さを集めた「広島推しフェス」の開催が提案されました。
転出超過対策としての県内就職促進
広島県は、転出超過対策として、より多くの大学生に県内で就職してもらうことを目的とした企業をめぐるバスツアーを初めて開催しました。
9月8日に福山市の機械メーカーを訪れた県内外の大学生10人は、工場の最先端技術に触れたり、若手社員と座談会を行ったりしました。参加した学生は、今回のツアーにより就職活動の選択肢が広がったと感じたようです。
私の見解
広島県の若者転出超過は、単なる人口統計の問題ではなく、地域の存続に直結する深刻な課題だと思います。特に20代女性の流出は、結婚や出産に直結するため、将来的な少子化リスクをさらに加速させかねません。
一方で、企業や行政、大学が連携して「HATAful」のような取り組みを進めていることは希望の兆しです。ただし、若者が求めるのは単に「仕事の数」ではなく、やりがいある仕事、生活の豊かさ、キャリア形成の可能性です。
つまり、「広島に残る理由」を増やすことが最重要であり、そのためには以下のような戦略が欠かせません:
- 女性活躍推進:育児・介護と仕事の両立支援やキャリアアップの場を整える。
- 文化・自然資源の再評価:歴史や自然を楽しみながら働ける「広島ならではの暮らし」を発信。
- 若者参加型の企画:子ども議会やフェスのように、当事者が意見を出し実現に関わる機会を増やす。
県内就職促進も効果的ですが、就職後に「誇りを持って暮らせる広島」であるかどうかが鍵になります。経済・暮らし・文化が循環する総合的な魅力づくりが問われていると感じました。
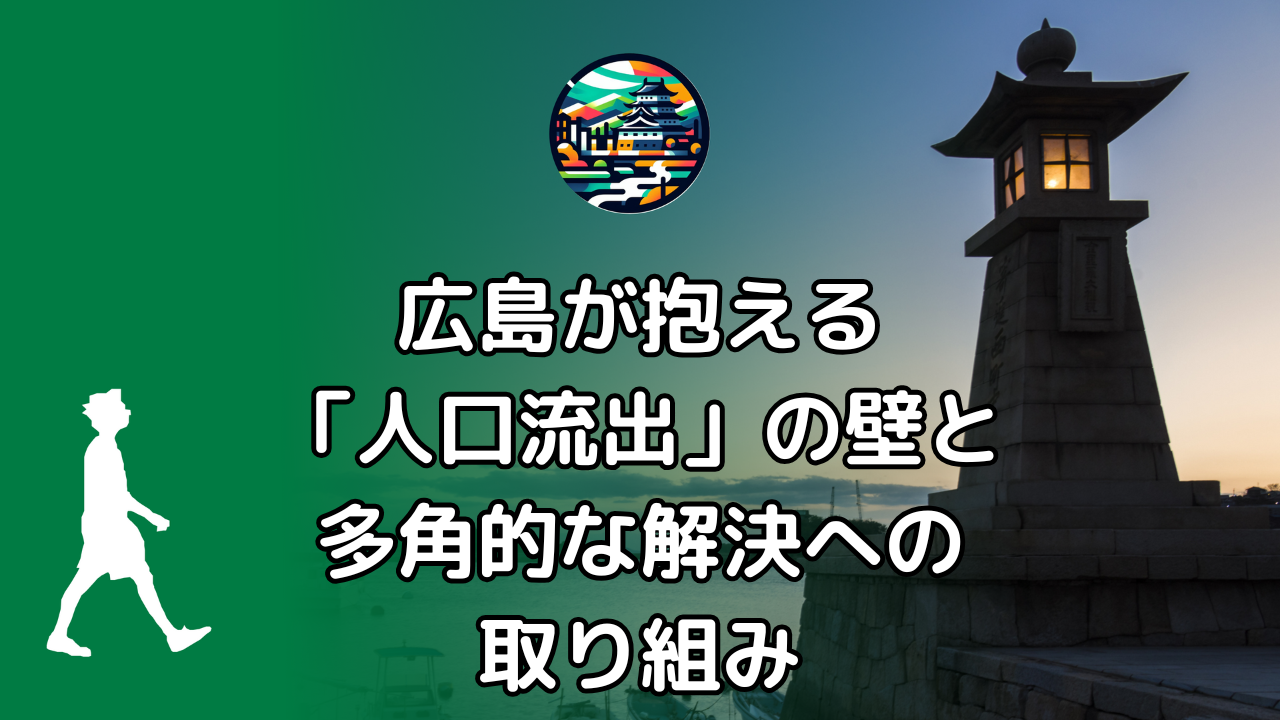
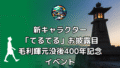
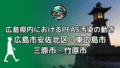
コメント