つらい口内炎、治らない理由は?
口の中が痛くて食事ができない――そんな経験をしたことがある人も多いのではないでしょうか。
口内炎の中でも「再発性アフタ性口内炎」は、何度も繰り返す厄介なタイプ。潰瘍のような傷ができ、しみる痛みで食事や会話が苦痛になります。従来はステロイド軟膏などが治療の中心でしたが、長期使用による粘膜の弱まりや免疫力の低下など、副作用のリスクも指摘されてきました。
広島大学が発見した「スギナエキス」の力
そんな中、広島大学の研究チームが注目したのが「スギナ(問荊)」という植物です。昔から生薬として知られるスギナの抽出物(EA)に、口内炎を治すだけでなく、痛みをやわらげる効果があることを発見しました。研究は、アース製薬と広島大学が共同で設立した「口腔炎症制御学講座」による成果です。
動物実験では、スギナエキスを塗ったグループで潰瘍の回復が早まり、痛みのために食事量が減っていたハムスターも再びよく食べるようになったとのこと。これにより、スギナエキスには「治す力」と「痛みを抑える力」の両方があることがわかりました。
痛みのメカニズムにも科学的裏づけ
さらに研究チームは、痛みの原因となる物質(TNF-αやIL-6、COX-2、サブスタンスPなど)がスギナエキスによって抑えられることを突き止めました。これは、炎症をしずめて痛みを和らげるという二重の効果を科学的に説明できる成果です。
今後に向けて
今回の発見は、ステロイドに頼らない自然由来の口内炎ケア製品の開発に向けた大きな一歩です。研究チームは今後、スギナエキスの中で実際に効果を発揮している成分を特定し、人での臨床試験へと進めていく予定です。副作用の少ない新しい口内炎治療法が実現すれば、つらい痛みに悩む多くの人の助けとなるでしょう。
私の見解
広島大学の成果は、スギナ(問荊)抽出物が口内炎の治癒と鎮痛を同時に改善する可能性を示しており、ステロイドに代わる安全性の高い選択肢として大いに期待できます。
分子レベルではTNF-α、IL-6、COX-2やサブスタンスPの発現抑制が示され、炎症制御と疼痛抑制の両面で合理的なメカニズムが確認されています。QOL改善に直結する点が魅力です。
ただし現時点は動物モデルの知見にとどまるため、有効成分の同定、投与量・毒性の評価、ヒト臨床試験による再現性確認が不可欠です。慎重かつ積極的な検証を期待します。
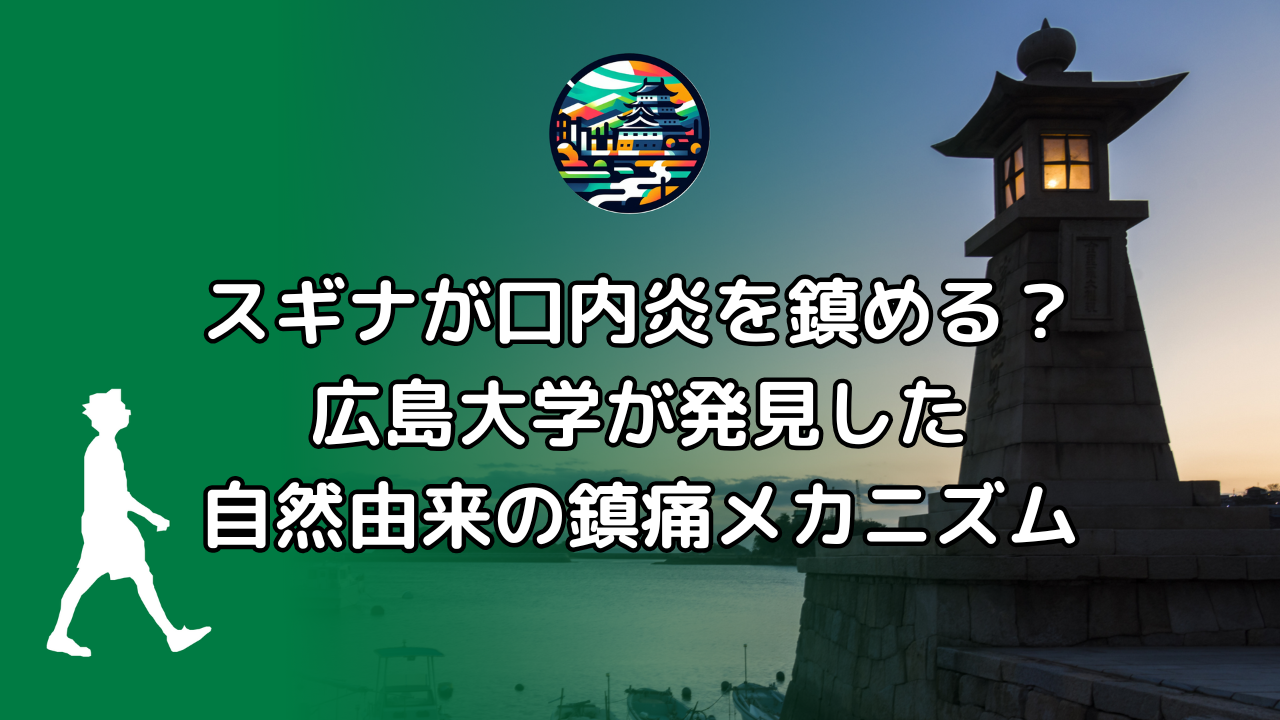
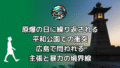
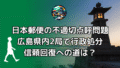
コメント