2人目の候補者、猪原真弓氏が立候補を表明
任期満了に伴う広島県知事選挙(10月23日告示、11月9日投開票)に向けて、無所属新人の猪原真弓氏(64)が10月7日に立候補の意向を表明しました。猪原氏は尾道市出身で、尾道商業高校を卒業後、医薬品卸会社に定年まで勤務した経歴を持ちます。現在は新日本婦人の会県本部委員であり、共産党県東部地区の常任委員も務めています。猪原氏は、共産党県委員会などで組織された「清潔であたたかい民主県政をつくる会」が擁立し、共産党の推薦を受けています。
猪原氏は、県民の命と暮らしを守る県政への転換を目指すことを掲げています。また、主な政策として、子どもの医療費助成を18歳まで無料にすることや、県立学校での給食費無償化、子育て支援策の充実、そして県職員の不祥事根絶などを実現させたい考えを示しました。出馬会見では、すべての県民が豊かになれるよう、県民と協議しながら行政を進めていきたいという点を強調しています。なお、猪原氏は昨年10月の衆議院選挙では広島5区から共産党公認(当時62歳)で立候補し落選していました。
選挙戦の構図と準備の徹底
知事選には、猪原氏の他に、既に無所属新人で前副知事の横田美香氏(54)が出馬を表明しており、横田氏は自民党の推薦を受ける見通しです。
選挙運動に先立ち、広島市中区では10月6日午前9時から立候補者のポスターを貼るための掲示板の設置が始まりました。広島市内では6日から21日までの間に2043か所、県全域では8034か所に設置される予定です。広島市選挙管理委員会の事務局次長は、県民生活に関する大切な選挙であるため、掲示板などを参考にして貴重な一票を投じてほしいと有権者に呼びかけています。
投票用紙の印刷と低投票率の課題
11月9日の投開票に向けて、10月8日午前には広島市内の印刷会社で、県知事選挙と県議会議員補欠選挙(県議補選)の投票用紙の印刷が始まりました。印刷作業は県選挙管理委員会の職員の立ち会いのもと、厳重に進められました。印刷された投票用紙は、知事選用が白色、県議補選用がクリーム色の2種類で、合計で約244万枚(正確には231万7400枚または約243万7千枚)です。これは県内の有権者数(約227万6000人)に予備分を加えた数で、仮に投票率が100%になっても十分に足りる枚数となっています。これらの投票用紙は10月10日に県内各地の選管へ発送される予定です。
この投票用紙には、開票作業を迅速化するための特別な工夫が凝らされています。用紙には「BPコート紙」という特殊な加工が施されており、折って投票箱に入れてもすぐに元の状態に戻るため、開票時に用紙を開く作業が不要となり、作業効率が向上します。また、夏の参議院選挙時に懸念された「鉛筆で書いても消えないか」という点についても、消えることはないことが確認されています。印刷は1時間に1万2千枚という高速で行われ、機械によるチェックだけでなく、熟練の職人が傷や汚れを人の目で確認する作業も行われています。
一方で、過去の広島県知事選挙の投票率は30%前後と低い状況が続いており、前回の2021年知事選でも34.67%で過去7番目の低さでした。今回の投票用紙の印刷や発送にかかる経費は約1300万円が税金から支出されているため、県選管の事務局長は、県民一人一人の声が届くよう準備を進め、投票率の向上に努めたいと述べ、無駄にしないためにも投票への参加を呼びかけています。
私の見解
猪原真弓氏の立候補表明により、今回の広島県知事選は明確な対立構図が見えてきました。行政経験のある候補と、生活者の視点から政策を訴える候補という対比が、県民にとって選択の幅を広げる形となっています。政策論争の中身に注目したいところです。
投票用紙の印刷や掲示板設置といった準備が着実に進む一方で、投票率の低さは依然として課題です。どれだけ多くの県民が「自分ごと」として政治に関心を持てるかが、民主主義の成熟を左右する重要な指標になると感じます。
候補者それぞれが示す政策だけでなく、実現に向けた具体性や持続可能性も見極めたいところです。暮らしに直結する選挙だからこそ、一票の重みを再認識し、主体的な判断を持って投票に臨みたいと思います。
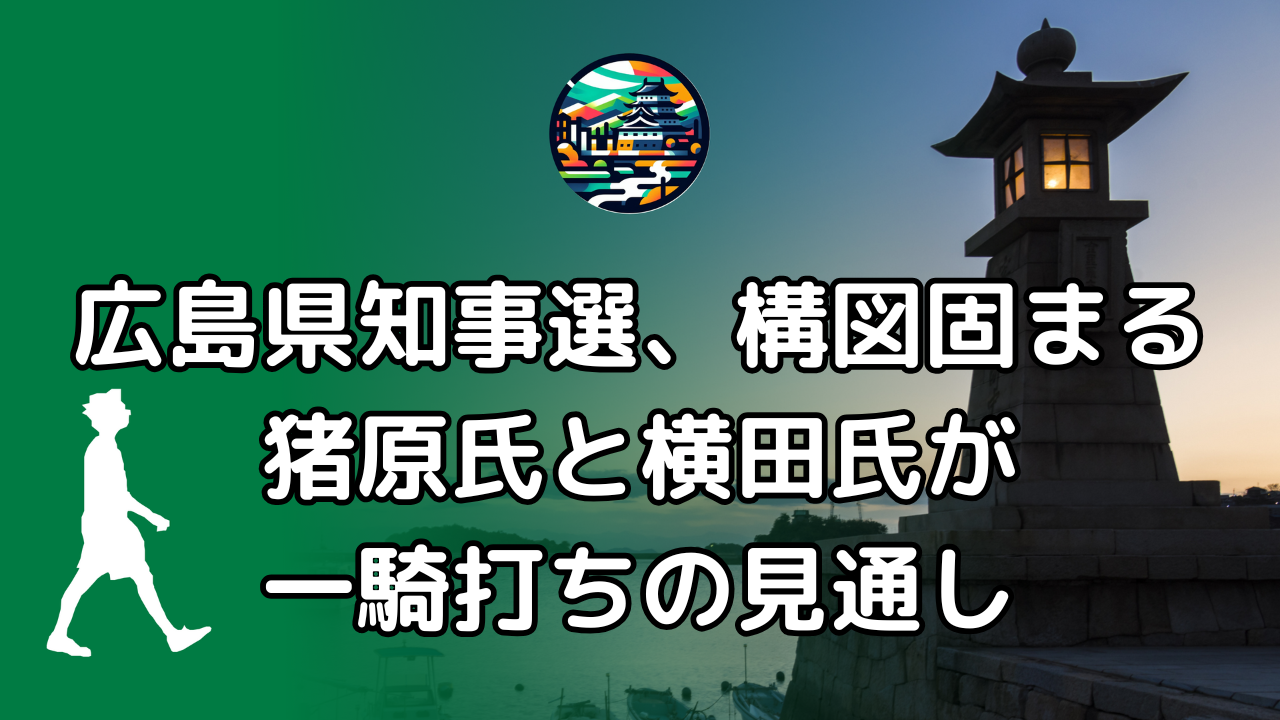
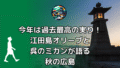
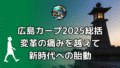
コメント