実証運行の背景にある深刻な課題
事業を取り巻く厳しい現状
路線バス事業は現在、運転手不足や収支の悪化といった厳しい環境に直面しています。広島県内のバス業界では、コロナ禍の2020年からの5年間で運転手が約1割減少するなど、人手不足が深刻化しています。
特にJRバス中国広島支店では、現在91名の乗務員が在籍しているものの、業務量を鑑みると約8名の人員が不足している状況です。不足分については、乗務員の休日出勤や、免許を持つ事務員による代行乗務で補っているといいます。
共同運営組織による路線の最適化
広島市とバス会社各社が共同で運営する「バス協調・共創プラットフォームひろしま」は、路線の効率化と最適化を図り、持続可能なバス事業を目指しています。同組織は、1社だけでは実現が難しい路線の最適化を推進しています。
実際に2024年に別の場所で実施した実証運行では、広島バスと広島電鉄の取り組みにより、安佐北区の小河原車庫・矢賀・広島バスセンターを結ぶ路線で、1か月あたり約112万円の赤字削減に成功しました。
JRバス中国の担当者は、今回の施策によりバスサービスを向上させつつ効率化が図れたことを歓迎しています。
利便性向上のための具体的な施策
団地内路線の充実と運行本数の増加
広島市安佐北区の高陽地区(高陽台・矢口が丘など)では、朝夕のピーク時以外の日中はバスの利用客や便数が少ないことが課題でした。そこで、2025年10月6日から、広島交通とJRバス中国の2社が共同で、ダイヤとルートを統一して交代で運行する実証実験が始まりました。
従来の広島市中心部への直通便を減らす一方で、高陽車庫とJR安芸矢口駅の間を結ぶ路線を高陽地区内で往復させる形に変更しました。これにより、これまで日中3時間ほど空いていたバスの間隔が約1時間間隔に増便され、地区内の病院やスーパーへの移動利便性が向上します。
特に高陽台・矢口が丘を走るバスは、今回の実証運行で1日4便から8便に増便されましたが、効率的な運用により運行に関わる人数は増やしていません。実証運行は12月30日まで毎日行われ、1日合計16便が運行されます。
利用者からの反応と新たな移動手段の提示
実証運行初日、団地内のバスを利用した住民からは、これまでは帰りの便がなくタクシーを利用していたため、便利になったという声や、タクシー代が高くなった中でバスが助けになるという喜びの声が聞かれました。特に高齢者が多く、免許返納者が増加している団地では、バスの増便により病院通いなどの利便性が高まることが期待されています。
一方で、広島市中心部へ行く際には、安芸矢口駅でJR芸備線に乗り換えるか、途中のバス停で直通便に乗り換える必要が生じています。ある大学生は、通学のために広島市中心部へ出やすくなるよう、できれば中心部まで路線を伸ばしてほしいという意見を述べています。
また、バスを待つ際の利便性向上のため、バス停近くの商業施設(フジグラン高陽)内には、待ち時間を表示する機器(バスロケーションシステムの案内板)が設置されました。今回の実証運行を通じて、利用者アンケートなどを実施しながら、課題の発見と持続可能な事業モデルの検証が進められます。
私の見解
今回の実証運行は、単なる「バスの増便」ではなく、地域全体の移動を見直す第一歩だと感じます。運転手不足という全国的な課題に対して、複数の事業者と行政が協力して取り組む姿勢は、広島市が掲げる“公共交通の共創”の好例です。地域に根ざした仕組みが持続可能性を高める鍵になるでしょう。
高陽地区のように高齢化が進む地域では、生活圏内での移動手段を確保することが極めて重要です。通院や買い物といった日常の移動がバスで叶う環境は、住民の安心感と生活の質を支えます。交通の利便性が向上することで、地域コミュニティの活性化にもつながると考えます。
今後は、利用データや住民の声を基に、路線の最適化や運行形態の見直しを継続していくことが求められます。持続可能なバス事業の成功は、他地域への波及効果も大きいでしょう。広島から始まる“共に支える交通”の形が、地域公共交通の新たなモデルとして注目されます。
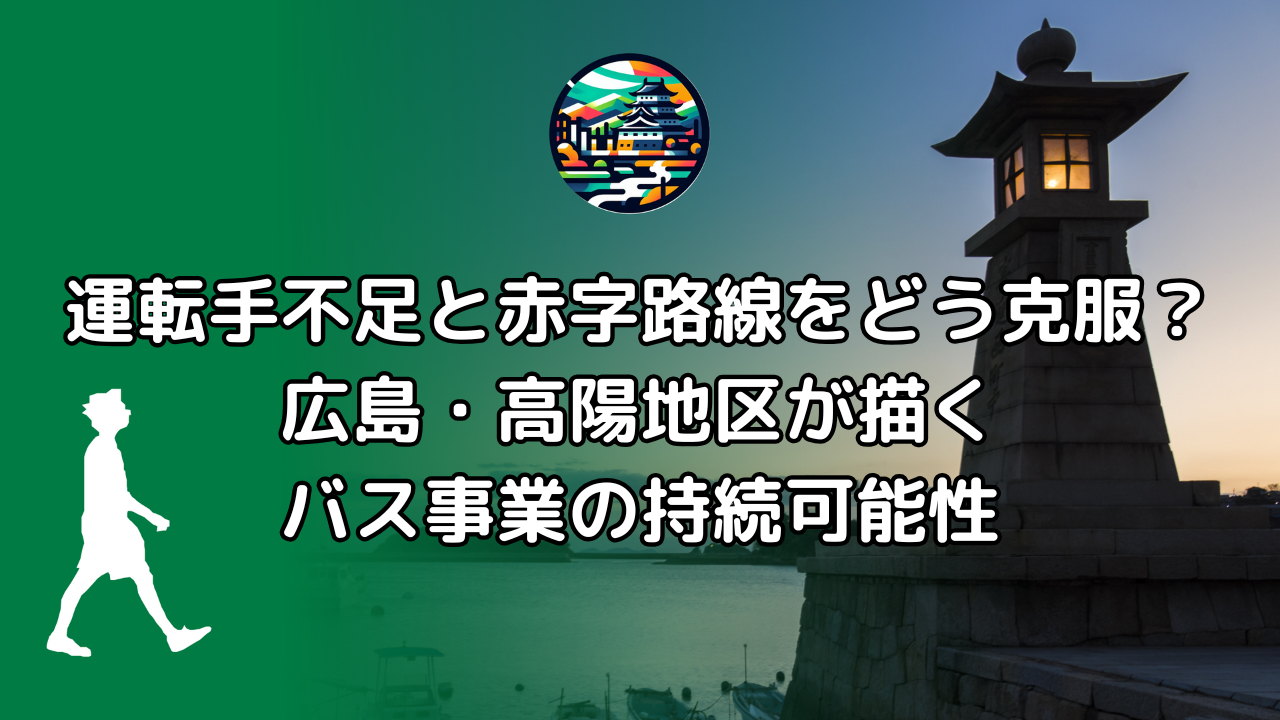
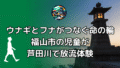
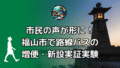
コメント