運転手不足の現状と対策
危機的な人材減少の状況
広島県のバス業界は、この数年で運転手が約1割減少するなど、人手不足が深刻な問題となっています。乗務員不足はバス事業の苦しい状況の一因であり、このままではサービス低下を招く減便といった施策しか取れないと懸念されています。
人材確保に向けた多角的な取り組み
「バス協調・共創プラットフォームひろしま」は、乗務員不足への対応として、消防局や自衛隊OBなどの採用を積極的に働きかけていく方針を示しています。また、広島県バス協会は、バス運転手という職業を少しでも多くの人にとっての職業選択の候補とするために、運転体験会を主催しています。
協会の専務理事は、体験を通じてバスを運転する楽しさを感じてもらい、運転手を職業の候補にしてもらうことを期待していると述べています。
運転体験会の実施と参加者の声
運転の楽しさを知ってもらう機会
広島県バス協会が主催した「バス運転体験会」には、県内6社のバス会社が参加しました。参加した約30人は、各社の担当者からの説明を受けた後、実際の路線バスと同じサイズのバスの運転を体験しました。 この体験会は、来月23日にも広島県福山市のロイヤルドライビングスクールで開催される予定です。
体験者・関係者が語るバス運転の実際
体験会に参加した人々からは、前向きな感想が聞かれました。バスの運転手を目指す男子大学生は、バスもマニュアル車も初めてだったものの、クラッチやギアなど専門用語が多く難しいと感じながらも「楽しかった」と振り返りました。転職を考えている50代の会社員男性は、体験会がなければバスの運転を経験できないため、非常に良い機会だったと評価しています。
ほかにも、乗用車と比べて「前輪よりも前に乗っている」ため、感覚が全く異なり、ミラーの数が非常に多いため「どこを見ればいいのか」と迷うほどやることが多い、という印象が語られました。
私の見解
広島県のバス業界が直面する運転手不足は、地域交通の持続性に直結する重大な課題です。人口減少と高齢化の影響により、運転職を志す若年層の減少が加速しています。これまで当たり前に存在した公共交通の利便性が、今後は維持できなくなる可能性があることを、私たちは真剣に受け止める必要があります。
一方で、体験会のような取り組みは非常に意義深いと感じます。実際に運転を体験することで、運転職の魅力や達成感を実感できるのは、求人広告だけでは得られない価値です。こうした機会が広がることで、潜在的な人材が「やってみたい」と思うきっかけになり、地域交通を支える新たな芽が育つのではないでしょうか。
今後は、働き方改革や待遇改善も含め、バス業界全体が長期的に魅力ある職場づくりを進めることが重要です。地域住民や行政も連携し、移動の確保を「自分ごと」として支える姿勢が求められます。交通を守るのは、運転手だけでなく、地域社会全体の意識と行動にかかっていると思います。
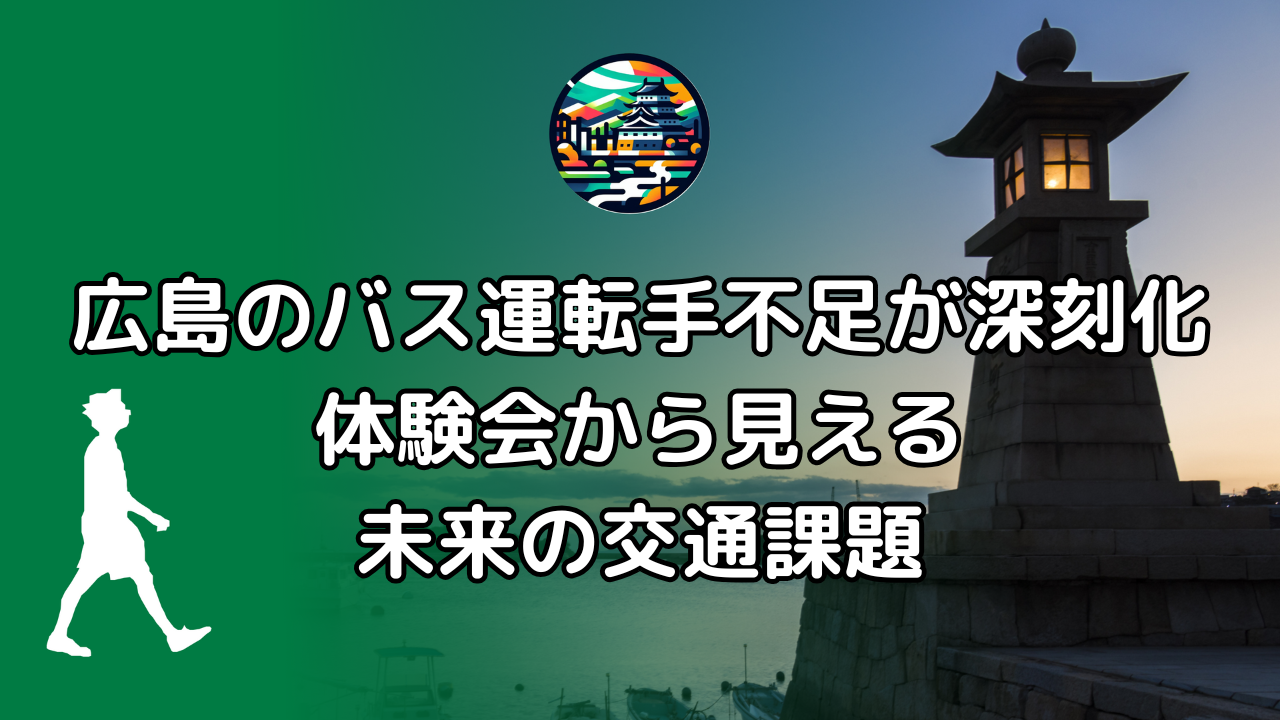
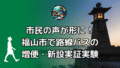
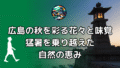
コメント