芦田川の歴史と風景を詳細に解説。海から陸地への変遷、人々の生活、治水工事の歴史など、芦田川の魅力を深く掘り下げます。芦田川の知られざる物語を是非ご覧ください。
芦田川の基本情報
芦田川はとても長い川で、その全長は86キロメートルもあります。芦田川は、広島県三原市大和町蔵宗という場所から始まります。ここは、山がちな地域で、標高570メートルもあります。
この川は、世羅台地という地域を通りながら、いくつもの小さな川、矢多田川や御調川などを合わせていきます。これらの小さな川を支川と呼びます。そして、広島県府中市にたどり着きます。
さらに下流に進むと、神谷川、有地川、高屋川などを合わせ、神辺平野という平らな地域を流れます。そして、瀬戸川を合わせ、最終的には広島県福山市の箕島町で瀬戸内海の一部である備後灘に流れ込みます。
芦田川が流れる地域全体を見ると、その面積は860平方キロメートルにもなります。このような大きな川は、一級河川と呼ばれます。
芦田川の歴史と人々の生活
芦田川は、備後地方の中心に位置し、長い歴史を持っています。芦田川は、地域の人々の生活と深く結びついてきました。その結果、今日の芦田川の風景が形成されています。
神辺平野の歴史的背景
今私たちが神辺平野と呼んでいる地域は、昔は「穴の海」と呼ばれていました。それは、この地域が海だったからです。その証拠に、今の府中市あたりまで海水が流れ込んでいたことがわかっています。
しかし、その海がどうやって陸地に変わったのでしょうか。それは、芦田川の力によるものです。芦田川は、雨季になると度々洪水を起こし、そのたびに大量の土砂を運んできました。その土砂が積もり積もって、徐々に海が埋まっていき、広い平野が形成されたのです。
そして、弥生時代になると、この新しくできた土地に多くの人々が住むようになりました。人々はこの地を「穴国」と呼び、新たな国を作り上げていきました。
水野勝成とその時代
江戸時代の1619年に、水野勝成が蝙蝠山という場所に城を築き始めました。水野勝成は、その頃の芦田川の地形をよく見て、工夫を凝らしました。府中から南側の山寄りに曲がりくねって流れていた芦田川を、一直線にして東に付け替えました。そして、中津原で川を直角に南下するように改修しました。
また、この曲がる角には、砂と土でできた土手を作りました。これを二重にして、洪水が起こったときにこの地点で水が溢れ出すようにしました。これにより、下流の城下町が洪水から守られるようになりました。
さらに、城山と城背の両社八幡のある永徳寺山(松山)との間には、芦田川の一部を大きく流して新たに吉津川を作りました。この吉津川は、大きな船が通ることができ、物資の輸送に役立てられました。
芦田川沿いの災害
水野勝成は土木工事に長けた人々を集めて、新たな土地を開拓し、池を掘り、治水工事を行いました。これにより、田畑の面積が大きく増えました。
しかし、その一方で、芦田川沿いでは毎年のように洪水が起こり、災害が絶えることはありませんでした。特に、1673年には、大洪水が起こり、鎌倉時代から繁栄を続けていた「明王院」の門前町である草戸千軒町が芦田川の川底に沈んでしまいます。
また、芦田川の支川である高屋川が合流する堂々川は、表土が流出しやすいため、度々土石流が発生していました。その結果、堂々川の下流に位置する備後国分寺は、何度も土石流によって破壊されてしまったのです。
福山藩の砂防工事
福山藩は、大規模な砂防工事をしました。これは、藩の重要な施設として、広い範囲で行われました。その一部として、「砂留」と呼ばれる砂防ダムが28基も作られました。これらのダムは、堂々川を含むいくつかの川に設けられました。
「砂留」とは、川の流れを調節し、土砂の流出を防ぐためのダムのことを指します。これにより、大雨などで川の水位が上がったときでも、洪水を防ぐことができます。
特に、堂々川に設けられた砂留は、その価値が認められ、国の登録有形文化財に登録されています。その中でも、最上流に位置する6番砂留は、1835年に作られたものです。
この上流部には、「堂々公園」という公園があります。ここは、堆砂敷きを利用して作られ、四季折々の木々や手入れされた低木、そして長さ344mの石で組まれた水路などがあり、人々が憩う場所となっています。特に6月上旬には、砂留周辺でホタルが乱舞する美しい光景を見ることができます。
また、芦田町福田の別所砂留のうち、規模の大きい14基は、土木学会から選奨土木遺産に選定されています。地元の人々からは、「福山のマチュ・ピチュ」と呼ばれ、親しまれています。
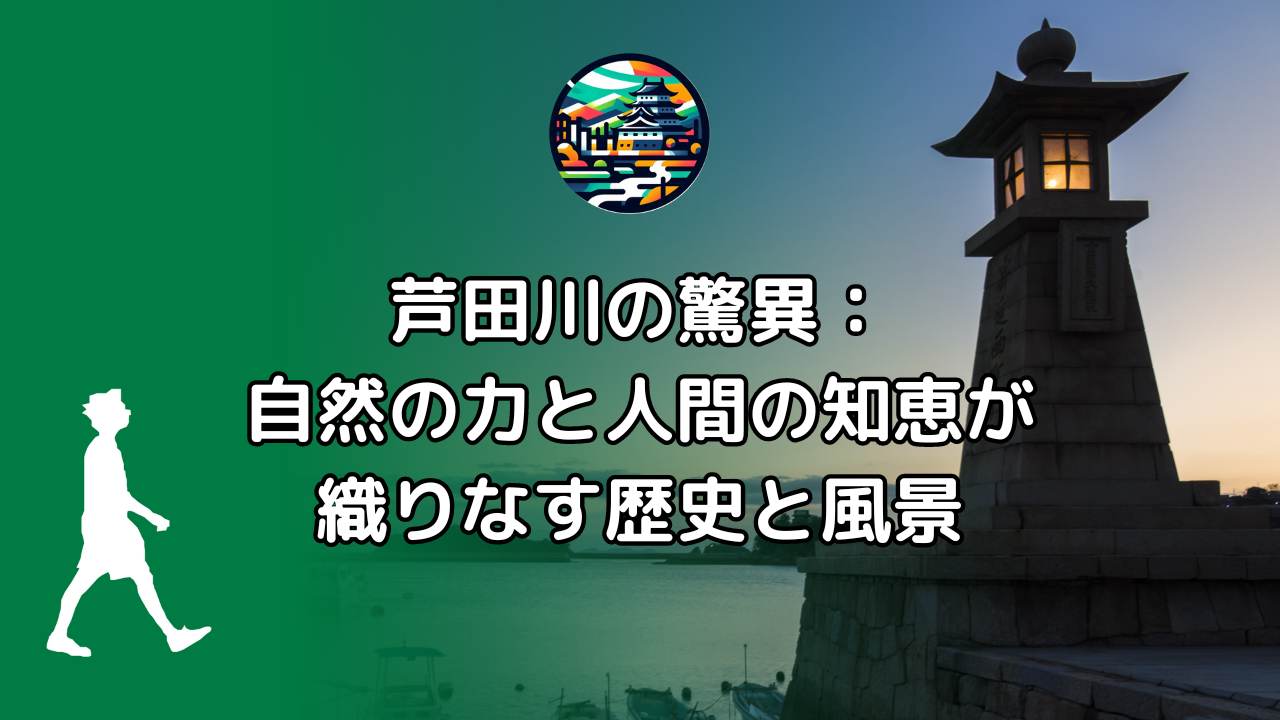
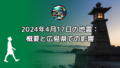

コメント