掘削工事の完了と遅延の短縮
広島高速5号線「二葉山トンネル」の掘削工事は、掘削機のトラブルや地表面の隆起などで度々中断していましたが、2025年4月には掘削が完了しました。工事完了の見通しは当初の2022年度から遅延していましたが、夜間作業の実施などにより、最終的に約1年短縮されました。
地盤変動に対する専門家の承認と住民の不安
工事の発注者である広島高速道路公社は、トンネル工事に伴う地表面の変動について、掘削終了後の1年間の計測データに基づき、2025年7月に専門家委員会から「変動は収束した」との承認を得ました。しかし、トンネルルート上にある広島市東区牛田地区の住民からは、「今も地盤沈下が続いている」「障子が動きにくいなどの不具合が進行している」といった不安の声が相次いでいます。
住民説明会での抗議と不満
2025年9月21日には、地表面の変位が収束したとの判断を受けて2回目の住民説明会が開かれましたが、住民側からは「収束の判断理由の説明が不足していて不安がぬぐえない」といった抗議や不満の声が上がりました。
住民の退席と公社側の対応
一部の住民は「安全安心を確保するところまでデータを示すべき」と訴え、説明会を途中で退席しました。公社側は、住民の意向を踏まえ、今後さらに少なくとも10年間は地表面の計測を続けることで理解を求めています。
追加費用を巡る裁判
二葉山トンネル(2027年度上期に開通見通し)の長期化に伴い発生した追加費用を巡っては、工事を受注した大林組などの企業グループが、発注元の広島高速道路公社に対し、費用の負担を求めて東京地方裁判所に訴えを起こしました。公社側は、契約約款に基づき適正に対応する姿勢を示しています。
私の見解
二葉山トンネル掘削工事は、度重なる中断を経てようやく掘削完了に至りましたが、工事遅延・地盤変動・追加費用といった複数の課題を抱えたまま「開通予定2027年度上期」に向かっています。
ポイントは三つあります。
- 工期短縮の成果と課題
夜間作業などで最終的に1年短縮されたことは、工事の効率化という点で評価できます。しかし「当初計画より大幅に遅れた」という事実は残り、信頼回復には至っていません。 - 専門家判断と住民の不安の乖離
専門家委員会は「変動は収束」と認定しましたが、住民は実生活の中で「障子が開きにくい」「沈下が進んでいる」と感じており、科学的データと体感の間にギャップが生じています。説明不足が住民の不信感を強めたと言えます。 - 裁判へ発展する追加費用問題
大林組ら施工側と公社の対立は、公共事業のリスク分担のあり方を問うものです。長期化・追加費用は公共インフラの整備において避けられない面もありますが、契約・責任範囲をめぐる法的争いが表面化したことで、事業の透明性や公共負担の妥当性が社会的に問われています。
総合的に見ると、工事完了自体は前進ですが、「技術的成果」よりも「社会的説明責任」が今後の焦点になるでしょう。
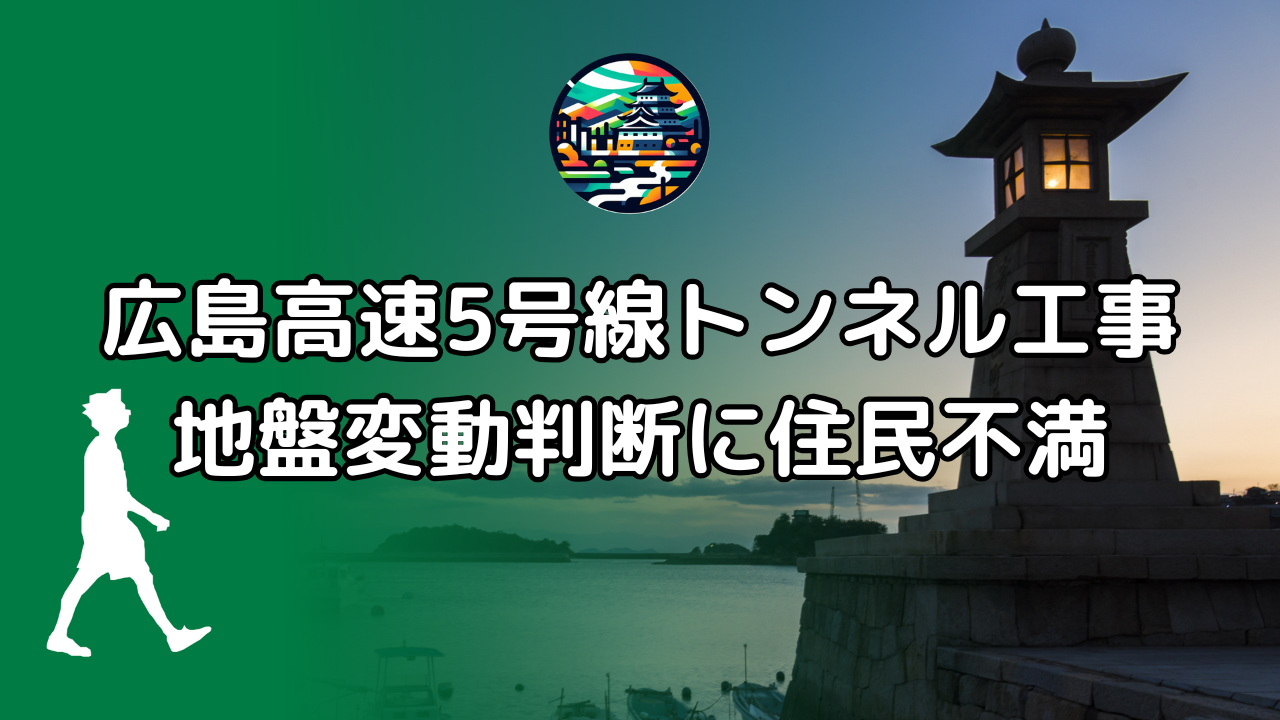
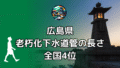
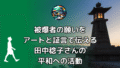
コメント