猛暑の影響で牡蠣の水揚げが遅延
広島県特産の養殖かきは、日本国内の養殖生産量の約6割を占める人気の冬の味覚です。例年、水揚げは10月1日に始まりますが、今シーズンは夏の猛暑による海面水温の上昇が影響し、かきの成長が遅れています。このため、漁業関係者は収穫開始を10月20日まで延期することを決定しました。昨年も同様の理由で約20日間遅れました。漁業協同組合の代表者によると、生産者らとの協議を経て、消費者へ最高品質のかきを全国に届けるために、収穫期間を短縮し、水揚げ量を制限する方針が取られました。
豊作の一方で深刻化する米作りの水質汚染問題(広島・三原市)
政府が米の増産方針を表明する中、広島県三原市の一部の地域では、水質汚染への懸念から米作りが困難な状況にあります。三原市本郷町の田んぼでは、今年、短期間で育つ品種「ヒカリ新世紀」が大豊作となりましたが、作付けできたのは田んぼの半分ほどに留まりました。原因は、田んぼのすぐ上流にある本郷最終処分場の排水への懸念です。この処分場は3年前からゴミの埋め立てが始まり、これまでに浸透水から基準値を超える水質汚染が3回検出され、行政指導を受けています。
日名内上地区の農家は、2年前に川の水を使わず、山水や別の谷水を取水するように水路を新設しましたが、汚染された川の水を使ったと見られることを避けるため、農協に米を卸すことができなくなっています。農家からは、環境が悪化し、川がもはや川の機能を果たしておらず排水路になっているとの声が上がっています。さらに、処分場から1.5km下流の日名内下地区でも、川が泡立ち、水が青黒く変色する異様な状態が度々目撃されており、地域住民は「こんな水を使って米が作れるわけがない」と感じています。
日名内下地区では、水路が整備されても水が届かない場所もあり、地区全体で510アールのうち半分以上の265アールで作付けができず、3軒の農家は完全に稲作を断念しました。ある住民は、水質悪化を実感し、コンバインも処分し、汚水問題が解決しない限り米作りは再開しないと決意しました。
新たな懸念として、住民の依頼による調査で、処分場の排水から有機フッ素化合物(PFAS)が国の暫定指針値を超えて検出されました。これを受け、広島県は日名内川と周囲の井戸で採水し、調査を進めています。一方、2025年10月10日には、処分場の設置許可取り消しを求める控訴審が開かれる予定です。住民らは、半世紀以上前の法令では現在の環境汚染を防げないとして、法改正を国に求める決議も行っています。
秋の味覚、栗とマツタケの話題
広島県三次市では、秋の味覚であるクリの収穫が進んでいます。三次市上田町の栗林では、丹沢栗や伊吹など約50本の栗の木が栽培されており、生産者は今年の夏に気温が高く日照りが続いたことで、例年になく実が大きく豊作だと述べています。収穫されたクリは「平田観光農園」で、200グラム500円の焼き栗として10月末まで販売されています。
また、世羅町にある国産マツタケの販売店では、9月20日から岩手県産などのマツタケの入荷が始まっています。今年の入荷は猛暑の影響で例年より1〜10日ほど遅れており、入荷量も去年の5分の1程度と少ない状況です。このため、価格は1割程度上がっており、最も高額なものは18センチで700グラム15万円の値がついています。広島県内産のマツタケは、気温が下がる10月中旬に入荷が見込まれています。
私の見解
猛暑で牡蠣の成長が遅れ、収穫延期となった判断は品質と安全を優先した妥当な対応だと考えます。短期的な供給不安は避けられませんが消費者も理解を示してほしいです。
三原市の水質汚染とPFAS検出は農家の暮らしと食の安全に直結する重大事です。県や国は速やかに原因究明と対策、被害補償を進め、再発防止を明確にすべきです。
栗の豊作は喜ばしい一方、マツタケの入荷減と高騰は気候変動の影響を示しています。地元産を意識的に選び生産者を支援するとともに、長期的な適応策を議論する好機です。
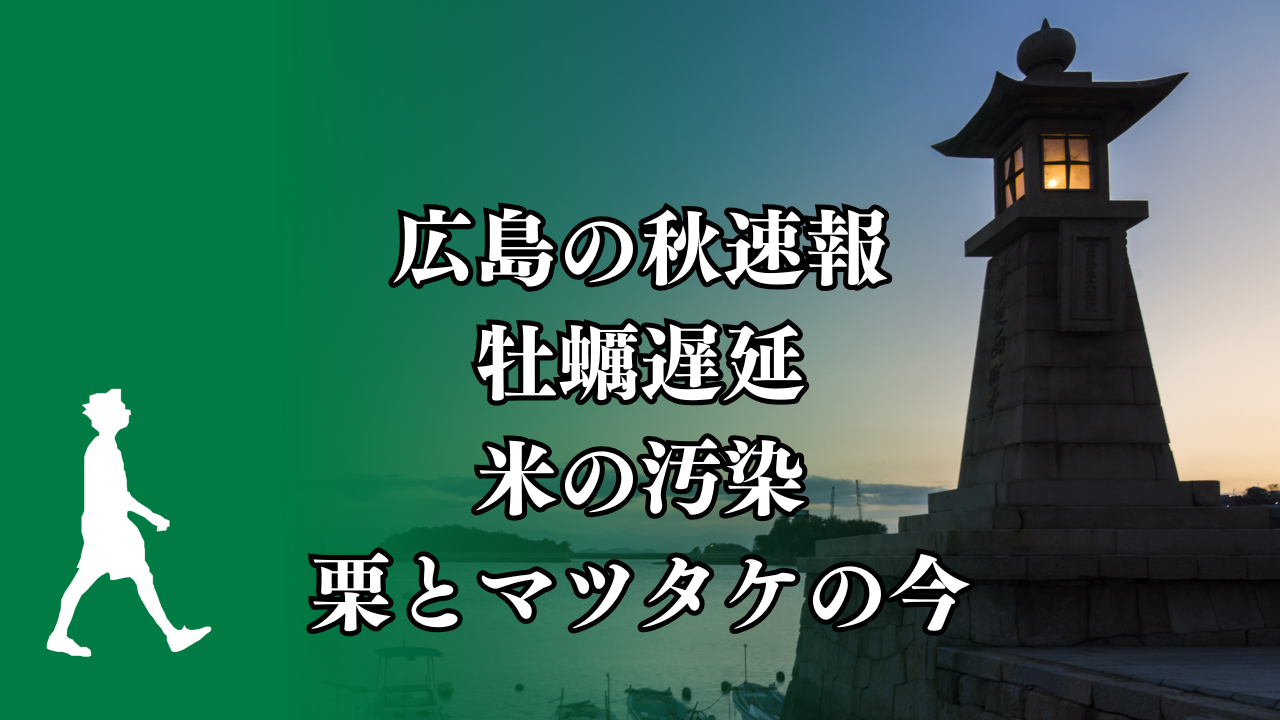
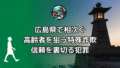
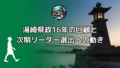
コメント