認知症への理解とサポート深化:広島県内各地で啓発活動
「認知症の日」に合わせた啓発と専門講演
2025年9月21日の「認知症の日」(世界アルツハイマーデー)に際し、広島県内では認知症に対する正しい理解を促す活動が活発化しました。JR広島駅では、認知症患者の家族などがチラシを配布し、当事者やその家族を支えることへの理解を呼びかけました。
広島市の担当者は、認知症によりできなくなることがあっても、周囲がそれを補えば地域で暮らし続けられるとし、優しい地域づくりを進めていく意向を述べました。広島市は9月27日にも、認知症の症状や関わり方について学ぶ支援者向けの講座を開く予定です。
福山市では、9月6日(土)に広島県民文化センターふくやまで、福山市民を対象とした「世界アルツハイマーデー記念講演会」が開催されました。ここでは、メープルヒル病院の石井伸弥医師による最新の認知症治療とケアに関する基調講演や、認知症の人と家族の会会員による介護体験発表などが行われました。
認知症情報集約サイトと中学生によるカルタ制作
福山市は9月19日、認知症に関する情報を一元化したウェブサイト「福山市認知症ナビ」の情報を更新しました。このサイトは、認知症の基礎知識、経過と対応、相談窓口、通いの場、学べる講座、そして認知症の人のもしもに備える制度など、幅広い情報を掲載しています。また、認知症の当事者、介護経験のある家族、支援者(戸手高校の生徒など)の声を掲載し、不安を抱える人々に寄り添うことを目指しています。
一方、東広島市では、地元の松賀中学校の美術部の生徒たちが、認知症患者や家族をサポートする団体からの依頼を受けて、認知症の理解を深めるためのカルタを制作しました。
生徒たちは事前に「認知症サポーター養成講座」を受講し、例えば「さぽーとをすすんで行おう私たちが」や、認知症患者の服などに貼られるQRコード付きの「らベルシール」をきっかけにするという読み札と絵札を作成。このカルタは9月中に完成し、地域の小学校などで活用される予定で、生徒は認知症の人が楽しく暮らせる地域にしたいと話しました。
認知症を巡る社会と最新の知見
行方不明事例と市民の協力
広島県内では年間で約350件もの認知症高齢者の行方不明届け出が出されており、その捜索は喫緊の課題です。広島市安佐北区では、8月11日から認知症が進行していた82歳の女性が行方不明となり、9月になっても大雨の中、娘が捜索を続けている状況が報じられました。
娘は、高速道路の下など、家から遠く離れた場所が最後の目撃情報であることを明かし、GPSなどの対策を後悔している点があるとしつつ、情報提供を求めています。
一方で、市民の協力により高齢者が保護された温かい事例も9月にありました。福山市では先月19日午前3時頃、仕事を終えた会社員の女性が道路の真ん中を歩く93歳の高齢男性を発見し、声をかけたところ、男性は「帰るところが分からん」と答えました。
男性は認知症の症状があり、岡山県真庭市の自宅から行方不明になっていましたが、女性が携帯電話を通じて家族と警察に連絡し、無事保護されました。警察は道に迷っている高齢者を見かけた際の通報を呼びかけています。
認知症当事者が活躍するレストラン
認知症への理解促進という点で注目を集めたのが、9月22日に庄原市で開催された「注文をまちがえてもおいしい店」です。この1日限定レストランは、認知症のお年寄りが接客を担当し、注文間違いを笑って許し合う寛容な社会のモデルを示しました。
来場した客は温かい雰囲気を感じたとし、実行委員長は、失敗をお互いさまとする精神が広がることに期待を寄せました。
認知症リスク低減に向けた研究成果
近年のサイエンス研究では、認知機能低下に対する新たな知見が示されています。2000年から2024年までの17件の研究を分析した体系的レビューによると、大規模でつながりの深いソーシャルネットワーク(社会的ネットワーク)を持つ人ほど、認知症や認知機能低下を発症するリスクが低いことが一貫して判明しました。特に、感情や社会的行動に関わる脳領域である扁桃体の健全性を維持する傾向が見られました。
また、近年に生まれた若い世代は、以前の世代と比較して高齢になっても認知症を発症する可能性が低いという研究結果も示されています。これは、20世紀半ば以降に女性の教育へのアクセスが向上したことや、喫煙の減少、心臓病などの疾患に対する治療改善といった介入が関係している可能性があると専門家は指摘しています。
私の見解
広島県内の取り組みを見ると、認知症に対する理解や支援は単なる医療や福祉の問題ではなく、地域社会全体で支える文化作りとして進展していることが分かります。
- 地域啓発活動:JR広島駅でのチラシ配布や講演会は、認知症を「本人だけの課題」ではなく、家族や地域の協力で補える社会資源として提示している点が重要です。
- 中学生や高校生の参加:カルタ制作や認知症サポーター養成講座の受講は、若い世代に「理解と共感」を自然に植え付ける効果があり、地域の長期的な支援文化を形成します。
- 社会参加の促進:「注文をまちがえてもおいしい店」のような取り組みは、認知症当事者が主体的に社会に関わることで、偏見や不安を和らげると同時に、本人の自己肯定感や社会的ネットワークの維持にも寄与します。
広島県内の事例は「認知症支援の総合モデル」と言えます。医療・福祉・教育・地域活動が連携し、若者から高齢者までが協力することで、認知症当事者が安全かつ尊厳を保って暮らせる社会づくりにつながっていることが特徴です。
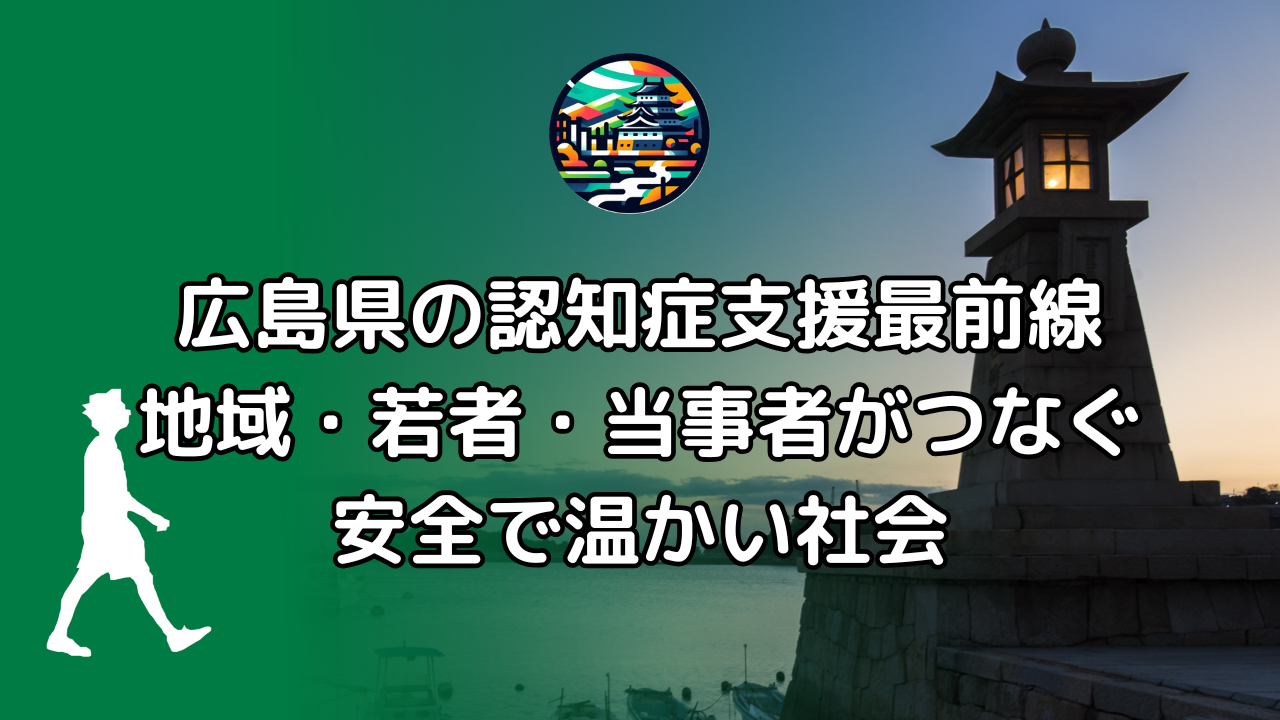
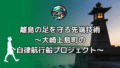
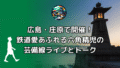
コメント