事故増加傾向と運動の重点目標
9月21日から30日まで、秋の全国交通安全運動が実施されています。この期間の重点は、歩行者の安全な道路横断、反射材や明るい色の服の着用促進、「ながらスマホ」や飲酒運転の根絶です。
広島県内の交通事故死者数は、9月20日時点で42人と、去年の同じ時期よりは減少していますが、秋から冬にかけては日没が早まるため、例年重大な交通事故が急増する傾向にあります。警察庁のデータでも、歩行者の死者数は夏至の6月(約55人)に対し、冬至の12月(約127人)と倍以上に増えています。
広島県警は、運転者に対しては早めのライト点灯やハイビームの活用を通じて、自車の存在をアピールするよう呼びかけています。また、歩行者には反射材の着用などを求め、互いに注意し合うよう訴えました。
ユニークな地域キャンペーン
広島県内各地では、ユニークな方法で交通安全が呼びかけられました。
- 神石高原町
- 道の駅で警察官や交通安全協会の関係者約30人が、「交差点ではトマットこう(止まっとこう)」という語呂合わせを込めて、町内で採れたトマトを配布しました。
- 世羅町
- 道の駅世羅では、「梨(ナシ)」と「事故ナシ」をかけて交通安全を願う恒例のイベントが15年以上続いています。ここでは特産の豊水ナシがドライバーに配られ、高齢者が交通事故死者数の半数を占める現状を踏まえ、早めのライト点灯と反射材の着用が特に呼びかけられました。
- 五日市市
- 五日市市でも「梨(ナシ)」と「事故ナシ」をかけて、地元で採れた梨がドライバーに配られました。
私の見解
交通事故は「季節性」が強い現象で、特に秋から冬にかけての夕暮れ時に増加することがデータからも明らかです。歩行者にとっては反射材や明るい服装が「命を守る装備」となり、運転者にとってはライトの早め点灯が「他者を守る合図」となります。つまり、どちらか一方の努力だけでは不十分で、歩行者と運転者の双方が「相互注意の文化」を持つことが不可欠です。
また、広島県内でのトマトや梨を活用した地域キャンペーンは、単なる啓発ではなく「記憶に残る仕掛け」として優れています。交通安全はどうしても抽象的・義務的に感じられがちですが、地域の特産物や言葉遊びを通じて親しみを持たせる工夫は、行動変容につながる可能性が高いと考えます。
重点目標の「歩行者の安全確保」「反射材着用」「ながらスマホ防止」「飲酒運転根絶」は、どれも事故を減らす基盤的な要素であり、この時期に意識を高めることは大きな意味があります。広島県では高齢者の比率が高いことも踏まえると、地域特性に即した啓発の継続が今後の鍵になると考えます。
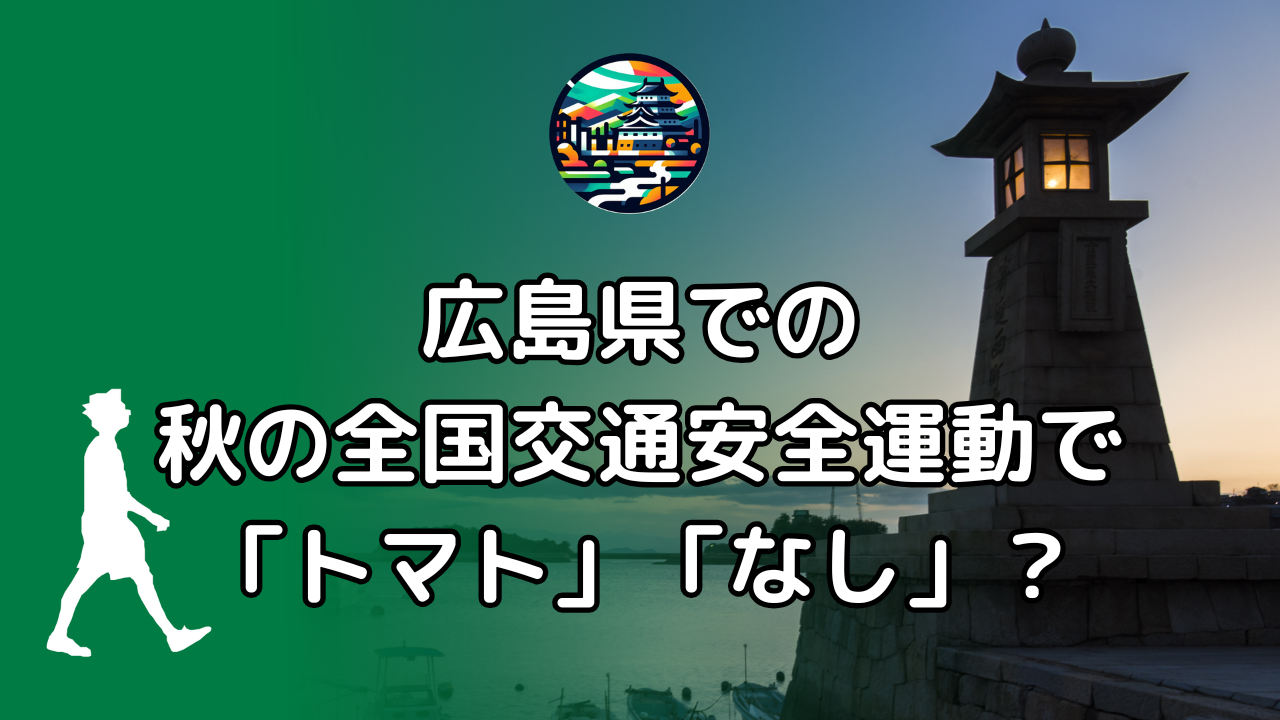
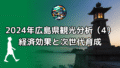
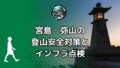
コメント