廃線が生まれる理由
野川氏は自身の趣味である「廃線探訪」について語り、なぜ必要とされて作られた鉄道が廃線になってしまうのかという問いを投げかけました。主な理由として以下の4点を挙げました。
- お客さんや運ぶものが減ったから: 人口減少や、木材・石炭などの資源輸送の終了が背景にあると説明しました。
- 運営する会社がなくなってしまったから: 炭鉱の閉鎖などで鉄道会社が倒産するケースを紹介しました。
- もっと便利な路線や交通手段ができたから: 高速道路や高速バスの開通により、既存の鉄道路線が競争に敗れる事例(芸備線や木次線、備後落合駅周辺の状況を例に)を挙げました。
- 災害からの復旧が難しいから: 多額の費用と時間、そして将来的な利用者が見込めない場合、復旧を断念し廃線となるケース(山口県の美祢線など)があると説明しました。
これらの理由は最終的に「お客さんや運ぶものが減った」という本質的な課題に帰結すると分析しました。
北海道・タウシュベツ川橋梁の事例
廃線探訪の魅力として、北海道十勝地方にあるタウシュベツ川橋梁を紹介しました。これはかつての国鉄士幌線のコンクリート橋で、ダム建設に伴い1955年に水没しました。
水力発電用のダムであるため水位が季節によって変動し、冬には水没、5月頃には水が干上がって橋の姿が現れると説明。この橋はコンクリート製で、現地調達の石が使われており、凍結と融解を繰り返す特殊な環境によって、地上の50倍のスピードで風化が進んでいるとされています。
その結果、70年しか経っていないにもかかわらず、古代ローマ時代の遺跡のような不思議な風景を呈していると語りました。
広島の廃線「尾道鉄道」と「鞆鉄道」の物語
野川氏は「てつたま」のコーナーで取り上げた広島県内の廃線についても言及しました。
- 尾道鉄道: 尾道と三次、さらには日本海側を結ぶ壮大な計画があったものの、御調町の市駅までしか開通せず、車の普及により1964年に廃止されました。現存するトンネルは、電気機関車が走っていたため煤煙による汚れが少なく、現在でも比較的きれいに残っており、千と千尋の神隠しのような神秘的な雰囲気が漂うと紹介しました。
- 鞆鉄道(ともてつどう): 福山駅から観光地・鞆の浦を結んでいた路線で、1913年に開業し、全長12.5km、軌間762mmの小型蒸気機関車(チンチン電車)が走っていました。福山が陸上交通の拠点、鞆が海上流通の拠点として、両地域を結ぶ役割を担っていました。最盛期には年間147万人を輸送しましたが、芦田川の改修工事に伴う線路付け替えや自動車の普及の波に飲まれ、1954年に廃止されました。野川氏は、地元の宇田氏を案内役に、かつての水呑駅付近や水呑町三新田の鉄橋跡など、現在の街中に残る鞆鉄道の痕跡を辿り、特に水呑町三新田の鉄橋跡は鞆鉄道最大の遺構であり、100年以上前の非常に頑丈な作りであったと紹介しました。
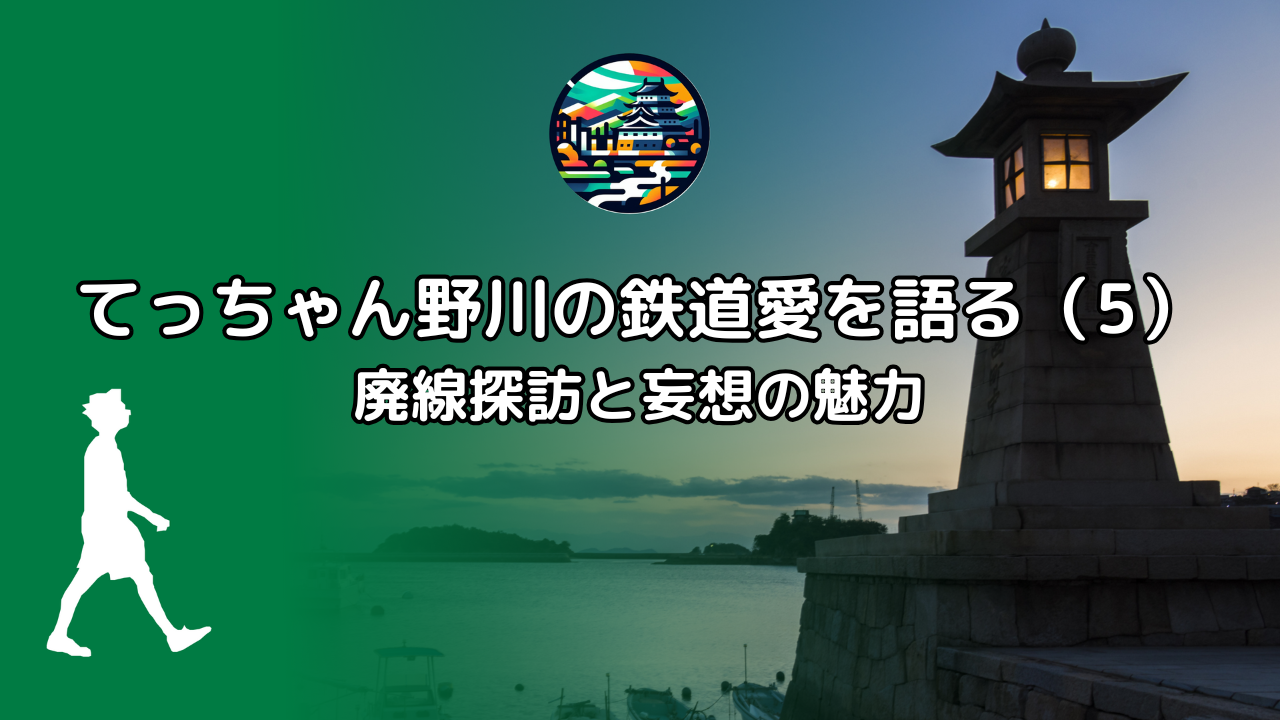
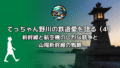
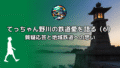
コメント