福山市の小学校で実施された出前授業
広島県福山市の小学校では、イノシシとの遭遇が相次いでいることから、児童が対処法を学ぶ出前授業が行われました。福山市内では2025年度はイノシシによる負傷はゼロですが、2年前の2023年度には噛みつきや追突によるけがが4件確認されています。
特に、市立宜山小学校の周辺の通学路では、8月中旬以降、親1頭と子ども3頭のイノシシが目撃されています。目撃現場周辺には、イノシシが掘り返した跡や切断されたワイヤ、好物の栗の木などがありました。
イノシシの生態と遭遇時の適切な行動
この授業では、県鳥獣対策等地域支援機構(tegos)の講師らが、イノシシは臆病な性格であり威嚇をしなければ人を襲うことはないが、大人の人間と同じくらいの重さである70kgを持ち上げられる力がある、といった生態をクイズ形式で教えました。
遭遇した際の具体的な対処法として、以下の点が指導されました。
- 大声を出さず、パニックにならないようにする。
- イノシシに背中を向けずに、後ろ向きでゆっくりと離れる。
- 高いところに移動する。
- もし近づいてきたら、ランドセルなどの物を投げて注意をそらし、その間に逃げる。
- 山に入る際は、鈴や音の鳴るものを身につける。
- 足跡やフンを見つけたらすぐに引き返す。
児童たちは、教室に置かれたイノシシの牙や剥製を触り、その大きさを実感して危険性を肌身で感じ取りました。PTA会長は、子どもたちだけで対処することは難しいため、遭遇時の適切な対応や、遭遇しないための工夫を学ぶことが有意義だったと語っています。
福山市は、今後も要望があればtegosと連携した出前授業を行っていく方針であり、箱わなを設置するなどの対策も進めていく予定です。
私の見解
今回の出前授業は、単なる危険回避教育ではなく、地域に根差した「共生と安全確保」の学びとして価値があると思います。
- 背景の切実さ
- 福山市内ではイノシシによる負傷事例が過去に確認されており、特に小学校周辺での目撃が続く現状は深刻。
- 通学路という日常の安全に直結する場所であるため、教育現場での対策は必須。
- 授業の実効性
- 生態を知ることで「むやみに恐れるのではなく、冷静に対処する姿勢」を養うことができる。
- 剥製や牙を触る体験は、机上の学び以上に子どもたちに強い印象を残す。
- 地域社会への波及効果
- PTAが指摘するように、子どもだけでなく家庭・地域ぐるみでの防災・防犯教育につながる。
- 今後の出前授業や箱わな設置は、住民と行政の信頼関係を築く意味でも重要。
総じて、自然との接し方を学ぶ教育は、都市部や地方を問わず今後ますます必要になると考えます。
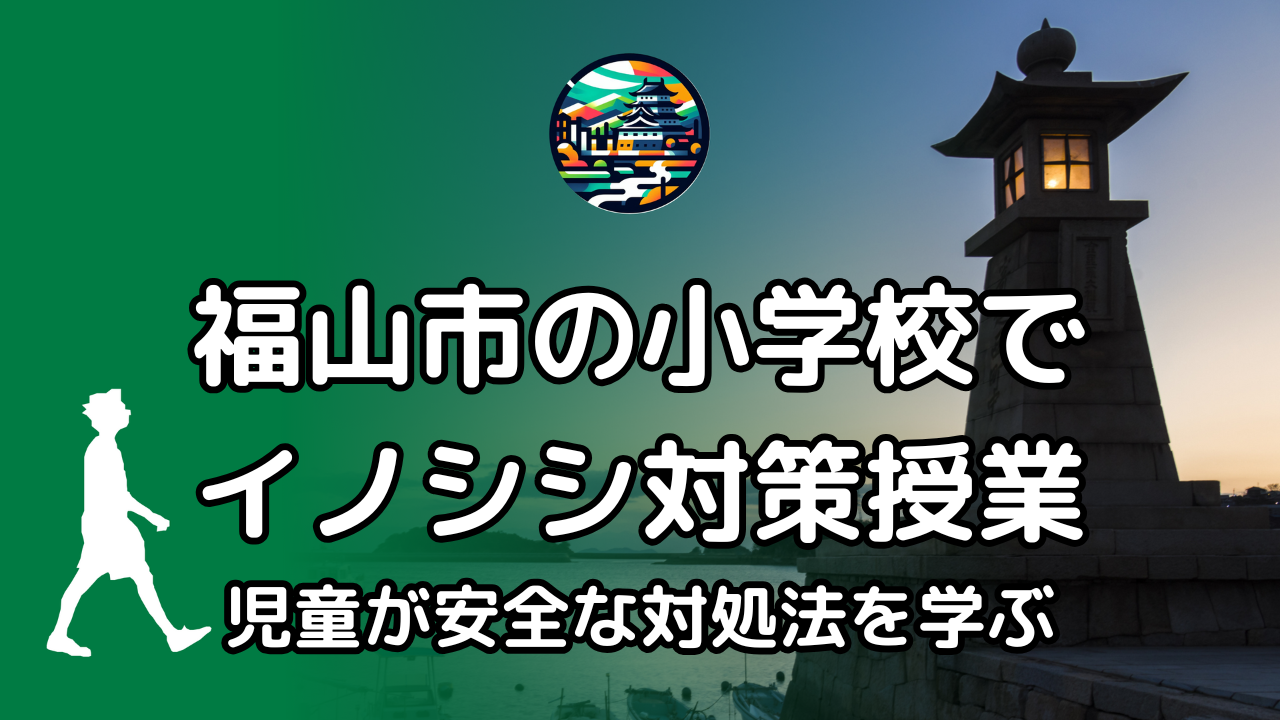
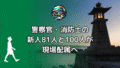
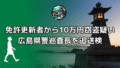
コメント