イベント概要と開催場所
国内外で折り紙ヒコーキの普及活動を行っている折り紙ヒコーキ協会(広島県福山市、会長:戸田拓夫)は、日本航空(JAL)社員による空の仕事についての講座やワークショップ、滞空時間選手権などを盛り込んだ「JAL DAY」を2025年9月27日(土)10時より開催します。これは2019年以来、6年ぶりの開催となります。開催場所は、紙ヒコーキを投げるために建てられた世界唯一の施設「とよまつ紙ヒコーキ・タワー」(広島県神石高原町下豊松381)です。
多彩なプログラム
イベントでは、JALグループが実施する次世代育成プログラム「空育®」が体験できる「JAL社員による空育 in とよまつ」(14:00~14:30)が開催され、パイロットやキャビンアテンダント、整備士など、空で働く人々の仕事を身近に感じ、学びを深めることができます。
また、「滞空時間選手権」(10:00~16:30、参加費200円)では、過去の最高記録21分4秒の記録更新にチャレンジでき、0.1秒以上飛べば景品がもらえ、滞空時間に応じて景品が豪華になります。折り紙ヒコーキ協会スタッフによる「よく飛ぶ紙ヒコーキ」のワークショップも随時開催され、入館者にはサトウキビの搾りかすで作った環境にやさしい専用用紙「バガス紙」5枚が提供され、よく飛ぶ折り紙ヒコーキの折り方を教えてもらえます。
さらに、「JAL KIDS STUDIO」(10:30~15:00)では、パイロットやキャビンアテンダント、整備士の制服を着て記念撮影ができます。入館料は300円で、小学生以下は無料です。
とよまつ紙ヒコーキ・タワーと協会の紹介
「とよまつ紙ヒコーキ・タワー」は、2003年に広島県神石高原町下豊松の米見山山頂(標高663m)に建てられた、世界的にも珍しい、展望台から紙ヒコーキを飛ばすことができるタワー施設です。エレベーターで地上15mまで上がると、360度を見渡せる展望台があり、遠くに大山や道後山、比婆山連峰などを臨むことができます。2013年4月からは「恋人の聖地/神石高原のシンボル施設」の記念銘板が設置され、恋愛成就・良縁成就の願いを込めた「ラブコプター」を飛ばすこともできます。
折り紙ヒコーキ協会は1995年に設立され、日本の伝承的文化である折り紙ヒコーキの普及活動及び認定指導員の育成・指導に取り組んでいます. 会長は室内滞空時間ギネス世界記録保持者(29.2秒)の戸田拓夫氏が務めており、2009年に室内滞空時間で27.9秒のギネス世界記録を達成し、その後29.2秒に更新しています。また、1,000機以上の紙ヒコーキが展示される「紙ヒコーキ博物館」(広島県福山市)や、とよまつ紙ヒコーキ・タワーの建設、多数の著書出版を通じて、折り紙ヒコーキの楽しさを世界中の人に伝えています。戸田氏が社長を務める株式会社キャステムは、折り紙ヒコーキ協会の活動を支援しています。
「JAL DAY in とよまつ紙ヒコーキ・タワー」タイムライン(2025年9月27日・土)
| 時間 | プログラム | 内容 |
|---|---|---|
| 10:00~16:30 | 滞空時間選手権 | 参加費200円。過去の最高記録21分4秒に挑戦。記録に応じて景品がもらえる。 |
| 10:00~随時 | 「よく飛ぶ紙ヒコーキ」ワークショップ | 折り紙ヒコーキ協会スタッフが指導。入館者には環境配慮の「バガス紙」5枚を配布。 |
| 10:30~15:00 | JAL KIDS STUDIO | パイロット、キャビンアテンダント、整備士の制服を着て記念撮影ができる。 |
| 14:00~14:30 | JAL社員による空育 in とよまつ | JAL社員による講座。空の仕事(パイロット・CA・整備士)を紹介。 |
| 随時 | 紙ヒコーキ体験・ラブコプター | 展望台から紙ヒコーキ飛ばし体験。恋人の聖地「ラブコプター」を飛ばすことも可能。 |
私の見解
「JAL DAY in とよまつ紙ヒコーキ・タワー」は、航空業界と折り紙ヒコーキ文化が融合したユニークなイベントであり、教育的意義とエンターテインメント性を兼ね備えています。特に、JALの次世代育成プログラム「空育®」を通じて、子どもたちがパイロットやキャビンアテンダント、整備士の仕事を知る機会を得られることは、将来の進路選択や職業観の形成に大きな影響を与えると考えられます。
また、「滞空時間選手権」や「よく飛ぶ紙ヒコーキ」ワークショップといった実体験を伴うプログラムは、遊びの中に科学的な学び( aerodynamics, 材質の違いによる飛行性能の変化など)を自然に含んでおり、STEAM教育の一環としても価値があります。さらに、バガス紙の活用や「ラブコプター」など環境配慮・地域性を盛り込んでいる点も評価できます。
「6年ぶりの開催」という希少性や、世界唯一の「紙ヒコーキ専用タワー」という舞台設定も相まって、地域の観光振興と教育普及を両立させるモデル的イベントと言えるでしょう。

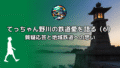
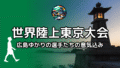
コメント