日本の漁業生産量減少に挑む栽培漁業
基調講演は、福山大学生命工学部海洋生物科学科の太田健吾教授によって「稚魚のゆりかご尾道の海を大切に」と題して行われました。太田教授は、約20年間国立研究機関で瀬戸内海の栽培漁業の研究に携わってきた経験があり、魚類の親魚養成や種苗生産、放流技術の開発が主な研究テーマです。
教授は、日本の漁業生産量が1984年をピークに右肩下がりであるのに対し、養殖業の生産割合は約20%で推移している現状を分析しました。戦後の沿岸漁業の急速な発展や遠洋漁業への転換が、沿岸資源の圧迫や漁業の空洞化を招いたとされています。
太田教授は、資源を持続的に利用するための方法として、良質な親魚から卵を採り、減耗が激しい稚魚の時期を人の管理下で育てて放流する「積極的な資源管理」としての栽培漁業のプロセスを解説しました。特に、成長に時間がかかるため養殖に不向きなオニオコゼやキジハタ(アコウ)は、この栽培漁業の対象魚種であり、尾道の貴重な資源として利用されています。教授の研究室では、オニオコゼの稚魚に背びれの棘を抜くという標識を付けて放流する取り組みを実施し、実際に3年後に全長20cmを超える個体が水揚げされた成功事例が紹介されました。
アサリ減少の複雑な原因とタコ養殖の最先端
パネルディスカッションに先立ち、国立研究開発法人水産研究・教育機構(水産研究・教育機構)水産技術研究所の伊藤篤部長が特別報告を行いました。伊藤部長は、尾道市百島にある庁舎に勤務し、主に無脊椎動物(背骨がない生き物)の研究に携わっています。
伊藤部長は、広島県東部がかつて有数の産地だったにもかかわらず、アサリの漁獲量が激減し、最盛期の0.5%以下にまで落ち込んでいる危機的な状況を報告しました。その減少要因は複雑で、干潟の減少、乱獲、温暖化、異常気象に加え、捕食生物(ツメタガイなど)の増加、水質悪化、そして海が綺麗になりすぎたことによる餌(植物プランクトン)不足など、複数の仮説が挙げられています。
アサリ資源回復のため、干潟に網を設置する保護活動(アサリ養殖)が試され、1年半後にはアサリが大量に回復した事例が示されましたが、網が破損したり、カキや海藻が付着したりする問題から、漁業だけでなく農業的な発想での管理が必要であると指摘されました。
また、資源減少が著しいマダコについては、卵から孵化させて大きく育てる養殖技術の研究が進められており、養殖されたタコは天然ものと遜色ない品質に達しているものの、タコが肉食で共食いする性質や、水槽から逃げ出す(脱走)という問題が、今後の課題として挙げられました。
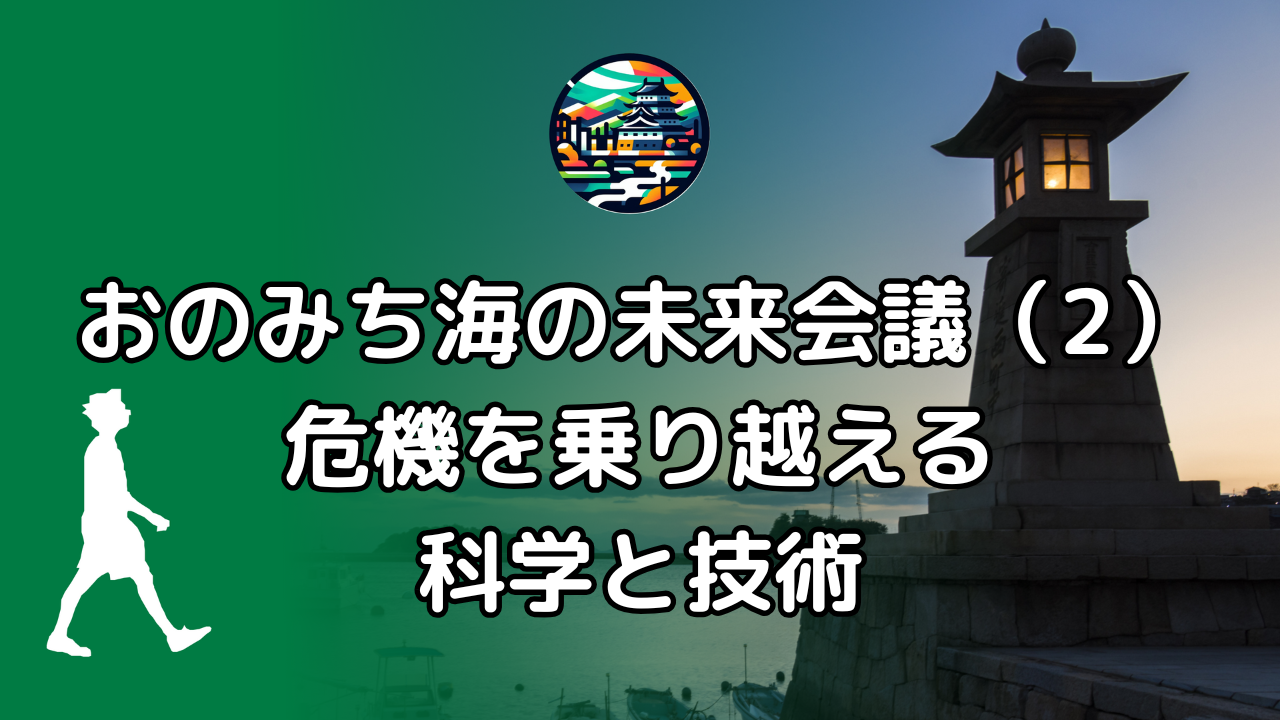
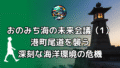
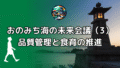
コメント