事故発生から1年:今なお続く住民の仮住まい
事故の概要と復旧の進捗
広島市西区福島町の市道陥没事故は9月26日で発生から1年を迎えました。事故は、地下約30メートルで雨水管を整備する市の工事中に発生し、陥没は東西約40メートル、南北約30メートル、深さ最大約2メートルに及びました。事故の影響で、建物19棟で傾きやひび割れなどの被害が確認され、このうち11棟はすでに解体されました。現在も11世帯20人が仮住まいでの生活を余儀なくされています。
地盤沈下対策とインフラ復旧
事故後も一帯の地盤はじわじわと沈下し、陥没中心地点から10メートル先の観測地点ではこの1年で約25センチ沈下しました。これに対し、市は7月末までに沈下を抑える地盤改良工事を完了させ、監視を続けています。下水道管の損傷も確認されましたが、修復作業は近く、10月中に終える見込みです。しかし、現場周辺は現在も関係者以外の立ち入り制限や通行止めが続いています。
原因究明の長期化と増大する費用
原因解明はさらに2年かかる見通し
事故原因を究明するための専門家による調査検討委員会は昨年11月に発足し、これまでに2回会合を開いています。これまでの調査で、事故は水平掘削を行っていた大型掘削機(シールドマシン)の内部に土砂が流入し、進行方向に空洞が発生し、地表が陥没したというメカニズムが分かっています。
現在は、マシンに土砂が流入した原因が焦点となっており、市は原因解明にさらにおよそ2年かかるとみています。原因究明のための現地調査は10月から着手予定ですが、地下に残るマシン周辺の地盤を凍結するなど安全確保の作業が必要です。
追加費用80億円以上、工期は3年以上遅延へ
復旧工事や住民への補償にかかる追加費用として、市は少なくとも80億円(または約82億円)を見込んでおり、内訳として、陥没埋め戻しや地盤沈下対策に約40億円、住民・事業者への補償に約12億円、掘削機調査などに約30億円が見込まれています。これらの費用負担は、原因解明後に施工業者との間で協議されます。
当初2028年3月を目指していた雨水管の完成は、原因究明と再発防止策の実施が必要なため、少なくとも3年は遅れる見通しで、工事の再開時期は未定です。
住民と市長の思い
地元の町内会長は、事故で地域を離れた人がいる寂しさを語り、原因究明と道路の早期復旧を望んでいます。近隣住民からは、地盤沈下が一番心配であること、近くに保育園があるため早めに安心して生活できる状態に戻してほしいという声が聞かれています。
広島市の松井市長は、避難住民に迷惑をかけている課題だとし、原因究明には時間がかかるが、手順を定めて慎重に進めていること、周辺住民への情報提供を工夫して丁寧に対応したいと述べています。
私の見解
福島町の市道陥没事故から1年経ってもなお20人が仮住まいを余儀なくされているという現状は、市民生活への影響の長期化を示しています。原因解明が2年、工事再開が未定という状況は、行政の説明責任や施工業者との責任分担をどう整理するかが大きな課題でしょう。
また、「地盤沈下の長期リスク」と「追加費用80億円以上」という数字は、市政の信頼性や今後の財政運営に直結する深刻な問題です。事故発生当初の「一時的な被害」から、「生活基盤に長く影響する災害」へとフェーズが移っている点が注目すべきポイントだと思います。
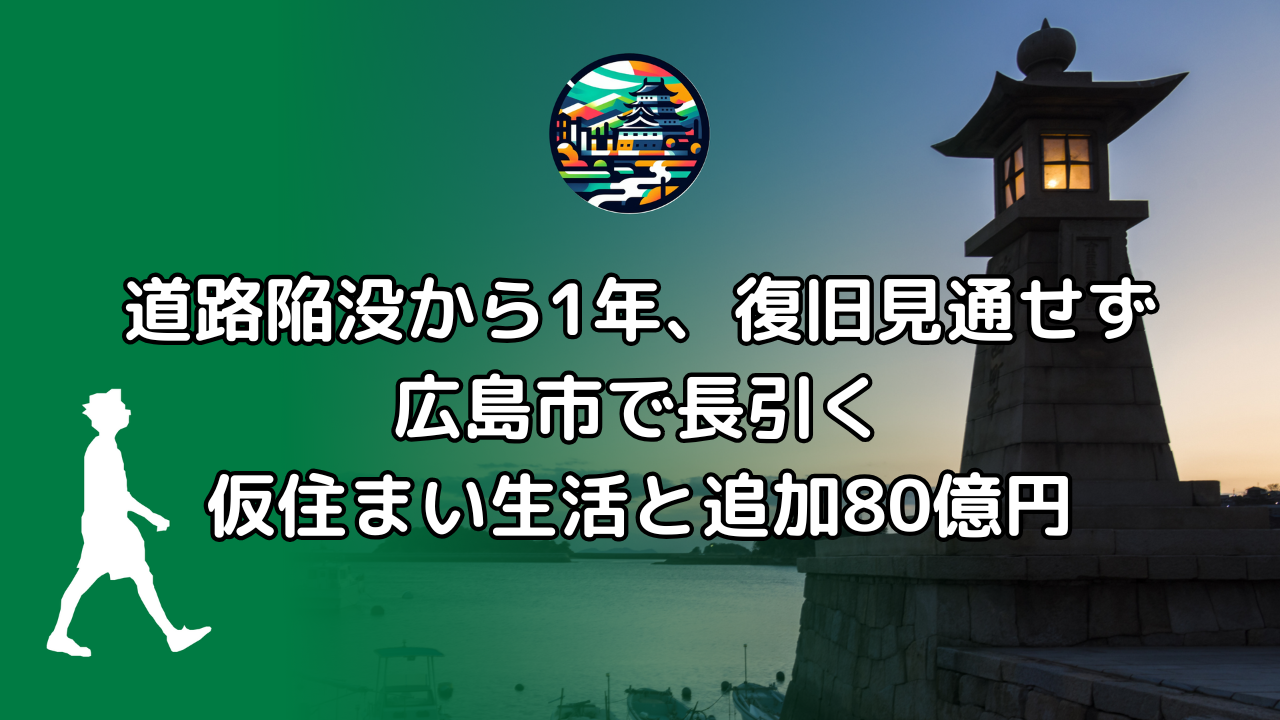
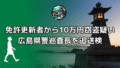
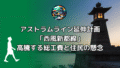
コメント