福山市の児童が芦田川で稚魚を放流
広島県福山市の芦田川では、10月7日に地元の福山市立光小学校の4年生約60人によるウナギとフナ(ヘラブナ)の稚魚の放流が行われました。
これは、水産資源や河川環境について学ぶ総合学習の一環として、芦田川漁業協同組合が主催したイベントです。児童たちは、稚魚に向かって「大きくなって帰ってきてね」と願いを込めながら放流しました。
地元漁協による種苗の自営養殖
芦田川漁業協同組合は、放流用のウナギとフナの種苗を自営事業として養殖しています。
ウナギは芦田川河口堰外で採捕したシラスウナギを、フナは芦田川で採捕した親フナをそれぞれ養殖し、毎年10月頃に地元の小学校の学習活動に取り入れて放流しています。この日の放流には、体長20~30センチのウナギ30キロ分が使用されました。
国土交通省福山河川国道事務所は、この放流イベントを通じて、芦田川の環境を守ることの重要性を呼びかけています。
私の見解
今回の放流活動は、子どもたちが自然とふれあいながら環境を学ぶ貴重な機会になったと思います。教室では学べない実体験を通して、生命の循環や地域の自然環境のつながりを感じることができたのではないでしょうか。
また、地元漁協が稚魚の養殖から関わる点は大きな意義があります。地域の人々の努力が川の環境を支えており、その連携を子どもたちが目にすることで、環境保全への意識がさらに高まると感じます。
芦田川は福山市を象徴する河川の一つです。こうした活動を通じて、地域全体で自然を守る気持ちが広がっていくことを期待します。子どもたちの経験が、未来の環境づくりの力になることを願っています。
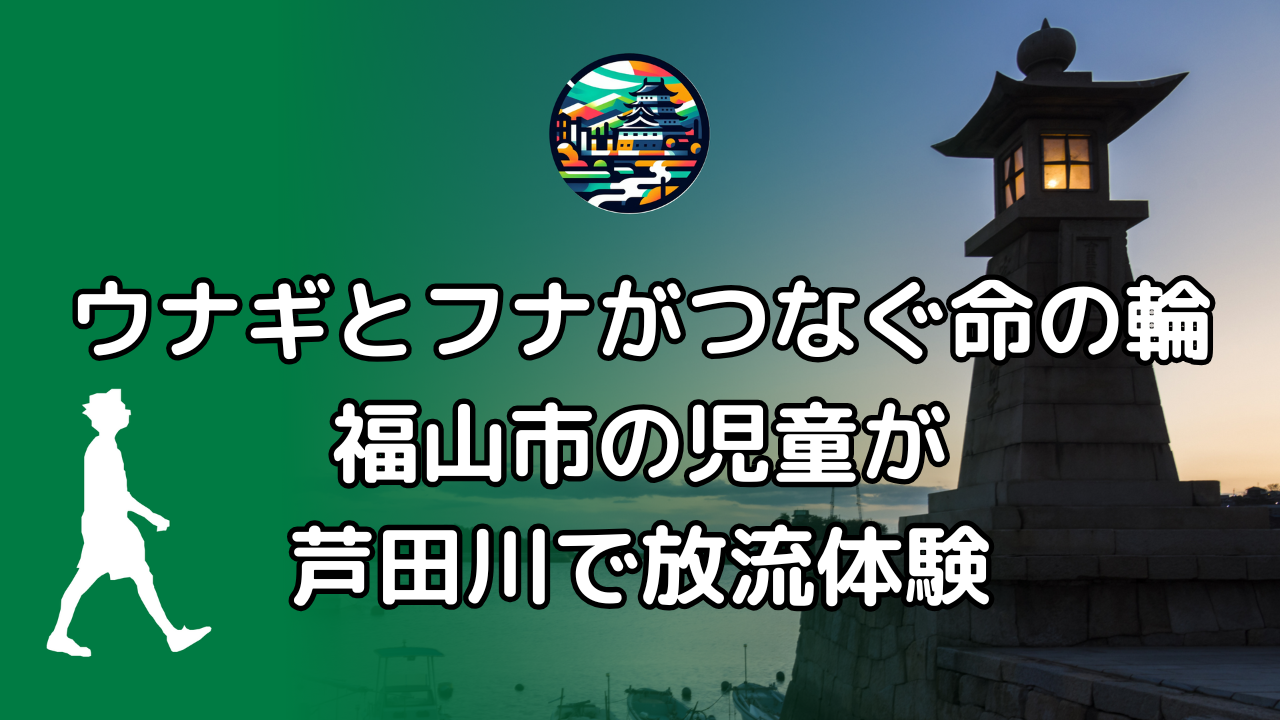
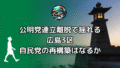

コメント