核軍縮の危機感と国際社会への提言
日本被団協の田中聰司代表理事は、ニューヨークの国連本部で開催された「核兵器の全面的廃絶のための国際デー」のハイレベル会合に出席し、核軍縮が停滞している現状に警鐘を鳴らしました。
田中氏は、核兵器使用のリスクは極限に達しており、人類が全滅の瀬戸際にあるとの危機感を強調し、人類が核兵器と共存することは不可能であると訴えました。また、核保有国の指導者に対し、被爆者と面会することで状況を打開するよう強く求めました。
この会合に合わせて、中央アジアのキルギスが核兵器禁止条約に署名し、アフリカのガーナが批准を発表しています。田中氏は、核保有国をわずかでも動かすことが最優先の課題であり、国連会議に出席する意義を強調しました。
核兵器禁止条約参加を求める市民の署名活動
広島市では、県内の7つの被爆者団体などが平和公園で署名活動を実施し、日本政府に対し核兵器禁止条約への参加を求めました。この活動は2か月に一度行われており、この日だけで170人分の署名が集まりました。
事務局長は、日本被団協のノーベル平和賞受賞以降、一回あたりの署名数が倍増していると報告しています。被爆者団体の理事長は、核兵器廃絶の課題を避けて政治が進むことはありえないとし、誰が総理大臣になってもこの課題を忘れないでほしいと要望しました。集まった署名は11月に政府へ提出される予定です。
世界核被害者フォーラム開催と「へいわ創造機構ひろしま」の法人化
核実験や原発事故などによる世界の核被害者たちが、10月5日と6日に広島市で「世界核被害者フォーラム」を開催します。
このフォーラムはHANWAなどが主催し、ウラン採掘による被ばく被害を受けたコンゴ民主共和国やインド、核実験の被害が広がったマーシャル諸島など、合計8か国から12人の核被害者が訪れ、健康被害の実態を報告する予定です。主催団体は、実態を世界に明らかにすることで、広島が核被害者のネットワークを強める原点になるべきだと語っています。
また、広島県が核兵器廃絶を目指して設立した任意団体「へいわ創造機構ひろしま」(HOPe)は、法人化(一般社団法人化)に向けて創立総会を開きました。
この法人化の目的は、県の関与を減らし、国連にNGOとして認定されることを目指すもので、これにより、県や任意団体では参加できなかった国連のプロセスに正式に参加し、国際社会に直接的な影響を与えられるようになると期待されています。
私の見解
この一連の動きから見えるのは、広島が単なる被爆都市にとどまらず、核廃絶の世界的ハブとして役割を果たしているということです。
- 危機感の共有:田中聰司代表理事が国連で示したように、核兵器使用のリスクは極限に達しており、現状の停滞は人類全体にとって深刻。
- 草の根の行動:平和公園での署名活動や被爆者団体の持続的な活動は、政治への圧力と市民意識の醸成に直結。署名数の増加は市民の関心の高まりを示す。
- 国際的ネットワーク強化:世界核被害者フォーラムの開催やHOPeの法人化は、広島から直接国連や国際社会に影響を与える基盤を作る重要なステップ。
- 戦略的意義:NGOとして国連プロセスに正式参加できることで、条約交渉や政策提言に参加し、核保有国に働きかける可能性が広がる。
総合的に見て、広島は「歴史的被害の記憶」を未来志向の外交・市民活動に変換しており、核廃絶に向けた国際社会のリーダー的存在としての価値を高めています。
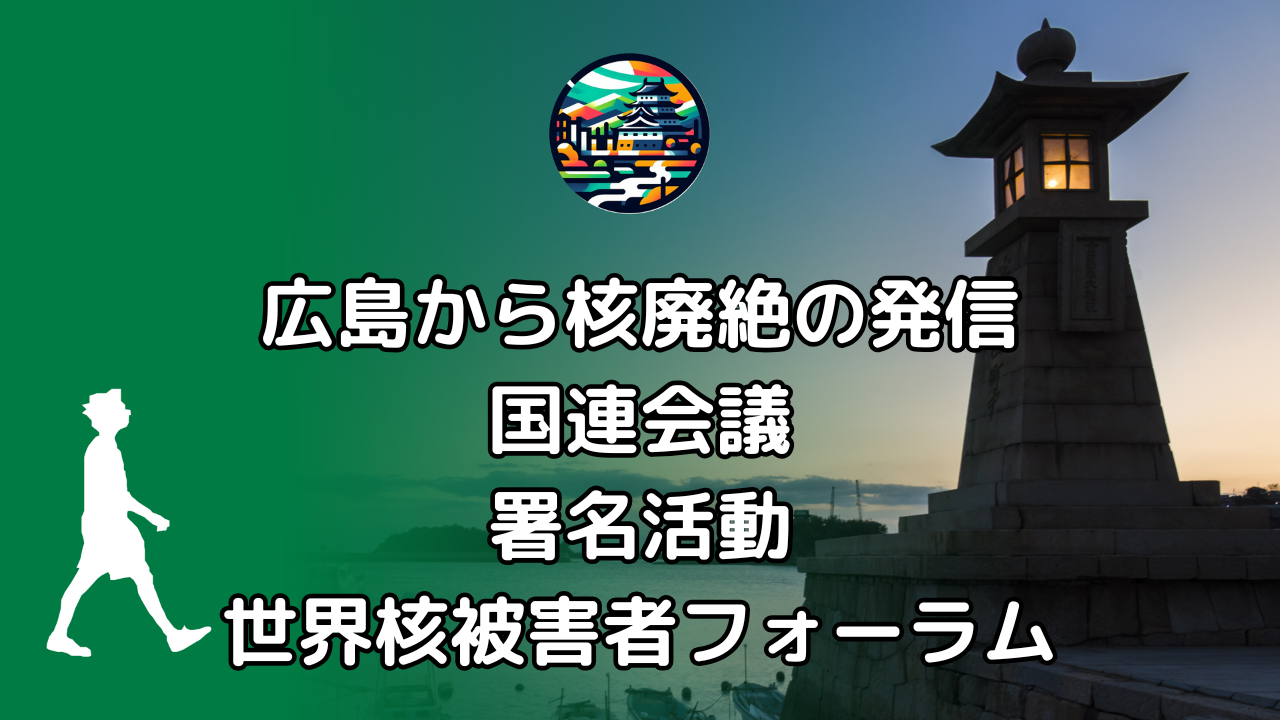
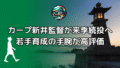
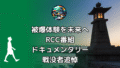
コメント