被爆体験の「継承」を評価された活動
基町高校による「原爆の絵」制作が高く評価
平和活動に貢献した個人や団体に贈られる谷本清平和賞が、広島市立基町高校普通科創造表現コースに授与されました。この賞は、被爆者支援に尽力した故・谷本清牧師の遺志を継ぎ、1987年から公益財団法人ヒロシマ・ピース・センターが毎年選定しています。基町高校の生徒たちは2007年度からボランティアとして活動を続け、被爆者から聞いた体験談をもとに「原爆の絵」を制作しています。生徒の有志は、約8カ月をかけ、証言通りになるように何度も描き直し、これまでに222点の絵を完成させ、今年も15点が原爆資料館に寄贈されました。選考センターは、被爆者の高齢化が進む中で、制作過程を通じて被爆体験が次世代に語り継がれている点を高く評価しました。学校側は、受賞が幅広い世代の人々が「平和のためにできること」を考え、実行する契機となることを期待すると述べています。
被団協のノーベル賞受賞後の変化と課題
2024年にノーベル平和賞を受賞した日本被団協は、受賞から約1年が経ち、世界からの関心が高まった一方で、新たな課題に直面しています。受賞後、原爆資料館の昨年度の入館者数は過去最多の220万人を超え、被団協の活動に対する認知度が上がり、署名活動の参加者数が倍増するなどの成果がありました。しかし、全国代表者会議では、被爆者の平均年齢が86歳を超え、語り部が減少している現状や、資金不足といった組織的な窮状が報告されました。代表委員の一人は、核兵器のない世界を目指す活動を生涯続ける必要性を述べつつ、若い世代が熱心に活動していることから、被爆者が一人もいない世の中が来ても心配はないだろうと若者へ期待を寄せました。
貴重な被爆資料の公開と記憶の伝達
原爆資料館の「新着資料展」と寄贈された遺品
広島市の原爆資料館では、2023年度に被爆者や遺族56人から寄贈された1400点以上の資料の中から、選定された126点の「新着資料展」が開催されています。展示されているのは、原爆投下時にきのこ雲を撮影したカメラ、学徒隊として建物疎開作業中に爆心地近くで亡くなった女学生の名札、亡くなった母親の代わりに心のよりどころとしてきた被爆仏像などです。寄贈者たちは、大切な人の記憶を後世に伝えたいという思いから、寂しさを乗り越えて資料を手放す決意をしたと伝えられています。この展示は2026年2月1日まで開催されます。
胎内被爆者の苦悩を伝える写真展
また、母親の胎内で被爆し、脳や体に重い障害を負った「原爆小頭症」の被爆者たちの日常を写した写真展「原爆が遺した子ら」が広島市内で開催されました。この写真展は、本人と家族の会である「きのこ会」が主催し、1966年から70年代初めに撮影された、日常の貴重な記録68枚が展示されました。小頭症の被爆者は長らく原爆放射線との因果関係が認められず、家族も偏見や差別に苦しんできました。きのこ会の事務局長は、この写真を通して原爆放射線が広島・長崎で何を引き起こしたのかを理解し、「どういう苦しみをしたのか知ってほしい」と来場者に訴えかけました。
国境を越えた平和のメッセージ発信
核保有国フランスでの被爆体験伝承
被爆から80年を迎え、被爆者の役割を継承しようとする若者の活動も活発です。25歳の被爆体験伝承者である井上つぐみさんは、核保有国であるフランスを訪問し、原爆孤児となった川本省三氏の被爆証言を伝えました。井上さんは、川本さんから託された紙飛行機と折り鶴を平和へのバトンとして大切にし、核兵器廃絶の重要性を訴えました。講話を聞いた現地のフランス人からは、原爆による直接的な被害だけでなく、被害者の苦悩を初めて知り、現在の世界的な戦争状況において行動する必要性を強く感じた、との反応がありました。また、被爆者は米国を恨んでいるのかという質問に対し、井上さんは、恨む気持ちはありながらも、被爆者たちが平和な世界を築くために皆で同じ未来を見ていくべきだと考えている、という川本氏の言葉を伝え、理解を得ました。
広島の玄関口から世界へ発信する芸術
広島の平和への願いを世界に発信するため、広島空港のターミナルビル外壁約200平方メートルに巨大壁画が制作されました。これは広島とメキシコの友好を記念するもので、メキシコ人のアーティストきょうだいが、平和の象徴である折り鶴や戦時下を生きた被爆者の姿を描き、核兵器のない世界への希望を込めています。制作前には被爆者から証言を聞き取る機会も設けられ、企画提案者によると、メキシコでは壁画が教育の題材となることが多く、平和のメッセージを伝える上で重要であるとしています。この壁画は10月15日に完成披露式が予定されています。また、市民目線で平和活動を続けるANT-Hiroshimaの理事長は、平和が手から滑り落ちていく危機感がある中で、被爆者から学んだ知恵を生かし、次の世代の未来を守るために全力を尽くすと決意を表明しています。
私の見解
基町高校の生徒たちが描く「原爆の絵」は、単なる芸術作品ではなく、被爆者一人ひとりの記憶を未来へ手渡す「証言の継承」そのものです。言葉を超えた表現を通して、戦争や核兵器の悲惨さを次世代が自ら考えるきっかけとなっており、教育と創造が結びつく平和活動の新しい形だと感じます。
被爆者の高齢化が進む中で、体験を語る人から聞く人へと、継承の主体が変わりつつあります。ノーベル平和賞を機に関心が高まる一方で、語り部の減少や資金難など現実的な課題も浮き彫りです。しかし、若者が新たな担い手として活動を広げていることに、広島が育む「平和の文化」の確かな芽を感じます。
芸術、資料、証言、写真──それぞれの形で広島の人々が平和を語り続けています。被爆80年を迎える今こそ、伝える努力を絶やさず、共に未来を描く姿勢が求められています。広島から世界へ、怒りではなく希望を発信することが、真の平和への第一歩だと思います。
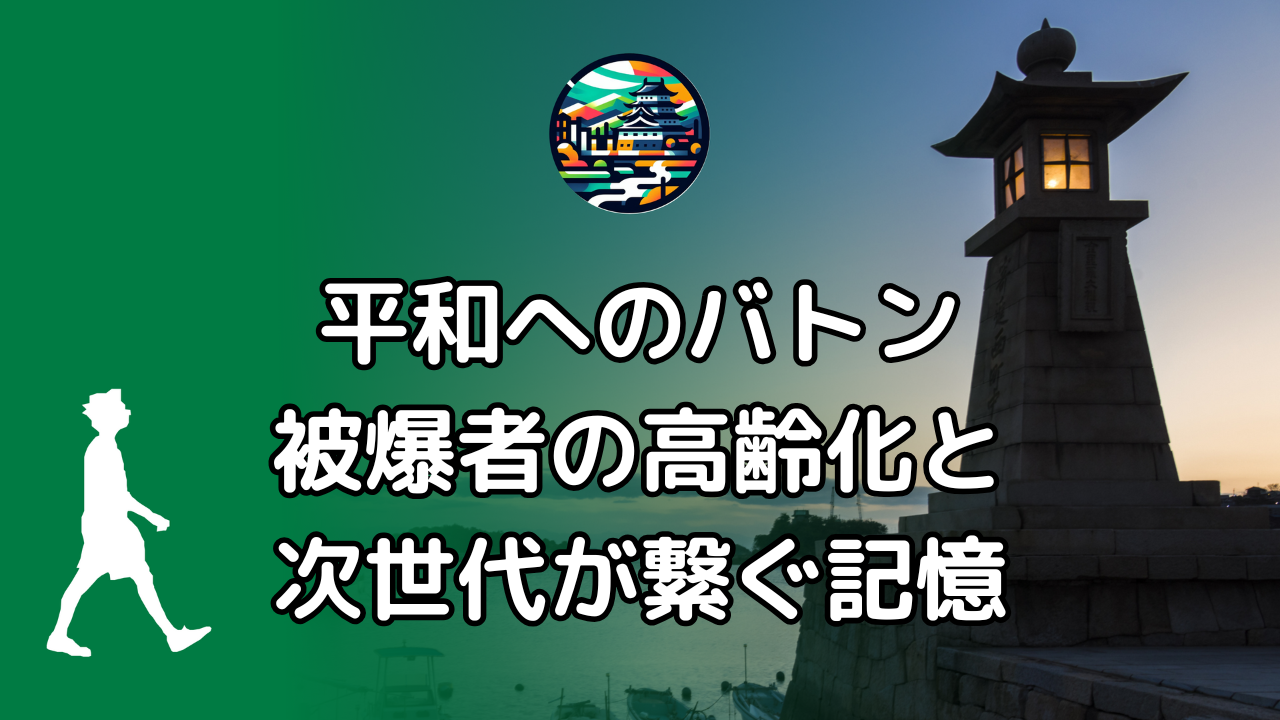
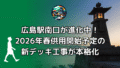
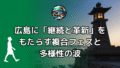
コメント