八潮市での陥没事故を受けた国の調査要請
2025年1月に埼玉県八潮市で大規模な道路陥没事故が発生したことを受け、国土交通省は全国の自治体に対し、老朽化した下水道管の特別重点調査を要請しました。この調査の優先対象は、設置から30年以上経過し、直径2メートル以上ある下水道管など、八潮市の事故現場と構造が類似している箇所です。
調査結果と緊急度1の管路の規模
9月17日に公表されたこの優先調査の結果、重度の腐食や破損が確認され、「原則1年以内の速やかな対策が必要」(緊急度1)と判定された下水道管が、全国35都道府県で合わせておよそ72キロメートルに上ることが判明しました。特に広島県内では、この緊急度1の管路がおよそ5.2キロメートルに及び、これは都道府県別で全国4番目の長さとなっています。
広島県内の状況と今後の方針
県内の内訳を見ると、広島県が管理する管路が約2.4キロメートルと最も長く、次いで大竹市が約1.6キロメートル、福山市が766メートル、広島市が441メートルとなっています。広島県は、鉄筋が見え始めている箇所など、腐食や劣化が進んでいる箇所から優先的に補修方法を検討し、早期の対策を講じる方針です。
国は、自治体に対し、「更生工法」(管の内側に新しい管を構築する手法)などを活用した補修を求め、技術面や財政面での支援を行うとしています。
私の見解
八潮市の陥没事故は、老朽化したインフラが持つ潜在的リスクを浮き彫りにしました。特に下水道管のように「目に見えにくい」施設は、更新や補修が後回しにされがちであり、結果として生活道路や住宅地で重大事故につながる危険があります。
今回の調査で「緊急度1」と判定された管路が全国で約72km、広島県内でも5.2kmと全国4位という数字は、地域の安全確保の観点から見ても看過できません。大竹市や福山市のように地方自治体が抱える距離も少なくなく、限られた予算・人員で対応するには国の財政支援と技術支援が不可欠です。
「更生工法」に代表される効率的な補修手法の導入は、コスト削減と工期短縮の両面で重要ですが、それだけでは十分ではありません。今後は、劣化の「予兆」を捉えるためのモニタリング技術の活用や、更新計画を中長期的に策定し、住民に公開する透明性も信頼性の確保に必要だと考えます。
つまり、陥没事故は単なるインフラ老朽化の問題ではなく、社会全体の「安全マネジメント」の在り方を問う事例であるといえます。
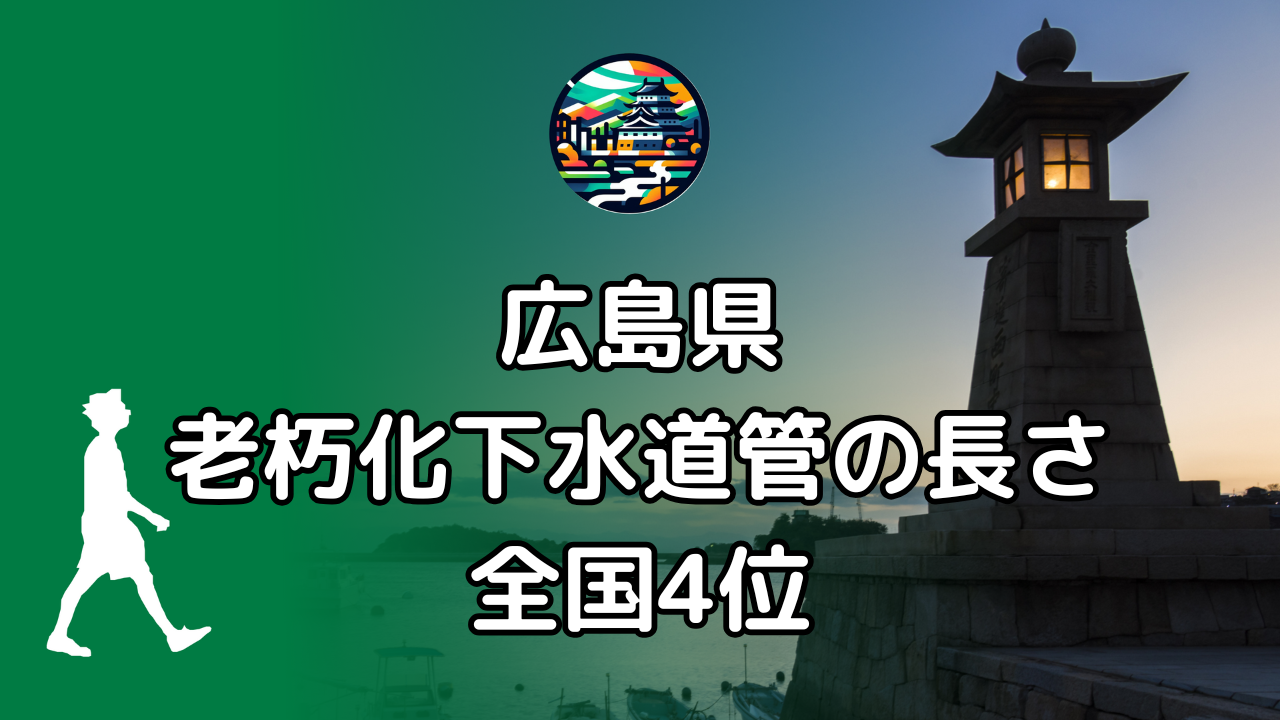
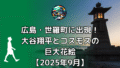
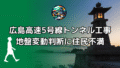
コメント