モデル事業の背景と目的
人が殺到するイベントでの雑踏事故などを未然に防ぐため、広島県警は2025年9月5日から、警備にあたる警察官が小型の「ウェアラブルカメラ」を装着する取り組みを開始しました。この取り組みは、3年前に韓国・ソウルの繁華街「梨泰院」のハロウィーンイベントで、集まっていた人が倒れて150人以上が死亡した事故を教訓としたものです。
警察庁が全国13都道府県で実施する「モデル事業」の一環として行われ、広島県警には頭部用と胸部用のカメラがそれぞれ1つずつ、計2台が導入されました。主な目的は、イベント会場などで人の流れを撮影し、離れた場所にいる指揮官がリアルタイムで映像を確認することで、危険を察知し、現場の警察官に適切な警備指示を素早く出すことにあります。これにより、事故の未然防止が期待されています。
運用体制と撮影方法
モデル事業の運用体制は、警察本部に総括運用管理者(警備部長)と本部運用管理者(警備部警備課長)が置かれ、警察署にも警察署運用管理者(警察署長)が配置されます。
ウェアラブルカメラによる撮影は、雑踏警備に際して適切な指揮を行う目的においてのみ実施され、雑踏警備以外の業務での活用は禁じられています。撮影者は、カメラを頭部または胸部に装着し、外形的に撮影を行っていることを認識できるよう取り付けるか、腕章を着用するなどの措置を講じます。撮影時は「ウエアラブルカメラ撮影中」と書かれた腕章などを身につけ、周知を図ります。
撮影場所は公道、イベント会場、駅などの公共の場所に限られ、イベント会場内や駅構内などの第三者の管理権限が及ぶ空間での撮影には、事前に管理者の承諾を得る必要があります。撮影は雑踏の概観や流れを重視し、不必要に参集者の容貌を撮影しないよう留意されます。指揮官は、送られてくる映像を受信し、適切な現場指揮を行います。
映像データの取り扱いと透明性確保
撮影した映像データは、個人情報保護法その他の法令に基づく場合を除き、雑踏警備における適切な指揮以外の目的で利用してはなりません。データは撮影日から1週間後に自動消去される仕組みとなっています。ただし、違法行為が撮影された蓋然性が高く、当該映像データを犯罪の捜査に利用するため法令に基づき求めがあった場合に限り、必要な部分を保存・提供することがあります。
モデル事業を実施する際は、撮影場所、撮影方法、データ消去期間、違法行為撮影時のデータ保存の可能性などをウェブサイトに掲載するなどして広報し、透明性を確保します。警察庁は1年間のテスト運用後に効果や課題を検証し、全国的な導入を検討するとしています。
私の見解
広島県警が開始したウェアラブルカメラのモデル事業は、雑踏事故の未然防止に向けた大きな一歩だと思います。特に以下の点で意義があります。
- 事故防止の実効性
現場の警察官の視界を離れた指揮官がリアルタイムで共有できることは、群衆の流れの変化を早期に察知し、迅速な警備指示につながります。これにより「事故が起きてから対応」ではなく、「事故が起きる前に回避」する体制が強化されます。 - 透明性とプライバシー配慮
撮影対象を「雑踏の概観」に限定し、個人の容貌を不要に映さない配慮や、データの短期間での自動消去ルールは、プライバシー侵害への懸念を抑える仕組みといえます。公開性(腕章着用やウェブでの周知)も信頼性を高める要素です。 - 課題
- カメラは2台のみと少なく、実際の大規模イベントで十分機能するかは検証が必要。
- 現場と指揮系統の通信が途切れた場合のリスク対応も重要。
- 国民の理解を得るには、どのような場面でどのように使われたかを検証・公開する仕組みが欠かせません。
総じて、この事業は「雑踏事故ゼロ」を目指す社会的要請に応える有効な取り組みであり、透明性とプライバシー配慮をどこまで実行できるかが成功の鍵になると考えます。
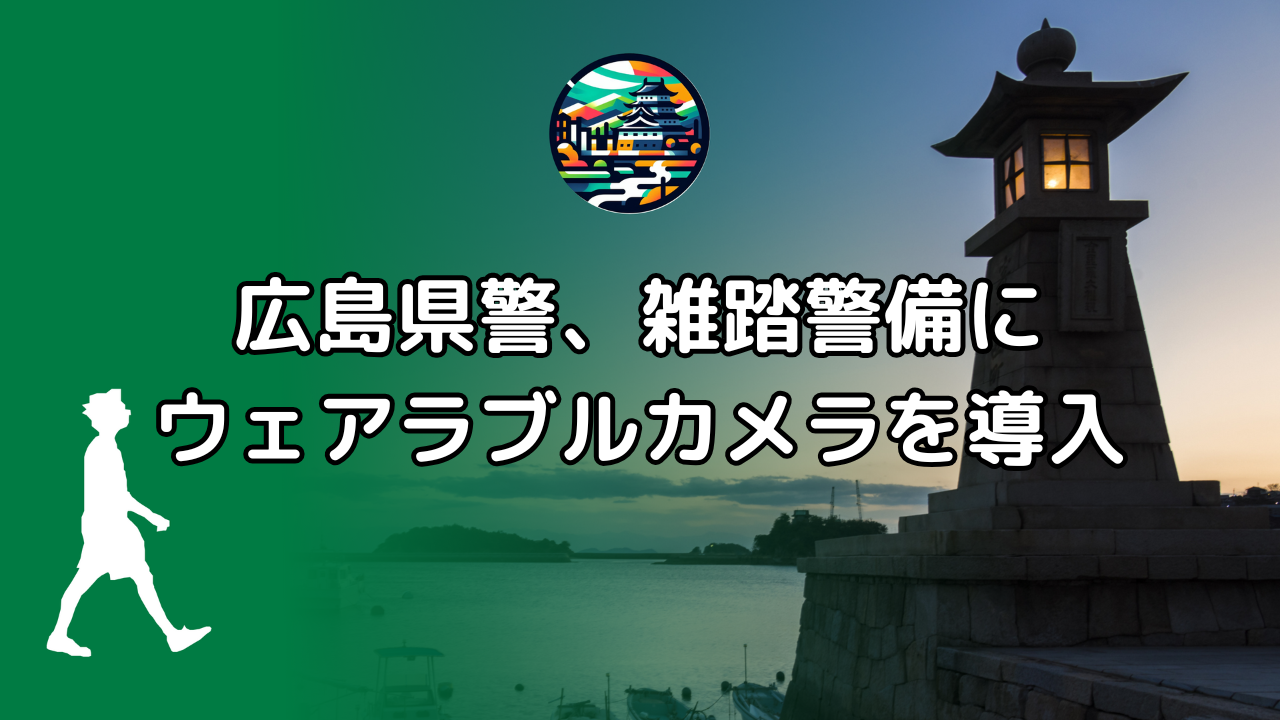
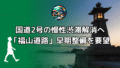
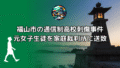
コメント