東海道新幹線と山陽新幹線のサービスの違い
「のぞみ」と「さくら」「みずほ」の座席仕様の違いは、東海道新幹線と山陽新幹線の路線特性の違いに起因すると野川氏は解説しました。東海道新幹線(東京-新大阪間)は、東京と大阪間の移動需要が非常に高く、3分から5分間隔で列車が来るほど本数が多いことが特徴です。JR西日本が公表しているデータによると、東京-大阪間の移動では、新幹線が75%、航空機が25%のシェアを占めており、これは航空機の搭乗手続きなどにかかる時間を考慮すると新幹線の方が有利であるためです。
しかし、東京-福岡間になると、新幹線が8%に対し航空機が92%とシェアが逆転します。これは福岡空港が街に非常に近いことが大きな要因だと指摘しました。東京-広島間では新幹線が60%、航空機が40%のシェアであり、約4時間を境に新幹線と航空機の有利不利が分かれると説明しました。
「ひかりレールスター」と「さくら」「みずほ」の登場
東海道新幹線が「スピーディーに座れる確率が高い」ことを重視する一方で、山陽新幹線(大阪-福岡間)は、東京-大阪間と比べて移動需要が少なく、福岡空港の利便性から航空機との競争がより激しい状況にありました。
この厳しい市場を勝ち抜くため、山陽新幹線は車内設備の工夫に力を入れました。かつて主力だった0系車両(最高速度210km/h)ではスピード面で不利があったため、当時の最速列車「ひかり」の車内設備を充実させ、2列+2列の座席配置や車内エンターテインメント、カフェなどを導入し、顧客を呼び込もうとしました。
しかし、それでもシェアは一時60%台にまで落ち込みました。そこでJR西日本は2000年に「ひかりレールスター」を投入。最高速度285km/hに向上し、2列+2列のゆったりとした座席が好評を博し、2008年にはシェアが80.9%にまで回復しました。
企業努力がもたらしたシェア回復
2011年には九州新幹線が開通し、山陽新幹線との直通運転が始まり、「さくら」「みずほ」が登場。最高速度は300km/hに達し、再び2列+2列のゆったりシートが採用されました。これは山陽新幹線が生き残りをかけてサービスを磨いてきた結果であり、その伝統が現在も「さくら」「みずほ」の座席に受け継がれていると強調しました。その結果、大阪-福岡間の新幹線シェアは2022年には87%まで回復し、野川氏はその企業努力を高く評価しました。
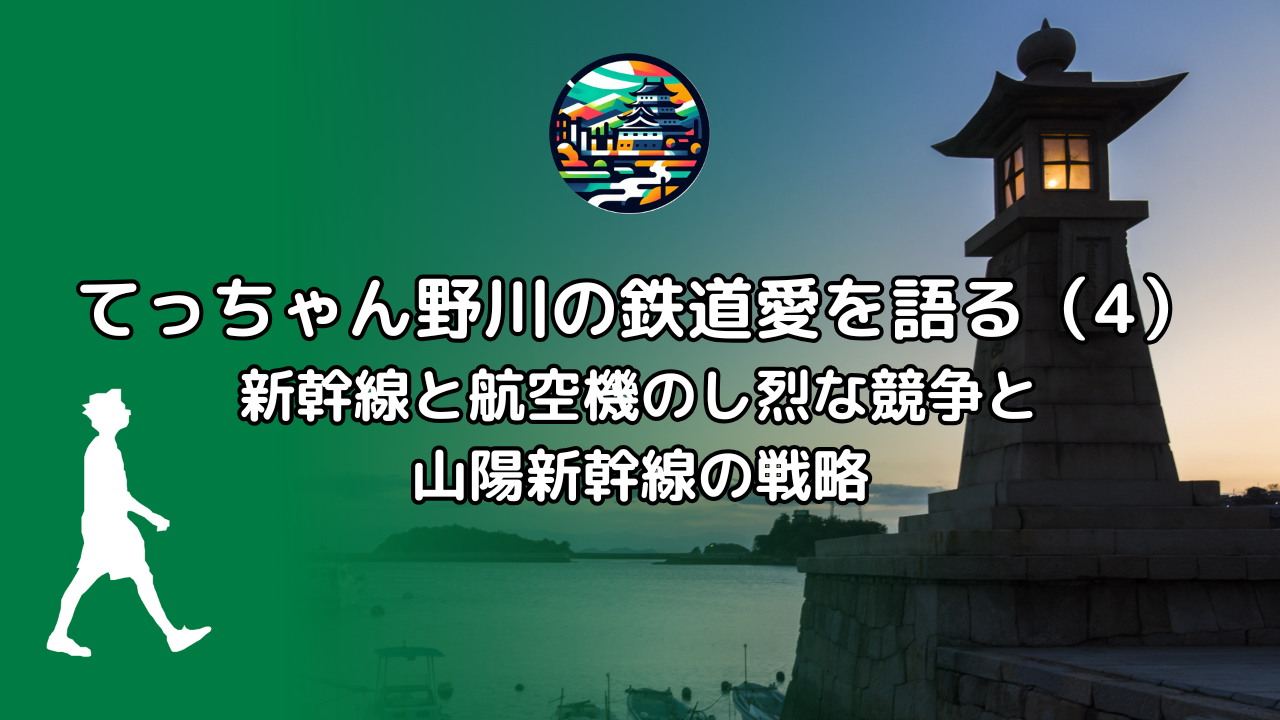
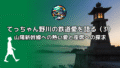
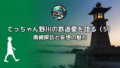
コメント