市街地での猟銃使用が特例的に可能に
クマやイノシシが市街地に出没した場合に、市町村の判断で猟銃の使用が特例的に可能となる改正法が2025年9月1日に施行されました。これは、市街地での猟銃使用がこれまで原則禁止されていた状況を改め、住民の安全を迅速に守るための措置です。猟銃の使用が可能となるのは、以下の4つの条件をすべて満たしていると自治体が確認した場合です。
- クマなどが人の生活圏に出没したり建物に侵入したりしていること
- 人への危害を防ぐ措置が緊急に必要なこと
- 迅速に捕獲できる手段がほかにないこと
- 住民の安全を確保できていること
環境省は、全国の市町村に対応マニュアルの作成を推奨していますが、広島県内の23のすべての市や町では、まだマニュアルを作成できていないのが現状です。
広島県、全国最多の被害状況を受け独自の対応指針を策定
広島県は、過去5年間でイノシシによる被害にあった人が全国最多の51人(うち広島市12人、福山市11人、尾道市10人)であることや、クマの目撃情報が昨年度789件(広島市233件、安芸太田町127件、廿日市市65件)と相次ぎ、市街地への生息範囲が拡大している傾向を受け、自治体が猟銃を使用する際の独自の対応指針を策定する方針を固めました。環境省によると、都道府県がこのような指針をまとめる報告はこれまでにないとのことです。
この指針には、猟銃使用を認めるべき状況、住民の安全確保策、損害が生じた場合の対応などが盛り込まれる予定で、専門家の意見も聴きながら具体的な内容を固め、県内の自治体に示されます。
自治体の戸惑いと今後の課題
市町村の担当者からは、「住宅密集地の基準が明確でない」「専門知識が乏しいので判断が難しい」「国は具体的な判断基準を示しておらず、市や町は責任を負えない」といった戸惑いの声が多く聞かれています。また、「発砲の判断は危機管理に関する部署が担当すべき」「警察や猟友会との連携が不可欠」など、これまでの枠組みを超えた関係機関との連携の必要性も指摘されています。
私の見解
市街地での猟銃使用を特例的に認めることは、住民の生命を守るための現実的かつ必要な手段だと思います。広島県のようにクマやイノシシの出没が常態化し、人身被害が全国最多となっている状況では、「原則禁止」のルールを守っていては対応が遅れ、命が奪われる危険性が高いからです。
ただし同時に、銃の使用は誤射や二次被害のリスクも伴うため、判断の基準と手順が極めて重要になります。
環境省が全国的なマニュアル作成を促しているにもかかわらず、多くの自治体が未整備という現状で、広島県が率先して独自指針を作ることは非常に前向きな一歩だと感じます。
「いつ撃てるのか」「誰が責任を持つのか」「住民にどう説明するのか」といった現場の迷いを解消し、県全体として共通認識を持つことは不可欠です。全国初という点でも他自治体のモデルになり得ます。
現場の戸惑いはもっともです。「住宅密集地の定義が曖昧」「専門知識が不足」「市町村が責任を負いきれない」といった声は、指針を作る上で真っ先に解決すべき課題。
特に 「誰が最終的に発砲を許可するのか」 は、責任の所在がぼやけたままでは危機管理として機能しません。
警察・猟友会・自治体・県が「共同で判断」する仕組みや、危機管理部門に一元化する体制が求められると思います。
銃を市街地で撃つとなれば、住民にとっては恐怖や不安も伴います。したがって、事前に
- 「どういう場合に発砲があり得るのか」
- 「そのとき住民はどう身を守るのか」
- 「もし損害が生じたら補償はどうなるのか」
といった情報を分かりやすく周知しておくことが信頼構築につながります。安全と透明性を両立することが大事です。
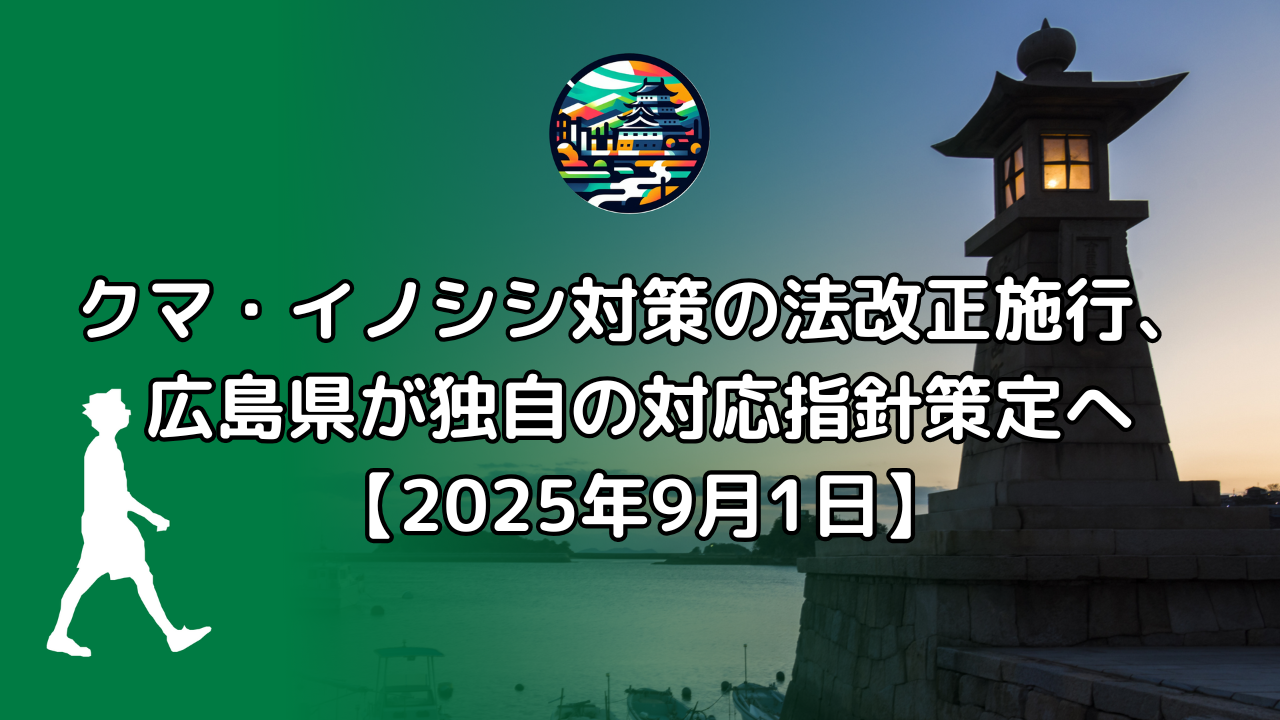
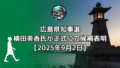
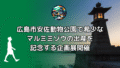
コメント