漁師の技術が築く「高品質ブランド」の確立
パネルディスカッションには、尾道漁業協同組合代表理事組合長の藤川伸一氏が登壇しました。藤川組合長は、海藻がなくなる「磯焼け」など生態系の変化を感じているとしつつ、稚魚放流などの資源造成事業が尾道漁業の存続に不可欠であると強調しました。持続可能な漁業のためには、行政と連携した資源管理(大きさの制限や禁漁区の設定)が重要であるという考えも示されました。
藤川組合長は、漁獲物の価値を高めるため、漁獲後の品質管理を徹底していると述べました。具体的には、迅速な血抜きや神経締め、氷水での冷却などを実施し、生産者を明記したバーコードを付けて市場に出荷することで、高い信頼とブランド化を図っています。この徹底した品質管理の結果、藤川組合長が獲った魚にはプレミアが付くほどであると紹介されました。
食育イベントを通じた若年層への魅力発信
尾道市地域おこし協力隊の坂本みゆき氏は、2024年10月1日に着任し、水産振興を担っています。坂本氏は、漁獲量が減少したアサリの保全活動に参加するほか、地元の魚を使った食育イベントに注力していると紹介しました。
特に、小学生を対象に鯛飯や魚ハンバーガーを作るイベントを実施し、若い世代に地元の魚の美味しさを知ってもらい、食べる機会を提供する活動の重要性を訴えました。
田中直樹さんは、講演の総括として、若い人が魚離れしている現状に対し、尾道の美味しい魚を食べる機会を増やし、地元の魚の魅力をアピールする必要性を訴えました。また、田中さんは、資源管理の重要性を強調し、一時的に漁獲を制限する「辛抱」が将来の資源回復に繋がるという意見を示しました。
海底のゴミ問題と「稚魚のゆりかご」の保全
太田教授と藤川組合長は、海の環境問題についても言及しました。太田教授は、稚魚の生育に必要な海藻やサンゴ礁などからなる「稚魚のゆりかご」のような天然の生息環境の保護が不可欠であると説きました。
しかし、漁場には陸上から河川を通じて流れ込むペットボトルやビールの缶などのゴミによる海底汚染が深刻であり、漁業者が自ら網にかかったゴミを回収している状況が報告されました。教授は、海を汚す原因が我々の身近な河川にあることを強調し、魚が戻る環境を守るためには、ゴミを捨てないよう配慮が必要であると示しました。
私の見解
尾道の海が抱える課題は、単なる環境問題ではなく、地域の食文化や暮らしに直結する大切なテーマです。今回のシンポジウムを通じて、世代を超えた対話が実現し、地域の未来を見据えた「共創」の姿勢が明確に示されたことは大きな意義があります。
「つくり育てる漁業」や食育イベントなど、科学と地域の力が結びついた実践が広がっていることに希望を感じます。持続可能な海を守るには、行政や研究者だけでなく、市民一人ひとりが意識を変え、行動することが欠かせません。
尾道の海が再び豊かに息づくためには、「魚を食べる」「ゴミを捨てない」といった日常の選択が鍵を握ります。私たちの小さな一歩が、次の世代に続く海の未来を支える力になると改めて感じました。
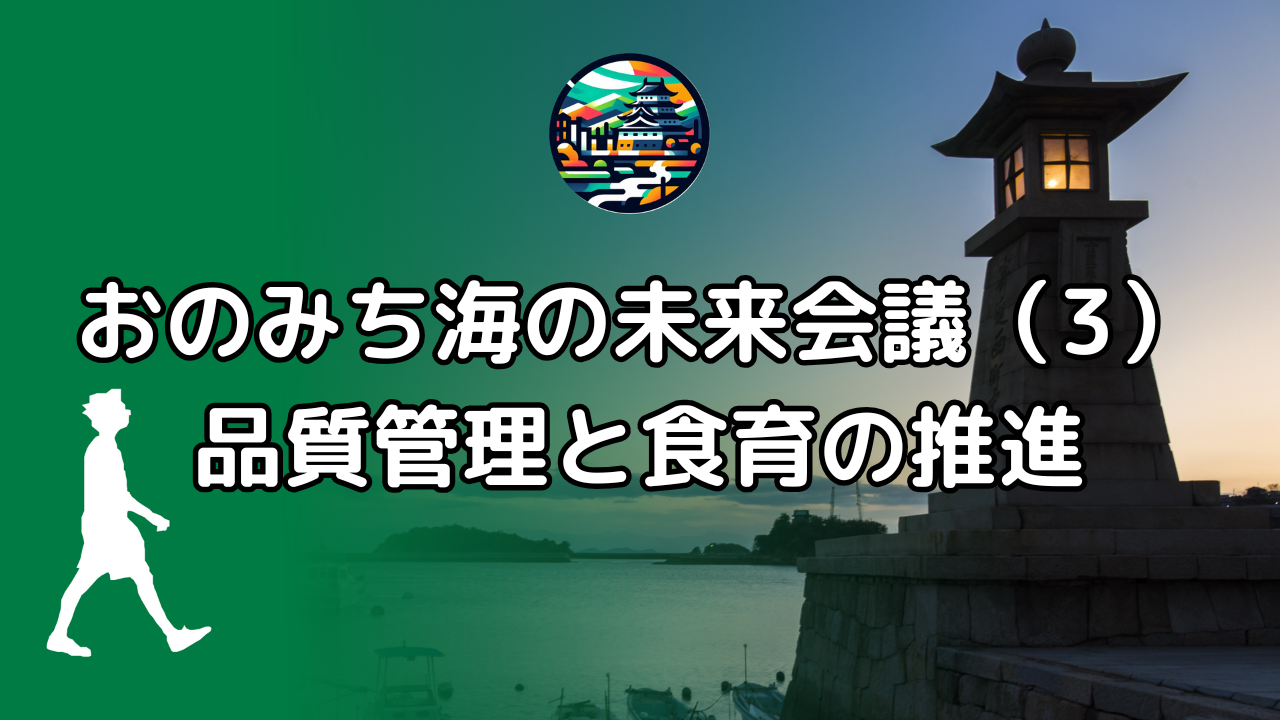
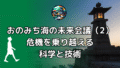
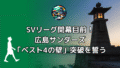
コメント